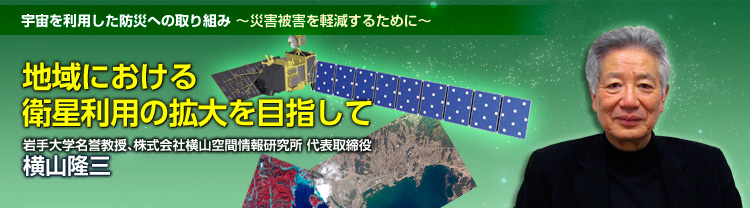Q. 昨年の東日本大震災においては、どのような取り組みを行いましたか?

![]()

「だいち」が観測した、震災前(上)と後(下)の岩手県陸前高田市周辺の様子。黄色丸には東西2kmに渡って松原が広がっていたが、津波により完全に流出した。(提供:JAXA/(株)横山空間情報研究所)
![]()
震災後すぐにJAXAと相談をして、津波の被害が大きかった岩手、宮城、福島県沿岸域の被災状況を把握するために、「だいち」の観測画像の解析処理を急遽始めました。そして、沿岸全体を撮った縮尺1/30,000の画像を、各県の災害対策本部、自治体、自衛隊、国の出先機関などに提供しました。岩手県沿岸だけでも画像の長さは長さ7mにもなりましたが、私自らがそれを関係機関に届けました。被災から5日後の3月16日のことです。
私は以前から「だいち」の観測画像の地域利用に取り組んでいましたので、3県の被災前の画像データも蓄積していました。ですから、被災前と後の画像を一緒に提供しました。被災から3週間後に国土地理院による空撮写真が出回るまでは、広範囲の被災状況を把握できるのは、この「だいち」の画像だけだったと思います。
Q. 提供した画像は具体的にどのように利用されたのでしょうか?
提供した被災前後の「だいち」の観測画像は、県庁や自衛隊の災害対策本部に貼り出されておりました。東日本大震災の被災地域は広範囲にわたり、多くの建物が津波で破壊され、電力や情報通信網、道路や電車などの交通網が遮断され、ガソリン不足で車も動かせない状況でした。半島の先端や離島など、町の中心から離れた場所の被災状況の把握と救援は困難を極めていたのです。このような厳しい状況下で、「だいち」の画像によって、所管する全域の被災状況を把握することができて大変役に立ったと聞いています。
Q. 自ら画像を持参されたとのことですが、自治体とのネットワークは以前からあったのでしょうか?

「だいち」が観測した震災前の岩手県山田湾の様子(2006年9月10日撮影)。(提供:JAXA/(株)横山空間情報研究所)
![]()

2012年12月に撮影された岩手県山田湾。湾の一部に復旧された筏が見られる。(提供:横山隆三)
「だいち」画像の地域実利用プロジェクトを通して、東北地方の自治体の方たちとは数多く仕事をしてきましたので、ネットワークはありました。私は、彼らとの共同研究などを通して、衛星データ利用の普及を行ってきたつもりです。このような関係から、自治体の方から直接私のところに「衛星画像データはないか?」という問い合わせも来るようになりました。
例えば、岩手県山田町の役場がその1つです。津波の数ヶ月後、山田湾の被災前の「だいち」画像がほしいという依頼がありました。山田湾では牡蠣やホタテ、ワカメなどの養殖が盛んで、湾内には4000台もの養殖筏が敷設されていたそうです。しかし、東日本大震災の津波により、筏は全部流されてしまいました。養殖を再開しなければ、山田町で漁業を営む人の収入がありません。そこで、筏が写っている被災前の画像を基に、山田湾の復興を行うことになったのです。震災から1年が経った今では、7割ぐらいまで復旧したそうです。
Q. 衛星を使った災害対策の課題は何だと思われますか?
災害が起きた時には、情報の迅速性と、その情報を必要としている人に確実に届けることが、災害対策に結びつきます。そういう意味では、普段から地域の方たちと連携してネットワークを作っておくことが大事です。先ほどの岩手県山田町のように、積極的に衛星データを利用しようと考えた方もいますが、それは決して多いわけではありません。衛星データの利用を地域社会に普及させる活動は、まだまだ不足していると感じています。
Q. 先生が目指す衛星データの利用とはどのようなものでしょうか?

毎日、テレビの天気予報で気象衛星「ひまわり」の画像が映し出されて、解説者の説明を聞き続けていると、普通の人でも画像を見ただけで「今日は雲がかかっているから傘を持っていった方がよいかな」といった、おおよその天気を予想できるようになります。今や、「ひまわり」の画像は市民生活にしっかり根づいているのです。
私は、「ひまわり」の画像のように、「だいち」など地球観測衛星の画像が一般社会に普及して、日常的に頻繁に利用されるような状況を作りたいと思います。農業や林業、水産などの分野に携わる人が、天気図を見るかのように地球観測衛星の画像を見て、その情報を自分たちの仕事に役立てるというイメージです。でも、そのためには有効な利用技術が必要ですね。
Q. JAXAに今後期待することや要望があればお聞かせください。
陸域観測技術衛星「だいち」は、日本の地域でも利用できる情報を提供する初めての衛星だったと思います。「だいち」は昨年の5月に運用を終了し、現在は、合成開口レーダを搭載した「だいち」の後継機、「ALOS-2」の開発が進んでいます。光学カメラを搭載する予定の「ALOS-3」はまだ検討段階ですが、光学カメラで撮った画像は、レーダによる画像よりも一般の方に分かりやすいので、普及という意味ではとても効果的です。ですから早く「ALOS-3」も打ち上げてほしいですね。これらの「だいち」の後継機によって、衛星データの地域利用がますます広がることを期待しています。
岩手大学名誉教授、株式会社横山空間情報研究所 代表取締役
1966年、東北大学大学院工学研究科電気及通信工学専攻修士課程修了。1970年、米国ロチェスター大学理工学部博士課程修了。1970年、東北大学工学部助手。1972年、岩手大学工学部助教授。1982年、岩手大学工学部教授。2005年、岩手大学特任教授として陸域観測技術衛星「だいち」データの地域実利用プロジェクトを推進。2011年、株式会社横山空間情報研究所を設立し、地球観測衛星や数値地図データの解析処理の受託事業をおこなっている。
地殻変動の検出で地震発生メカニズムを明らかに
防災に役立つ衛星による火山活動の把握
地域における衛星利用の拡大を目指して
「だいち」後継機で大規模自然災害に備える