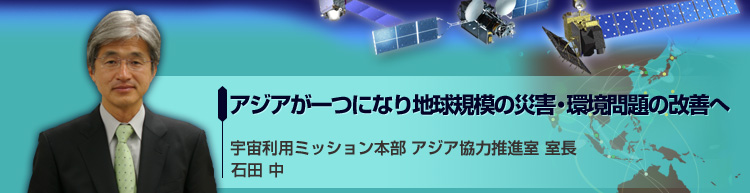
Q. JAXAの国際展開の中で、アジアはどのような位置づけなのでしょうか? JAXAはなぜアジアを重視しているのでしょうか?
JAXAが掲げる長期ビジョンには、「宇宙航空技術を活用することで、安全で豊かな社会に貢献する」という大方針があり、アジアについては、自然災害など地域の問題解決に宇宙技術を使ったシステムを実現、展開していくというビジョンが設定されています。
地球観測には、災害管理支援システムと地球環境観測予測システムという、2つの大きな柱がありますが、私たちの安全安心な社会をつくるために、アジア諸国との連携が欠かせません。気候変動などの地球環境問題にしても、産業経済にしても、アジア諸国は日本にとって、言わずもがな、隣国・隣人であり、密接に関係していますから、そういう意味でアジアは重要な地域だと思います。
また日本は、アジア地域における宇宙の先駆者として、気象衛星「ひまわり」の衛星情報をアジア太平洋地域30数ヵ国の防災に役立てるなど、貢献してきました。ですから、今後もアジアにおける宇宙先進国として、 JAXAがリーダーシップを発揮していくことが必要だと思います。「宇宙外交の推進」は、この6月に定められた「宇宙基本計画」にも国の方針として明記されていますので、JAXAはその方針に従ってシステムや衛星の開発利用を行い、アジアとの連携をさらに発展させていきたいと思います。
地球観測には、災害管理支援システムと地球環境観測予測システムという、2つの大きな柱がありますが、私たちの安全安心な社会をつくるために、アジア諸国との連携が欠かせません。気候変動などの地球環境問題にしても、産業経済にしても、アジア諸国は日本にとって、言わずもがな、隣国・隣人であり、密接に関係していますから、そういう意味でアジアは重要な地域だと思います。
また日本は、アジア地域における宇宙の先駆者として、気象衛星「ひまわり」の衛星情報をアジア太平洋地域30数ヵ国の防災に役立てるなど、貢献してきました。ですから、今後もアジアにおける宇宙先進国として、 JAXAがリーダーシップを発揮していくことが必要だと思います。「宇宙外交の推進」は、この6月に定められた「宇宙基本計画」にも国の方針として明記されていますので、JAXAはその方針に従ってシステムや衛星の開発利用を行い、アジアとの連携をさらに発展させていきたいと思います。
Q. APRSAFとは、どのような取り組みですか? なぜ、ASRSAFを設立したのでしょうか?
APRSAFは「Asia-Pacific Regional Space Agency Forum:アジア太平洋地域宇宙機関会議」の略で、アジアの宇宙機関が集まって、宇宙技術の開発と利用の協力を推進するという国際的な会合です。宇宙利用を進めるためには、宇宙機関だけではなく、利用機関やアジア各国の政府機関などの協力も必要ですので、そういった方々にも参加していただき、宇宙技術やその利用について議論して、進めています。
APRSAFは1993年に設立され、これまでに15回、ほぼ一年に一回のペースで、開催されています。1992年の「国際宇宙年」では、アジア太平洋地域で宇宙関係の会合が開催され、そこで、アジアが協力する枠組みを作るべきだという意見が多く出ました。そこで、国際宇宙年でアジア地域のイニシアチブをとっていた日本が中心となってAPRSAFを設立しました。当時はアジア各国で宇宙機関が発足し、宇宙開発への取り組みが始まった頃でした。その中で、アジア太平洋地域の国々が協力して一つになり、平和目的のために宇宙技術の発展と利用を推進するというのが、APRSAF設立の目的です。
APRSAFは1993年に設立され、これまでに15回、ほぼ一年に一回のペースで、開催されています。1992年の「国際宇宙年」では、アジア太平洋地域で宇宙関係の会合が開催され、そこで、アジアが協力する枠組みを作るべきだという意見が多く出ました。そこで、国際宇宙年でアジア地域のイニシアチブをとっていた日本が中心となってAPRSAFを設立しました。当時はアジア各国で宇宙機関が発足し、宇宙開発への取り組みが始まった頃でした。その中で、アジア太平洋地域の国々が協力して一つになり、平和目的のために宇宙技術の発展と利用を推進するというのが、APRSAF設立の目的です。
Q. APRSAFを15回続けてきて、メンバーは増えていますか? また、メンバーの宇宙開発、宇宙利用に対する意識は変わってきていますか?

第15回アジア・太平洋地域宇宙機関会議(APRSAF-15)はベトナムで開催(提供:APRSAF)
APRSAFは自主的な参加による会合ですから、国連のような決まったメンバーや、あるいは、会員制度というのはありません。宇宙機関のほか、主な利用機関や産業界などにも声をかけていますので、参加機関は確実に増えていると思います。昨年の12月にベトナムで開催された第15回APRSAFでは、20ヵ国から、200人以上の関係者が集まりました。最近は、この宇宙を通じたアジアの国際協力平和活動をアジア各国の政治家や国際協力機関にもご理解、ご支援してもらえるように、参加を呼びかけていますので、そういう点でも活性化してきていると思います。
また、参加者たちの意識も変わってきていると思います。やはり、宇宙技術を自分たちの地域の問題解決に役立てたいという期待感が大きいのと、実際に、「センチネル・アジア」による地球観測衛星の画像が災害時に役立つという協力の成果が出てきましたので、宇宙利用のメリットを実感する方たちが増えてきました。そして、宇宙を利用することによって実際に利益を受けた機関が、積極的に参加してきています。
実は、APRSAFが設立されてからの最初の10年間は、各国の技術者を中心とした宇宙開発に関する情報交換が主な取り組みで、その意味では、宇宙の平和利用のための技術者の交流という一定の成果は得ていたのですが、2003年頃から、APRSAFとして何か、アジアの宇宙機関が協力して具体的な宇宙利用の成果を出していこうと、プロジェクト型に切り替えることになりました。そして2006年に、アジア太平洋地域の自然災害の監視を目的とした、「センチネル・アジア」という国際協力プロジェクトを発足させたのです。このような方向転換を行った結果、参加者の意識がより具体的な成果を求めるように変わってきていると思います。
また、参加者たちの意識も変わってきていると思います。やはり、宇宙技術を自分たちの地域の問題解決に役立てたいという期待感が大きいのと、実際に、「センチネル・アジア」による地球観測衛星の画像が災害時に役立つという協力の成果が出てきましたので、宇宙利用のメリットを実感する方たちが増えてきました。そして、宇宙を利用することによって実際に利益を受けた機関が、積極的に参加してきています。
実は、APRSAFが設立されてからの最初の10年間は、各国の技術者を中心とした宇宙開発に関する情報交換が主な取り組みで、その意味では、宇宙の平和利用のための技術者の交流という一定の成果は得ていたのですが、2003年頃から、APRSAFとして何か、アジアの宇宙機関が協力して具体的な宇宙利用の成果を出していこうと、プロジェクト型に切り替えることになりました。そして2006年に、アジア太平洋地域の自然災害の監視を目的とした、「センチネル・アジア」という国際協力プロジェクトを発足させたのです。このような方向転換を行った結果、参加者の意識がより具体的な成果を求めるように変わってきていると思います。
Q. ASRSAFのメンバー国から、日本のどのようなことに期待が持たれているのでしょうか?
日本が期待されているのは、利用の観点からいうと、やはり災害監視です。日本は、「だいち」のような、最先端の地球観測衛星をもっているので、災害が起きたときの緊急観測やデータの提供など、災害監視に対する協力への期待は非常に大きいと思います。次に、環境監視の必要性も徐々に高まっています。日本は、今年1月に温室効果ガス観測衛星「いぶき」を打ち上げました。また、宇宙の技術、特に小型衛星を持ちたいというニーズがあり、そのための技術者の人材育成をしてほしいという要望があります。

ベトナムで行われたAPRSAF-15 水ロケット大会(提供:APRSAF)
Q. ASRSAFで、これまで特に成果が上がったものは何だと思われますか?
これまでの具体的な成果として、「センチネル・アジア」が挙げられます。2006年の第13回APRSAFで「センチネル・アジア」がプロジェクト化されて、今年でまだ3年しか経っていませんが、すでにアジアの各国の防災機関により定常的に利用され、国際的にも認められています。
「センチネル・アジア」は、災害が発生した際、衛星による「緊急観測」を行い、そのデータを災害状況の把握や被災地での対策で使ってもらうのが主な取り組みです。これまでに50回ほどの緊急観測を行っています。例えば、2008年5月に起きた中国の四川大地震では、日本が世界に先駆け最初に被災地の衛星データを提供したということで、中国からも非常に感謝されました。その他にも、インドネシアのメラピ山の噴火や、ジャカルタ地震、ミャンマーの洪水など自然災害が続き、JAXAの陸域観測技術衛星「だいち」の画像は、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、インド、バングラデシュのほか、南太平洋の島国であるサモアなどにも提供されています。
またAPRSAFでは、教育分科会が中心となって、アジア地域の子供たち向けの、宇宙に関する教育についても熱心な取り組みがなされてきており、宇宙教育の教材作成や理科実験である「水ロケット」のアジア大会を開催するなど、アジアの将来を担う子供たちの夢を育んできています。
これまでの具体的な成果として、「センチネル・アジア」が挙げられます。2006年の第13回APRSAFで「センチネル・アジア」がプロジェクト化されて、今年でまだ3年しか経っていませんが、すでにアジアの各国の防災機関により定常的に利用され、国際的にも認められています。
「センチネル・アジア」は、災害が発生した際、衛星による「緊急観測」を行い、そのデータを災害状況の把握や被災地での対策で使ってもらうのが主な取り組みです。これまでに50回ほどの緊急観測を行っています。例えば、2008年5月に起きた中国の四川大地震では、日本が世界に先駆け最初に被災地の衛星データを提供したということで、中国からも非常に感謝されました。その他にも、インドネシアのメラピ山の噴火や、ジャカルタ地震、ミャンマーの洪水など自然災害が続き、JAXAの陸域観測技術衛星「だいち」の画像は、インドネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、インド、バングラデシュのほか、南太平洋の島国であるサモアなどにも提供されています。
またAPRSAFでは、教育分科会が中心となって、アジア地域の子供たち向けの、宇宙に関する教育についても熱心な取り組みがなされてきており、宇宙教育の教材作成や理科実験である「水ロケット」のアジア大会を開催するなど、アジアの将来を担う子供たちの夢を育んできています。

超高速インターネット衛星「きずな」
Q. 「センチネル・アジア」は、今後、どのように発展させていくのでしょうか?
「センチネル・アジア」は3つの段階に分けて運用が進められており、2006年から2007年にかけてステップ1を成功裏に終了し、2008年1月からステップ2が始まりました。ステップ1は、インターネットを利用した防災情報共有システムを構築し、主として日本の地球観測衛星「だいち」と一部インドの衛星が使われました。ステップ2では、1)参加衛星の増加、2)データアクセスの改善、3)解析画像など付加価値情報の提供、4)モニタリングする災害項目の増加、という点に重点をおいて活動が行われています。
ステップ1では、洪水や森林火災をモニタリングするワーキンググループが設置されましたが、ステップ2では氷河湖の拡大や数の増加も観測しています。近年、地球温暖化の影響などで氷河が溶け、その水が貯まってできた湖(氷河湖)が決壊して洪水を発生することがあるため、その水害を防ぎます。また、JAXAの超高速インターネット衛星「きずな」を利用し、これまでインターネット環境が十分整備されていなかったような地域にも、高速でデータが送れるようにしたいと思います。また、日本やインドの衛星だけでなく、タイの地球観測衛星「THEOS(テオス)」や韓国の多目的実用衛星「KOMPSAT(コンプサット)」の観測データも「センチネル・アジア」に活用される予定で、協力が広がっています。さらに、中国も「センチネル・アジア」への参加と自国衛星データの「センチネル・アジア」への提供を検討しています。これまで中国へは災害時のデータ提供の実績があるほか、アジアの水循環の観測データの交換など研究者レベルでの協力は進んでいますので、今後、地球観測や宇宙科学などの分野へと、国同士の協力の輪が広がる可能性はあると思います。
ステップ3は2010年以降に実施される予定ですが、ここでは、これまで構築してきた災害管理支援システムを定常化することを目指しています。現在は、アジア防災センターに災害時の緊急観測要求の受付窓口となっていただいていますが、「センチネル・アジア」自体を現業機関に運用してもらうなど、利用の定着化と拡大につなげていきたいと思います。
「センチネル・アジア」は3つの段階に分けて運用が進められており、2006年から2007年にかけてステップ1を成功裏に終了し、2008年1月からステップ2が始まりました。ステップ1は、インターネットを利用した防災情報共有システムを構築し、主として日本の地球観測衛星「だいち」と一部インドの衛星が使われました。ステップ2では、1)参加衛星の増加、2)データアクセスの改善、3)解析画像など付加価値情報の提供、4)モニタリングする災害項目の増加、という点に重点をおいて活動が行われています。
ステップ1では、洪水や森林火災をモニタリングするワーキンググループが設置されましたが、ステップ2では氷河湖の拡大や数の増加も観測しています。近年、地球温暖化の影響などで氷河が溶け、その水が貯まってできた湖(氷河湖)が決壊して洪水を発生することがあるため、その水害を防ぎます。また、JAXAの超高速インターネット衛星「きずな」を利用し、これまでインターネット環境が十分整備されていなかったような地域にも、高速でデータが送れるようにしたいと思います。また、日本やインドの衛星だけでなく、タイの地球観測衛星「THEOS(テオス)」や韓国の多目的実用衛星「KOMPSAT(コンプサット)」の観測データも「センチネル・アジア」に活用される予定で、協力が広がっています。さらに、中国も「センチネル・アジア」への参加と自国衛星データの「センチネル・アジア」への提供を検討しています。これまで中国へは災害時のデータ提供の実績があるほか、アジアの水循環の観測データの交換など研究者レベルでの協力は進んでいますので、今後、地球観測や宇宙科学などの分野へと、国同士の協力の輪が広がる可能性はあると思います。
ステップ3は2010年以降に実施される予定ですが、ここでは、これまで構築してきた災害管理支援システムを定常化することを目指しています。現在は、アジア防災センターに災害時の緊急観測要求の受付窓口となっていただいていますが、「センチネル・アジア」自体を現業機関に運用してもらうなど、利用の定着化と拡大につなげていきたいと思います。