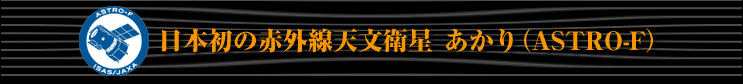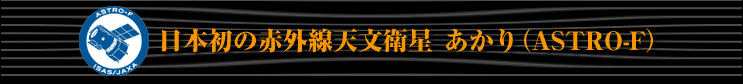|
 |
 |
|

スピッツァーの運用はいまのところうまくいっています。これまでに唯一大変だったのは、ものすごい太陽風によって、観測装置が影響を受けたことです。それ以外はとても順調です。衛星にはいくつかのバックアップシステムが搭載されていますが、幸い私たちはまだ使わずに済んでいます。打ち上げ前にはさまざまな困難や課題がありましたが、打ち上がって軌道に入ってからは、本当によく観測してくれています。正直言って予想以上で、最初に期待していたよりも多くの科学データを取得しています。
スピッツァーでは、約20名のチームが3年の歳月を掛けて特別なデータ処理ソフトを作りました。このソフトは、観測装置から生のデータを受け取り、さまざまなチェックや処理などをおこない、天文学者が日頃使用しているデータフォーマットに変換します。これを作るのは本当に大変でした。
打ち上げが成功したあと、 「あかり」 に携わる人たちが直面する課題は、 「あかり」 のデータをいかに迅速に科学的価値のあるデータに加工できるかだと思います。スピッツァーも当初は時間が掛かっていましたが、いまは順調におこなわれて、使いやすいものになっていると思います。今後も改良を重ねてより良いものにしていきます。
|
|
|
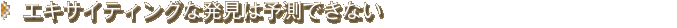
私がこれまでに関わってきた経験から学んだことは、エキサイティングな科学的発見は、事前の予測をはるかに超えているということです。まったく予期してないことが発見される例が多いのです。ただ「あかり」に限っていえば、今から素晴しい成果が予測できます。なぜなら今までにない優れた感知能力で全天を観測できますし、より広域の波長帯で新しいタイプの天体の発見やより遠くの銀河への理解が進み、宇宙の進化の過程などが解明されるのではないかと期待しています。さらに、これまでの観測では想像できなかったような新しいことが見つかるかも知れません。解析が進むにつれて、さまざまな天体の特徴や進化の様子、星の形成の過程などが解明されるでしょう。そして私が予想もしえないようなもっとすごい驚きがあるだろうと楽しみにしています。
|
|
|

一般的に科学的研究、特に天文学の研究は、ある一つの国家だけではなく、全人類に関係のあることとして象徴的なものです。全ての国が貢献しながら、各々の存在をアピールしていくことがとても大切です。こうした観点から日本が「あかり」を通じて世界に貢献する姿勢は、世界の天文学の発展に大きく寄与します。あらゆる面での成功を願っていますが、それは私だけでなく、このようなプロジェクトに携わる世界中の天文学者が、この「あかり」の重要さと、このプロジェクトに関わる人たちが費やしてきた努力を十分に理解し、評価しているからです。私も含め世界の人々が「あかり」
の成功を祈り、応援しています。
|
|
|
 |
 |
ジョージ・ヘルー(George Helou)
カリフォルニア工科大学教授、スピッツァー宇宙望遠鏡科学センター副所長。
レバノン生まれ。ベイルート・アメリカン大学で物理学を専攻。卒業後渡米。コーネル大学大学院にて博士号を取得(天体物理学)。卒業後、コーネル大学アルセティ天文台を経て、1983年よりカリフォルニア工科大学に勤務。その後、IRAS、ISOなど、数々の赤外線天文衛星プロジェクトに参加。現在、カリフォルア工科大学赤外線データ解析センター所長、NASAハーシェル科学センター所長なども兼任。天文学者として研究するほか、NASAの天文科学ミッションの立案などをリードする。子供の頃、レバノンで夜空を眺めて星に惹かれた思いを持ち続け、いまも夜空を眺めながら思いを巡らしている。 |
|
|
|