 |
||||
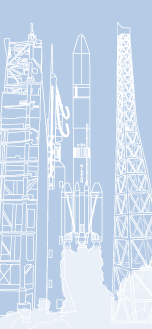 |
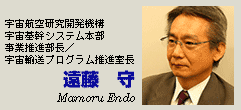
日本の純国産大型ロケットの開発は、H-IIにはじまり、H-IIAへと進化していきました。 |
|||
H-IIAの固体ロケットブースターは、燃焼圧力が従来の2倍という、これまでにない画期的なものでした。地上試験で予想以上にノズルの断熱材が削られる現象がみられたため、当初予定していた3回の地上試験に2回を加え計5回実施し、最終的には、穴があくまで削れることはないという判断を下し、H-IIA試験1号機を打ち上げたのです。それ以降、5号機まで失敗することはなかったので、技術は確立されたと考えていました。しかし、今回の事故の兆候を見抜けなかったことで、改めて宇宙開発の難しさを知ることになったのです。 |
||||
自動車や航空機、家電製品などは、利用の場である地上で徹底的に模擬実験をすることができますが、ロケットは宇宙に行くためのもので、地上試験だけでは本来不十分です。しかし、宇宙で試験をすることは現実的に不可能なので、ある程度の地上試験を経て、実際に打ち上げてみなければ総合試験とはなりません。 現在、日本の宇宙開発は、つま先立って世界のトップレベルに並んでいる状態で、これから踵を地につけて世界と肩を並べるには、さらに経験や技術力が必要です。今回の事故もこの背伸びをした状態に過信が重なり、問題の本質を見抜けなかったのだと思います。 |
||||
今後、日本の宇宙開発、ロケット開発の信頼性を高めるためには、技術の裾野を広げ、総合的な判断ができる人材を育成するとともに、さらに経験を積んで未然に危機を予測し発見する能力を養わなければなりません。 |
||||
 |
||||

