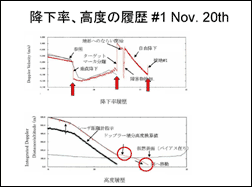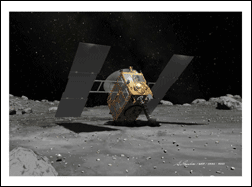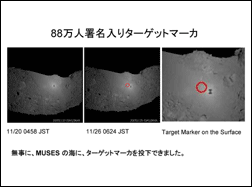後ほどのデータ解析で、「はやぶさ」が姿勢制御モードに移行した直後に障害物が検出され、探査機は降下の中断が適当と自らが判断して緊急離陸を試みたようです。しかし「はやぶさ」自身で離陸加速を遂行するためには姿勢に関する許容範囲が設定されており、この時点では姿勢がその範囲の外にあったので、安全な降下の継続が選択され、2回のバウンドの後に、およそ30分間の着陸状態を継続していたことが分かりました。着陸の姿勢は、サンプラーホーンと探査機の+X軸側下面端または太陽電池パネルの先端を表面に接した状態だったと推定されています。 第2回目の着陸は11月26日に行われました。第1回目と同じミューゼスの海に向かって降下し、その途中で20日に投下した署名入りターゲットマーカーを確認しました。(※図11)応募してくださった皆さんのお名前は、イトカワがある限り残るということになりますね。そして「はやぶさ」は、高度7m のところでホバリングを行った後、表面にならう姿勢に探査機の向きを変えます。その後、下向きに毎秒 4cmで加速して降りていきますが、どうやら斜面に段差があったようで、詳細は現在解析中です。 12月8日以降、「はやぶさ」は燃料の漏洩によって姿勢を喪失し、地上との交信が途絶えました。しかし、1年以内に復旧できる確率が 60%〜70%あったため、緊急運用に変更し、地球帰還を2010年6月まで3年延期しました。そして、2006年1月23日に、約50日ぶりにビーコン信号を受信し、1月26日からは姿勢制御運用を開始しています。残念ながら、搭載のリチウムイオン電池は故障し、化学推進機関の燃料も酸化剤も喪失したと思われます。そこで、惑星間飛行用のイオンエンジンを使って姿勢制御をしようという案が出されました。イオンエンジンの推進材であるキセノンガスを静電加速せずにガスのまま出せば、姿勢制御できることが分かり、今はキセノンガスを頼りに運用しています。 そして現在は、中利得アンテナによる256bpsで毎日正常に運用しています。地球指向誤差も1度程度まで追い込めていて、誤差 0.2〜 0.3度以下の精度になるとハイゲインアンテナによる通信も可能になります。また、3月6日には距離計測に成功し、「はやぶさ」の位置が決定できました。その時点での「はやぶさ」は、イトカワから 13,000kmほど離れたところを、毎秒3mの速さで遠ざかっていることが分かっています。2010年 6月の帰還を目指し、「はやぶさ」の挑戦はこれからも続きます。 「はやぶさ」は、イトカワ表面の状態がよく分かる精細な写真を数多く取得し、現在その解析が進められています。2006年6月初めには論文を発表し、その時期に専門家を集めた合同説明会を開催したいと思っています。 「はやぶさ」は我が国が独自に開発した探査方法であり、イオンエンンジンや自律航行など技術的要素の実証に成功しました。国際的にも、私たちが積極的に貢献できる太陽系探査として、後継機「はやぶさ2」をぜひ打ち上げ、このサンプルリターン技術を継承していきたいと思います。日本が世界をリードし、今後の太陽系探査ミッションを推進していくことを期待しています。
|