Q.若田宇宙飛行士が宇宙飛行士の募集に応募したときのことをお聞きしたいのですが、どういったきっかけで宇宙飛行士になろうと思われたんですか?

月面へ着陸をした「アポロ11号」の宇宙飛行士(提供:NASA)
今の宇宙飛行士の多くが同じような経験をしたと思いますが、私が5歳の時に、「アポロ11号」というアメリカの宇宙船が月に着陸するのをテレビで見て、宇宙に対する強いあこがれを持ちました。当時は、日本人の宇宙飛行士はいなかったので、幼心にも日本人が宇宙飛行士になれるとは思っていませんでした。小さい頃から飛行機に強い興味を持ち、航空機の技術者になることを目指して勉強し、大学院修士課程修了後には航空会社で飛行機の機体構造の技術者として仕事をしていました。
その時新聞で当時の宇宙開発事業団(現JAXA)が宇宙飛行士を募集するという記事を見て、日本人にとって新しい分野の職業である宇宙飛行士が実際どのように選ばれるのかという点に興味を感じたのと同時に、5歳の時にアポロ11号の月着陸を見たときの感動、宇宙飛行へ憧れの気持ちが蘇りました。宇宙飛行士という世界の多くの人々に貢献できる素晴らしい仕事に挑戦してみたいという気持ちが、宇宙飛行士選抜への応募へとつながりました。
Q.宇宙飛行士の選抜試験で特に印象に残っていることはありますでしょうか?
今でもお付き合いをさせてもらっていますが、選抜の時に知り合った素晴らしい仲間に巡り会えたことはとても幸運だったと思います。学科試験から始まって、身体の隅々までチェックされた医学検査や心理検査など、いろいろなことを経験することができましたが、強く印象残っているのは、二次試験の医学検査の直後に脱獄計画を立てるという課題を与えられたことでした。書面に示された前提条件の下で、いかにして脱獄するかの計画を自分で考え、7〜8人の受験者のグループの中でプレゼンテーションを行います。その後は、グループでディスカッションを行いながら1つの計画にまとめていくというものです。宇宙飛行士の選抜試験に参加した人たちの中に、おそらく脱獄をした人はいないと思いますから、突拍子もないテーマです。誰もが経験のない、自分の専門ではない分野での思考が要求されるので、参加者全員に対して公平なテーマだと思いました。個人のオリジナリティ溢れたアイデアを出す能力、プレゼンテーション能力、グループ討論を通して意見を述べ合うディベート能力、グループとして1つの計画にまとめていく協調性やリーダーシップ。そういったものが総合的に評価されるよう大変興味深い試験だったと思います。
しかし、何と言っても一番印象に残っているのは、最終的に候補者が6人に絞られて、ヒューストンのNASAジョンソン宇宙センターでの心理検査と医学検査を受けに行った時に、毛利さん、向井さん、土井さんの 3人の本物の日本人宇宙飛行士にお会いしてサインまでもらえたことです。
Q.実際に宇宙飛行士になってよかったと思うことは何でしょうか?

初フライト(STS-72)でロボットアームを操作する若田宇宙飛行士(提供:NASA)

宇宙飛行までの道のりは長く険しいものですが、1996年にスペースシャトルで初めて宇宙に行って、暗黒の宇宙に浮かぶ青く美しいオアシスのような地球の姿を見た時の感動は忘れられません。数々の訓練を重ね頑張ってきた甲斐があった、本当に宇宙飛行士になってよかったと強く感じた瞬間でした。宇宙飛行士として、世界中の多くの人々と協力しながら、有人宇宙活動を発展させていくという共通の目標に向かって仕事ができることは大きな喜びです。世界15ヵ国の協力で進められているISS計画では、様々な国の宇宙飛行士と一緒に宇宙飛行を行うだけではなく、各国の技術者の方々と一緒になって宇宙の新しいシステムの開発に参加したり、各国の訓練施設で訓練したり、また多くの科学者の方々と協力して宇宙での様々な実験や観測を行ったりと、国際チームの中での協調作業が多くなります。国や言語、宗教、文化、習慣を越え、人類としての共通のフロンティアを開拓していくという宇宙飛行士の仕事はとても大きなやりがいがある仕事です。
Q.宇宙飛行士はリスクも含めて精神的なストレスが高いと思いますが、いかがでしょうか? また、どのようにしてリフレッシュしているのでしょうか?

ロシアでソユーズ宇宙船の訓練を行う若田宇宙飛行士
宇宙飛行士の仕事にはリスクが伴います。一緒に仕事をしてきた尊い同僚の命が、2003年のコロンビア号の事故で失われた事は大きな衝撃でした。スペースシャトルだけでも14名の宇宙飛行士の命が失われています。しかし、人間が宇宙に行くことで地球人全体が享受できる新しい知見や地上での生活を豊かにする新技術が得られてきています。有人宇宙開発は人類が将来にわたり永続していくために、ゼロにはできないリスクを受け入れた上で取り組む価値のある重要な仕事だと思います。
普段の生活の中でリフレッシュするために、スポーツはとても有効です。ISS長期滞在ミッションの訓練では世界各国への出張が頻繁で、移動の翌日からシミュレーション訓練や船外活動訓練など長時間に渡る訓練が実施される事もあるので、時差ぼけを極力少なくすることは肝心です。そのためにも、お日様の当たる戸外でのスポーツはとてもよいと思います。私はジョギングやウェイト・リフティングを週4回程度行います。好きな野球は打ち上げの8ヶ月前から禁止されているので今はプレーできず残念です。ISS長期滞在飛行の訓練では世界各国への出張が頻繁ですが、出張先のいろいろな国でジョギングをしていると、これまで見たことのないような興味深い景色に巡り会えることもあり、楽しみの一つです。ジョギングをしていると、いろいろな物事を考える事ができ、新しいアイデアを思いつく事もよくあり、ジョギングは体と共に頭のリフレッシュにも最高です。
また、訓練で遠く離れていても、家族とのインターネット・ビデオチャットなどでの会話が精神的な大きな支えになっています。現在は家族で訓練拠点であるヒューストンに住んでおり、1年のうち半分近くは ISS長期滞在訓練のためロシアなどに出張しているという状況です。家族は日々の生活でのオアシスのような存在だと思いますし、家族との時間も大切にするように努めています。
Q.実際に宇宙飛行士になってみて、宇宙飛行士にとって何が大事だと思いますか?
一番大切なことは、「宇宙で仕事をしたい」という情熱だと思います。宇宙飛行士に選ばれた後、宇宙に行けるまでに何年かかるか分かりません。予期せぬ事故などで、計画が予定通りに進まないこともあります。とても長い訓練の時間を経て、やっと宇宙飛行ができるというケースも十分あるわけです。なぜこの仕事を選んだのか、宇宙で何をしたいのかを、自分自身でしっかり納得した上でこの仕事に就くこと、そして訓練が如何に長く厳しくても、「必ず宇宙に行くんだ」という情熱を持ち続ける事が大切だと思います。
宇宙飛行での仕事を安全且つ確実に遂行していくために不可欠なものは、いわゆる「運用のセンス」であり、そこには「正確な状況把握」、「的確な作業の遂行」、「優れたコミュニケーション」といった資質が含まれます。また、宇宙飛行士1人だけでできる仕事はとても少ないため、仲間の宇宙飛行士や地上の管制官を含む多くの関係者とのチームワークが非常に重要であり、リーダーシップとともに協調する事を大切にできる姿勢も宇宙飛行士には要求されます。


Q.若田宇宙飛行士の今後の目標を教えてください。
現在、今年の冬からのISS長期滞在飛行に向け訓練を行っています。2回のスペースシャトル飛行やISS参加各国での様々な訓練の成果を含め、これまでの16年間の宇宙飛行士業務を通して得た全ての経験を十分に発揮し、国際宇宙ステーション計画を成功させるために全力を尽くしたいと思います。また、日本の有人宇宙活動をさらに発展させるための、様々な技術開発の仕事もしていきたいと思います。そして将来は宇宙飛行士としての経験を生かして日本の種子島宇宙センターから、日本や世界各国の宇宙飛行士を宇宙に打ち上げることができるような宇宙船を開発することが私の夢であり、大きな目標です。
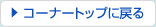

月面へ着陸をした「アポロ11号」の宇宙飛行士(提供:NASA)
その時新聞で当時の宇宙開発事業団(現JAXA)が宇宙飛行士を募集するという記事を見て、日本人にとって新しい分野の職業である宇宙飛行士が実際どのように選ばれるのかという点に興味を感じたのと同時に、5歳の時にアポロ11号の月着陸を見たときの感動、宇宙飛行へ憧れの気持ちが蘇りました。宇宙飛行士という世界の多くの人々に貢献できる素晴らしい仕事に挑戦してみたいという気持ちが、宇宙飛行士選抜への応募へとつながりました。
Q.宇宙飛行士の選抜試験で特に印象に残っていることはありますでしょうか?
今でもお付き合いをさせてもらっていますが、選抜の時に知り合った素晴らしい仲間に巡り会えたことはとても幸運だったと思います。学科試験から始まって、身体の隅々までチェックされた医学検査や心理検査など、いろいろなことを経験することができましたが、強く印象残っているのは、二次試験の医学検査の直後に脱獄計画を立てるという課題を与えられたことでした。書面に示された前提条件の下で、いかにして脱獄するかの計画を自分で考え、7〜8人の受験者のグループの中でプレゼンテーションを行います。その後は、グループでディスカッションを行いながら1つの計画にまとめていくというものです。宇宙飛行士の選抜試験に参加した人たちの中に、おそらく脱獄をした人はいないと思いますから、突拍子もないテーマです。誰もが経験のない、自分の専門ではない分野での思考が要求されるので、参加者全員に対して公平なテーマだと思いました。個人のオリジナリティ溢れたアイデアを出す能力、プレゼンテーション能力、グループ討論を通して意見を述べ合うディベート能力、グループとして1つの計画にまとめていく協調性やリーダーシップ。そういったものが総合的に評価されるよう大変興味深い試験だったと思います。
しかし、何と言っても一番印象に残っているのは、最終的に候補者が6人に絞られて、ヒューストンのNASAジョンソン宇宙センターでの心理検査と医学検査を受けに行った時に、毛利さん、向井さん、土井さんの 3人の本物の日本人宇宙飛行士にお会いしてサインまでもらえたことです。
Q.実際に宇宙飛行士になってよかったと思うことは何でしょうか?

初フライト(STS-72)でロボットアームを操作する若田宇宙飛行士(提供:NASA)
宇宙飛行までの道のりは長く険しいものですが、1996年にスペースシャトルで初めて宇宙に行って、暗黒の宇宙に浮かぶ青く美しいオアシスのような地球の姿を見た時の感動は忘れられません。数々の訓練を重ね頑張ってきた甲斐があった、本当に宇宙飛行士になってよかったと強く感じた瞬間でした。宇宙飛行士として、世界中の多くの人々と協力しながら、有人宇宙活動を発展させていくという共通の目標に向かって仕事ができることは大きな喜びです。世界15ヵ国の協力で進められているISS計画では、様々な国の宇宙飛行士と一緒に宇宙飛行を行うだけではなく、各国の技術者の方々と一緒になって宇宙の新しいシステムの開発に参加したり、各国の訓練施設で訓練したり、また多くの科学者の方々と協力して宇宙での様々な実験や観測を行ったりと、国際チームの中での協調作業が多くなります。国や言語、宗教、文化、習慣を越え、人類としての共通のフロンティアを開拓していくという宇宙飛行士の仕事はとても大きなやりがいがある仕事です。
Q.宇宙飛行士はリスクも含めて精神的なストレスが高いと思いますが、いかがでしょうか? また、どのようにしてリフレッシュしているのでしょうか?

ロシアでソユーズ宇宙船の訓練を行う若田宇宙飛行士
普段の生活の中でリフレッシュするために、スポーツはとても有効です。ISS長期滞在ミッションの訓練では世界各国への出張が頻繁で、移動の翌日からシミュレーション訓練や船外活動訓練など長時間に渡る訓練が実施される事もあるので、時差ぼけを極力少なくすることは肝心です。そのためにも、お日様の当たる戸外でのスポーツはとてもよいと思います。私はジョギングやウェイト・リフティングを週4回程度行います。好きな野球は打ち上げの8ヶ月前から禁止されているので今はプレーできず残念です。ISS長期滞在飛行の訓練では世界各国への出張が頻繁ですが、出張先のいろいろな国でジョギングをしていると、これまで見たことのないような興味深い景色に巡り会えることもあり、楽しみの一つです。ジョギングをしていると、いろいろな物事を考える事ができ、新しいアイデアを思いつく事もよくあり、ジョギングは体と共に頭のリフレッシュにも最高です。
また、訓練で遠く離れていても、家族とのインターネット・ビデオチャットなどでの会話が精神的な大きな支えになっています。現在は家族で訓練拠点であるヒューストンに住んでおり、1年のうち半分近くは ISS長期滞在訓練のためロシアなどに出張しているという状況です。家族は日々の生活でのオアシスのような存在だと思いますし、家族との時間も大切にするように努めています。
Q.実際に宇宙飛行士になってみて、宇宙飛行士にとって何が大事だと思いますか?
一番大切なことは、「宇宙で仕事をしたい」という情熱だと思います。宇宙飛行士に選ばれた後、宇宙に行けるまでに何年かかるか分かりません。予期せぬ事故などで、計画が予定通りに進まないこともあります。とても長い訓練の時間を経て、やっと宇宙飛行ができるというケースも十分あるわけです。なぜこの仕事を選んだのか、宇宙で何をしたいのかを、自分自身でしっかり納得した上でこの仕事に就くこと、そして訓練が如何に長く厳しくても、「必ず宇宙に行くんだ」という情熱を持ち続ける事が大切だと思います。
宇宙飛行での仕事を安全且つ確実に遂行していくために不可欠なものは、いわゆる「運用のセンス」であり、そこには「正確な状況把握」、「的確な作業の遂行」、「優れたコミュニケーション」といった資質が含まれます。また、宇宙飛行士1人だけでできる仕事はとても少ないため、仲間の宇宙飛行士や地上の管制官を含む多くの関係者とのチームワークが非常に重要であり、リーダーシップとともに協調する事を大切にできる姿勢も宇宙飛行士には要求されます。

Q.若田宇宙飛行士の今後の目標を教えてください。
現在、今年の冬からのISS長期滞在飛行に向け訓練を行っています。2回のスペースシャトル飛行やISS参加各国での様々な訓練の成果を含め、これまでの16年間の宇宙飛行士業務を通して得た全ての経験を十分に発揮し、国際宇宙ステーション計画を成功させるために全力を尽くしたいと思います。また、日本の有人宇宙活動をさらに発展させるための、様々な技術開発の仕事もしていきたいと思います。そして将来は宇宙飛行士としての経験を生かして日本の種子島宇宙センターから、日本や世界各国の宇宙飛行士を宇宙に打ち上げることができるような宇宙船を開発することが私の夢であり、大きな目標です。
若田 光一(わかた こういち)
JAXA有人宇宙環境利用ミッション本部有人宇宙技術部 宇宙飛行士
九州大学大学院工学部航空宇宙工学専攻博士課程修了。博士(工学)。1989年、日本航空株式会社に入社し、機体構造技術の開発などに従事。1992年4月、国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟の組み立て・運用に備え、NASDA(現JAXA)が募集したミッションスペシャリスト(MS)候補に選ばれる。同年7月、米国航空宇宙局(NASA)が実施するMS・パイロット候補者訓練用の第14期宇宙飛行士候補者養成コース参加のため渡米。1年間の訓練を経て、1993年、NASAよりMSとして認定される。1996年、STS-72に日本人初のMSとしてスペースシャトル搭乗。2000年、ISS組み立てミッションであるSTS-92にMSとして搭乗し、日本人として初めてISS建設に参加。2007年、ISS第18次長期滞在クルーのフライトエンジニアに任命され、現在、世界各国で訓練中。
JAXA有人宇宙環境利用ミッション本部有人宇宙技術部 宇宙飛行士
九州大学大学院工学部航空宇宙工学専攻博士課程修了。博士(工学)。1989年、日本航空株式会社に入社し、機体構造技術の開発などに従事。1992年4月、国際宇宙ステーション(ISS)の「きぼう」日本実験棟の組み立て・運用に備え、NASDA(現JAXA)が募集したミッションスペシャリスト(MS)候補に選ばれる。同年7月、米国航空宇宙局(NASA)が実施するMS・パイロット候補者訓練用の第14期宇宙飛行士候補者養成コース参加のため渡米。1年間の訓練を経て、1993年、NASAよりMSとして認定される。1996年、STS-72に日本人初のMSとしてスペースシャトル搭乗。2000年、ISS組み立てミッションであるSTS-92にMSとして搭乗し、日本人として初めてISS建設に参加。2007年、ISS第18次長期滞在クルーのフライトエンジニアに任命され、現在、世界各国で訓練中。