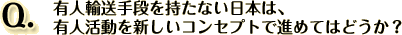
 向井:宇宙ステーションが地球を回っていることの最大の利点は、既存の重力レベルをゼロにできることだと思います。それにセントリフュージ(生命科学実験施設)を組み合わせることによって、どういう重力でも作れます。1Gと0Gの間で、重力が可変となるのです。ところが地球上にいる限り1Gがベースですから、1.2G、1.5G、2GなどハイパーGはできても、長期間に低いGはできない訳です。私たちがいる地球というのは宇宙の中で特殊な環境で、こういう特殊な環境にいるから、こういう人間が、生命体が存在します。しかし、地球では1Gしかわからないため、実際には0.5Gの方が良いかもしれませんが、それはわかりません。たとえば宇宙で細胞培養をやってみると、重力が1Gより低い方が増殖率が高くなったりすることがあります。地球にいただけでは、適正重力というのがわからないのです。ですから私は、宇宙へ飛び出すことの1つの理由は、飛び出して先のことを見るのも重要だけど、そこから振り返って、私たちが住んでいる1Gの世界では、どうしてこういう人間の形になったのかとか、あるいは、どうしていろいろなものができたのか、といったことを考えるよい機会になると思います。 向井:宇宙ステーションが地球を回っていることの最大の利点は、既存の重力レベルをゼロにできることだと思います。それにセントリフュージ(生命科学実験施設)を組み合わせることによって、どういう重力でも作れます。1Gと0Gの間で、重力が可変となるのです。ところが地球上にいる限り1Gがベースですから、1.2G、1.5G、2GなどハイパーGはできても、長期間に低いGはできない訳です。私たちがいる地球というのは宇宙の中で特殊な環境で、こういう特殊な環境にいるから、こういう人間が、生命体が存在します。しかし、地球では1Gしかわからないため、実際には0.5Gの方が良いかもしれませんが、それはわかりません。たとえば宇宙で細胞培養をやってみると、重力が1Gより低い方が増殖率が高くなったりすることがあります。地球にいただけでは、適正重力というのがわからないのです。ですから私は、宇宙へ飛び出すことの1つの理由は、飛び出して先のことを見るのも重要だけど、そこから振り返って、私たちが住んでいる1Gの世界では、どうしてこういう人間の形になったのかとか、あるいは、どうしていろいろなものができたのか、といったことを考えるよい機会になると思います。
私はよく「宇宙に行って何がいちばん面白かったですか?」と聞かれますが、いちばん面白かったのは、重力のない世界にいた後で地球に戻ってきた時、地球上では重力が私たちをすごく支配しているということがわかったことです。しかし、私たちは重力のもとで生まれて、ここで一生を過ごしてしまうので、そのことに気づかないんですね。ものすごい力で私たちの身体なり、いろいろなものが下に、中心に引きつけられているか、というのを感じました
私たちを含め生命体は、重力のもとでいろいろな現象を起こしています。実際にどういう現象が起きているか、それを見極めるには、重力のない場所が必要です。たとえば私たちの目がどれくらいよく見えるかを調べるためには暗室が必要です。光が全くないところに入って、光がどれくらい見えるかを調べます。また、耳の機能を調べたい場合は、音が全くない部屋が必要です。静かな部屋に入ってどれくらい聞こえるか、そのようにして医学は検査しているのです。私たちが住む地球のことを知りたかったら、そこから離れて地球を顧みることも必要であり、私は、その場所が宇宙ステーションだと信じています。
秋葉:宇宙へ出て行くことは、まだたいへんな時代です。最近になってやっと商業化が考えられ、宇宙旅行など、人間が宇宙へ出て行く時の法体系を作ろうという段階にきた訳です。
日本は、もちろん立派なロケットを持っています。しかしそれは20世紀の価値において立派なロケットだと思わなければなりません。21世紀に通用する輸送手段は全くちがうものだという観点が必要と思います。皆さんの中には、ロケットの打ち上げをご覧になった方がいらっしゃると思いますが、たいへん素晴らしい音を聞かせていただいて感動したとよく言われます。しかし、毎日あのような音で飛ばしたら、うるさいと言われるでしょう。そこで、私が考えたのは、飛行機に載せて飛行機から発射する打ち上げシステムです。今のロケット打ち上げシステムは、年間せいぜい20〜30回しか打ち上げられず、1回10トンとして、年間200〜300トンしか宇宙に飛ばせません。ところが、飛行機だと年間数百回の打ち上げが可能です。ですから有人活動ももちろん必要ですが、次世代の宇宙輸送機を開発する必要があると思います。また、宇宙空間という危険な場所でしっかり作業をして重要な役割を果たすのは、ロボティクスです。この2点の開発を進めてほしいと私は思います。
小野:秋葉先生のお話を聞いて感じた方がいらっしゃるかもしれませんが、私が宇宙科学研究所にいた頃から、ロケットのコンセプトは全く進歩していないのです。ドイツのV2 ロケットが飛んで以来、システムの根本的な技術革新が行われていないように思います。
立川:そうですね。小野議員がおっしゃるように、新参者から見ると、この50年間、宇宙輸送の概念的な進歩はあまりないかもしれません。ですから秋葉先生がおっしゃるように、新しい発想で宇宙をどう使うか、宇宙にどうアクセスするかというのは、多いに考えた方がよいと思いますし、それは若い方の大きな夢になるのではないでしょうか。
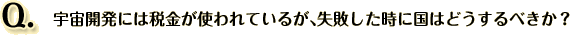
小野:新しいことに挑戦すれば、失敗するのは当たり前。しかしその失敗を教訓として活かして次の挑戦ができないようであれば、残念ながらその組織は新しいものを担う資格はないということです。ロケットの打ち上げに失敗した時、もちろん私たちは厳しいことを申し上げます。しかしそれは、その厳しさを乗り越えて、次の新しいものを拓いてほしいと思うからです。もう開発を中止しろと言っているのではありません。私たちは挑戦する人を求めています。しかし、挑戦した結果、失敗から学ばない人は必要ありません。そのためにかかる費用は、高額は出せないにしても皆さんが望むものに少しでも応えていきたいと思っています。
的川:現在の世界のロケットを考えますと、打ち上げの成功率は90パーセントくらいです。だから10機に1機はどのロケットも失敗しています。ただ、威張って失敗しているのではなく、全力を尽くして失敗している訳で、やはり「挑戦」というのは宇宙開発の大事な言葉だと思います。しかし、10機に1機失敗するという技術レベルでは、これから宇宙へ進出するのにまだまだ未熟です。たとえば「成田空港から月へ100機飛びますが、10機は落ちるでしょう」と言ったら、だれも乗りませんよね。そういう意味では、宇宙技術の成熟度は飛行機に比べるとまだまだ足りないと思います。その成熟度を高めるには、先ほど秋葉先生がおっしゃったように、これからはもう国に頼っているだけでなく、国民一人一人が宇宙開発を展開する。自分が宇宙開発をやっている人類の一部だという観点からのアプローチが必要と思います。
最後に、これからの日本の宇宙開発について皆さんからひと言ずつお願いします。
|

