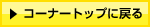Q. 準天頂衛星初号機「みちびき」の現在の状況を教えてください。

LEX信号を用いた歩行ナビゲーションのデモ風景
2010年9月に打ち上げられた「みちびき」は順調に運用を続け、準天頂衛星システムの技術実証を行ってきました。「みちびき」を使ってアメリカのGPS衛星を補完・補強し、従来よりも高精度の測位技術を実証するという開発当初の目標は、ほぼ達成しています。「みちびき」のプロジェクトには複数の省庁と研究機関が関わっていて、JAXAの担当は、GPSの補完技術と、次世代衛星測位の基盤技術の研究開発です。
次世代の測位技術を確立するために使うのはLEX(L-band experiment)信号で、これは「みちびき」独自の実験用信号です。 JAXAでは、このLEX信号を使って、PPP(Precise Point Positioning:単独搬送波位相測位)という測位技術の開発を行っています。ひとことで言うと、現在、一般的には地上の基準点を用いて相対的に実現しているセンチメートル級の精密測位を、「みちびき」のLEX信号で送られる精密な衛星の軌道とクロック情報を使うことによって実現する方法です。このPPP技術だと基準局を必要としないため、基準局がない海上のような場所でも数センチメートル単位の測位ができるかもしれないと期待されています。

Q. GPSの補完に関する実験では、どのような成果がありましたか?


「みちびき」の受信機(上)を搭載した実験車(下)
オープンスカイから森林内、都心のビルに囲まれた場所など、さまざまな環境での準天頂衛星の効果を検証するため、JAXAでは、「みちびき」の受信機をいろいろな大学や民間企業に貸し出して、データを取得する実験を行いました。具体的には、タクシー会社やトラック運送業者、宅配業者の方々に協力をしていただいてデータを集めました。このデータを検証した結果、これまでGPSだけでは測位できなかったビルの谷間でも、「みちびき」を組み合わせることによって、測位が可能になったことを確認しています。ビルが林立する東京の新宿では、測位可能な時間と場所が GPSだけの時と比べて2.5倍も改善された例もありました。天頂付近にある「みちびき」を利用することによって、都市部などの環境が悪い場所においては、測位可能な時間、場所及び、測位結果のバラツキに対して顕著な改善効果があることが確認できました。
Q. 今後の課題は何でしょうか?
カーナビを例にとってみると、ビルが立ち並び測位がしにくい都市部などでは、現在は道路のどの車線、どちらの歩道に居るかまでは分かりませんので、測位精度の面でもっと改善が必要です。将来的には、道路の左右どちら側に居るか、どの車線に居るかまで識別できるようにしたいと考えており、複数周波数、搬送波位相測位を用いた精密測位、新しい信号利用を進め、LEX信号による搬送波位相測位手法を開発したいと思います。
ただ、現在のカーナビがGPSだけでなく、加速度センサなど他のセンサを使って精度を高めているのと同じように、「みちびき」だけというよりは、いろいろな他のシステムと組み合わせていくことになるのではないかと思います。実際に最近のスマートフォンは、GPSだけでなくロシアのグロナス衛星の受信機も内蔵することで、より測位利用率を高め、環境が悪い場所でも精度の高い測位情報を提供しています。
衛星測位の高度な利用が進めば進むほど、そのサービスがいつでもどこでも、安心して利用できることが求められるようになると思います。精度だけでなく、信頼性向上、妨害波などへの耐性を高めること、屋内から屋外測位への接続の容易さの改善などについても高度化が必要だと考えています。

Q. 衛星測位システムに対する世界の動きはいかがですか?
近年は、アメリカのGPS衛星の他、ヨーロッパの「ガリレオ」、ロシアの「グロナス」、中国の「コンパス」など、世界各国で測位衛星が打ち上げられています。測位衛星はもともと軍事システムとして開発されたものですが、民生用信号が解放されることにより、さまざまな利用が広がってきました。今後、民生用として使える周波数、信号の数が増えてくるので高精度で信頼性の高い衛星測位サービスの提供が可能になります。そのサービスは非常に広範囲で使えるため裾野が広く、市場は世界規模です。どの国も世界市場への参入を真剣に考えています。そういう意味で、民生用の信号については、各衛星のシステムの違いを減らして、世界のユーザーが使いやすい環境を作ろうという動きがあります。私たちはこのことを“相互運用性を高める”と言っています。
国連に、地球的衛星測位システム(GNSS: Global Navigation Satellite System)に関する国際委員会「ICG(International Committee on GNSS)」という委員会がありますが、そこでは、各国の衛星測位システムの相互運用性をどんどん高めようという活動を行っています。複数のシステムを使える環境を作って、新しい測位衛星の使い方をみんなで実証し、GNSSのメリットを最大限に活用することがICGの目的です。例えば、同じ周波数帯を使って測位信号を送ろうとか、1つの受信機で複数の衛星信号を処理できるようにしようという議論を行っています。また、将来的には測位信号を全世界共通化して、大きな1つの測位システムを構築しようという議論も行われています。測位システムの統合については、大変興味深い議論だと思います。
Q. 「みちびき」を使った国際協力についてはいかがでしょうか?

2011年11月に韓国で行われたGNSSワークショップの様子
「みちびき」の信号が届く範囲はアジア・オセアニア地域ですが、このエリアはヨーロッパやロシア、中国、インドの衛星測位システムもカバーしています。これは、他の地域よりもいち早く複数システムが利用できる環境が整うことを意味します。
そこで、アジア・オセアニア地域で世界に先駆けて相互運用性に関する実証実験を行い、その検証結果をICGにおける議論にフィードバックできればよいのではないかと、日本から、「複数GNSS実証実験キャンペーン」をICGに提案しました。2010年には、ICGの後援を受けて、マルチGNSSアジア(MGA)という組織を立ち上げ、相互運用性の実現に向けた取り組みを行っています。その第一歩として、「みちびき」の受信機を使った実験が、タイやマレーシア、中国、オーストラリアなどアジア・オセアニアの国でちょうど始まろうとしているところです。複数GNSSの時代では、「みちびき」の補強機能が重要な役割を果たすようになると考えており、前述したLEX信号を用いたPPPも、GPSだけでなく「ガリレオ」や「グロナス」なども利用した実験を行うことを計画しています。
また、アジア・オセアニア地域の複数衛星測位システム利用の普及と情報交換を目的として、ワークショップを開催しています。これまでに、タイ等で行い、2012年12月にはマレーシアで4回目のGNSSワークショップを開催する予定です。このワークショップを通じて、新興国等における人材育成支援などにも貢献できればと考えています。

Q. 準天頂衛星はどのような分野での利用が期待されているのでしょうか?

防災や農業などさまざまな分野での利用が考えられていますが、例えば、鉄道と気象関係があります。鉄道分野では、列車の運行管理に測位衛星を使えるかどうかを鉄道総合技術研究所と共同研究を行っています。現在、列車の運行は、閉塞と呼ばれる方式で追突・衝突事故を防止、運行管理を行っています。列車が、線路上に一定区間ごとに区切られた線路を列車の鉄輪がまたぐと電流が流れることを利用して、列車がどの区間にいるかを運行管理センターが検知するという仕組みです。この線路上の装置がきちんと作動しているかどうか、毎日、運行時間が終わった夜中に人が線路を歩いて点検を行っていますが、特に人口の少ない地方のローカル線は、鉄道会社の大きな負担になっています。そこで、測位信号の受信機を取り付けて、列車位置を管理することが考えられています。山間部などGPSだけでは位置情報を取得できないところも、「みちびき」と組み合わせることで、測位が可能になります。保守費用を削減するだけでなく、円滑な運行管理や運転士の方のサポートを行うという面でも役に立つと思います。
また、京都大学生存圏研究所の津田敏隆先生は、「みちびき」の受信機を使って大気中に含まれる水蒸気の量を調べることで、局所的、かつ短時間に発生するゲリラ豪雨を予測する研究を行っておられます。これまで使っていた GPSの場合は、仰角10度以上にある広い範囲にある衛星を使って水蒸気の量を推定していましたが、「みちびき」は高仰角に長時間滞在するため、真上からピンポイントで、より細かい分解能で水蒸気量の分布を調べることができます。ゲリラ豪雨は狭いエリアで起こる気象現象なので、「みちびき」の観測データが、気象予報、タイムリーな警報による防災に役立つのではないかと研究が行われています。
本格的な実用が始まるまでに、準天頂衛星システムの応用範囲をさらに広め、利用促進につなげていければと思います。
小暮聡(こぐれさとし)
宇宙利用ミッション本部 衛星利用推進センター 準天頂衛星システムミッションマネージャ
1993年、名古屋大学大学院航空工学修士課程修了。同年、宇宙開発事業団(現JAXA)に入社。中央追跡管制所に配属され衛星の運用官制を担当。2001年、米国コロラド大学留学から帰国後、ミッション推進センターにて準天頂衛星システムの立ち上げに従事。準天頂衛星システムプロジェクトチームで測位システムの開発、アメリカのGPSやヨーロッパの「ガリレオ」など他衛星測位システムとの対外調整、ユーザインタフェースを担当。プロジェクトチーム解散後は、衛星利用推進センターにて準天頂衛星初号機「みちびき」の技術実証実験と利用推進を担当。2012年4月より現職。