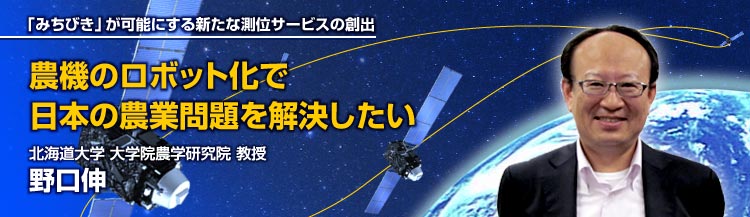Q. 先生は、「みちびき」が測位可能なアジア・オセアニア地域の農業関係者とも交流があると伺っています。彼らは「みちびき」に関心を持っていますか?
アジア・オセアニア地域は主産業が農業であり、「みちびき」を使った農業技術に非常に関心を持っています。韓国やマレーシアは、「みちびき」の受信機を使って、今年実証実験を行っています。特に、GPSの補強機能がとても期待されていますね。通常、GPSを補強するためには、補正信号を発信する基準局を地上に設置する必要がありますが、宇宙にある「みちびき」から補正信号が送られてくれば、地上にそのようなインフラを整備する必要はありません。そこが利点です。将来的には、日本発の測位衛星を利用した農業技術を海外に輸出したり、それを使って外交支援することができるかもしれません。
Q. 測位衛星による農機の自動化の研究を始められたきっかけは何でしょうか?

イリノイ大学に留学中の野口教授(提供:野口伸)
1997年にアメリカのイリノイ大学に留学した時に、すでにアメリカでは測位衛星を利用した農作業の自動化の研究が進んでいました。アメリカの農場は日本と比べ物にならないほど大規模なので、農機の位置を正確に知るために、測位衛星が注目されていたのです。それで私も関心を持つようになりました。
1998年にはアメリカで初めて、トラクターを無人で自動走行させるデモンストレーションを行い、参加者から拍手をいただいた時に手応えを感じました。でも、アメリカで使われている農機は、かなり大きくて速度も速いので、実際に無人で自動運転させるのは、安全面で難しいと感じています。一方、日本で使われている大きさの農機ならば、無人走行の可能性は十分あると思いました。
Q. 先生が描く、測位衛星を使った農業の将来像を教えてください。

私の目標は、遠隔監視技術を使ったロボット農業を実現することです。現在農林水産省「農作業の軽労化に向けた農業自動化・アシストシステムの開発」というプロジェクトの中で実施しているものですが、複数の畑でロボット化された農機が自動運転していて、それを離れた事務所のモニターで監視しているというイメージです。その農機は無人運転で、肥料などがなくなった場合は、そこに人が行って補給します。地域ごとにモニター室を設けて、少なくとも、2人の人間で4台以上の農機を管理できるようなシステムを作りたいと思っています。
その第一ステップとして考えているのが、1人の人間が2台の農機を管理するシステムです。無人で農機を自動運転させるには、安全性の面でまだ改善しなければならないところがあるため、その後ろを人間が乗った農機が追随し、安全を確認します。ただ、単に前の無人機を監視するのではなく、きちんと別の農作業を行います。同時に2つの作業を行えるので、2倍の能率になるわけですね。このように、まずは、ロボットと人間が協調して能率を上げるという形で始め、実用化に向けて進めていきたいと思っています。
実は、この2台体制のアイディアを出してくれたのは、若い農家でした。農機を自動運転させることで一番問題になるのは安全性で、万が一、人をひいてしまったら大変なことになります。障害物を感知するセンサを使っても、100%安全ということはあり得ないのです。また、そのような危険性があるものにメーカーは手を出したがりません。そういう問題で行き詰まっていた時に、農家の方が意見してくれたのです。私たちは農業の現場で絶対に必要だと思う技術を開発しているものの、実際に田畑で働いているわけではないので、現場のことに疎くなりがちなんですね。ですから、農家の方たちからのフィードバックは非常に重要で、彼らから教えていただくことはたくさんあります。だからこそ、農家の方たちに満足していただけるようなシステムにしていきたいですね。
現在日本では農村の過疎化が問題になっていますが、農村に魅力を感じてもらえるようになれば、人が集まってくるかもしれません。私の取り組みが、農業に魅力を感じてもらえる一つのきっかけになってくれればと思います。
北海道大学 大学院農学研究院 教授。農学博士
1990年、北海道大学大学院農学研究科博士課程修了。1997年助教授を経て、2004年より現職。1998〜2001年、米国イリノイ大学農業工学科教授。現在、中国農業大学、華南農業大学、西北農林科技大学の客員教授。専門は農作業の自動化、農業のリモートセンシング、IT農業。
農機のロボット化で日本の農業問題を解決したい
視覚障害者の歩行環境を改善するために
日本発の屋内外シームレス測位の実現へ
衛星測位利用の高度化実用化に向けて測位精度のさらなる向上を目指す