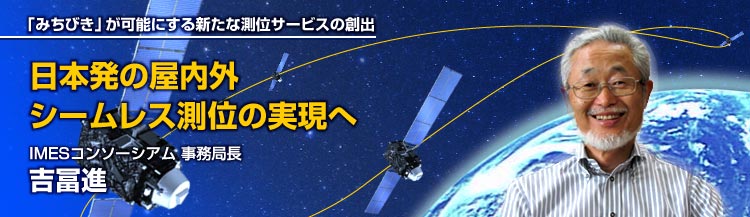Q. IMESの実用化に向けた課題は何でしょうか?

LEDランプ内蔵型のIMES送信機(提供:株式会社リコー)
一番の課題は、IMESの信号が読める携帯電話がまだ市販されていないことです。これは「みちびき」についても同じことが言えますね。最近、アメリカの通信機器メーカーが「みちびき」の信号が読める受信機を販売しましたが、携帯電話はまだ「みちびき」に対応していません。もともとGPSの受信機はLSI化されていて、チップで携帯の中に入っています。そのチップのソフトウエアを少し書き換えるだけで、準天頂衛星の信号もIMESの信号も読めるようになるのですが、それが実現していません。どの携帯電話通信会社も、IMESには関心を持っていますが、ビジネスとしてどこまで成り立つのか見通しがつかないと言うのです。チップを作っている会社も同じように、IMESがどこまで使えるシステムかを見極めているところです。いくら素晴らしいシステムだと説明をしても、実際に IMESが使われているところを見せないと信じてもらえないと思いますので、これからもっと事例を増やしていくことが大事だと思っています。
それと、屋内につける送信機の設置費用を誰が出すのかという問題もあります。送信機は名刺ほどの大きさのカード式で、1台、数万円します。それを5m〜10mおきに取り付けて配線をしますので、設置コストがかかってしまうのです。しかし最近、株式会社リコーが、蛍光灯型LEDランプにIMESの送信機を組み込んだ試作品を作りました。このような送信機であれば、配線コストが不要になります。でもIMESコンソーシアムとしては、送信機の設置は国や自治体にお願いしたいと思っています。なぜなら、IMESの技術は、災害対策に役立ち、安全・安心のためのツールとして利用できるからです。平常時は民間が送信機を使ってビジネスをして、利益が出れば、税金の形で国や自治体に納められるのですから、悪い話ではないと思います。
財団法人日本宇宙フォーラム常務理事。横浜国立大学大学院講師(非常勤)
1972年、宇宙開発事業団(現JAXA)入社。技術試験衛星I型「きく1号(ETS-I)」の開発、電離層観測衛星「うめ(ISS)」、技術試験衛星II型「きく2号(ETS-II)」の運用等に従事。また、我が国初のリモートセンシング衛星となった海洋観測衛星「もも1号(MOS-1)」の概念設計から打ち上げまでを一貫して担当。1991年〜1994年、NASDAパリ駐在員事務所長。1994年に帰国後、国際宇宙ステーション計画(ISS)に従事。主に「きぼう」日本実験棟に搭載する各種実験装置の開発や、研究者支援を担当。2003年、宇宙環境利用センター長。2005年、通信測位衛星利用センター長。その後、衛星測位システム室長として、準天頂衛星プロジェクトの立ち上げに従事。2007年、JAXA退職、財団法人日本宇宙フォーラムに移籍。2011年、IMESコンソーシアム事務局長に就任。2012年4月より現職。
農機のロボット化で日本の農業問題を解決したい
視覚障害者の歩行環境を改善するために
日本発の屋内外シームレス測位の実現へ
衛星測位利用の高度化実用化に向けて測位精度のさらなる向上を目指す