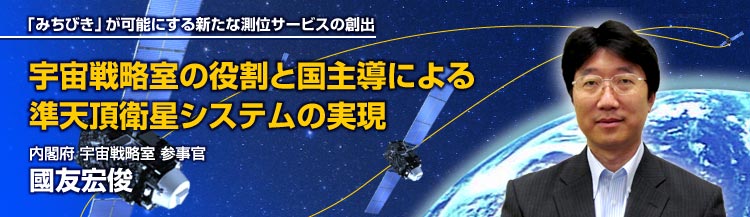Q. 現在、日本政府が特に力を入れている宇宙政策は何でしょうか?
現在、我が国が最も力を入れているのは、衛星測位を目的とする「実用準天頂衛星システム」で、宇宙戦略室がこのプロジェクトを担当しています。衛星測位は、国土交通省、経済産業省、農林水産省、消防庁、警察庁など様々な官庁が関係しています。また、民間企業においても、測位衛星を利用したいろいろなサービス産業が創出されています。例えば、GPSの測位機能を活用した子供や高齢者の「見守り」サービス、食品等の物流監視システム、高精度の時刻情報を利用した金融取引システムなど、GPSを使ったサービスは、私たちの生活の隅々にまで行き渡っています。
準天頂衛星システムは、産業の国際競争力強化、産業・生活・行政の高度化・効率化、さらには日米協力など国際プレゼンスの向上にも資するものです。国民の生活から産業に至るまで幅広い効果を生むことから、平成23年9月に実用準天頂衛星システムについての閣議決定を行い、我が国の宇宙政策で最優先事項と位置付けています。
Q. 準天頂衛星は今後どのような計画で打ち上げられるのでしょうか?

準天頂衛星初号機「みちびき」
平成22年9月に準天頂衛星初号機「みちびき」を打ち上げ、これまでに200を超える企業・大学・団体が参加して、多くの成果を出してきました。測位衛星を利用した新しいサービスを開発するための利用実証実験は今も続けられています。ただし、1機の準天頂衛星が日本の上空にあるのは1日8時間程度です。実用化には24時間365日のサービス提供が求められ、そのためには最低4機の準天頂衛星が必要です。
平成23年9月の閣議決定において、2010年代後半を目途にまずは4機体制を整備することが決定され、平成24年度の予算で所要の予算を確保しています。できるだけ早く、インフラとして準天頂衛星システムを整備し、国内のみならず海外でも活用できるようにしたいと考えています。
Q. 準天頂衛星を活用することにより、私たちの生活はどう変わると思われますか?
準天頂衛星システムの高精度な位置情報や時刻情報を生かしたサービスが新たに提供されることにより、産業、生活、行政が高度化、効率化し、国民生活の利便性の向上に寄与すると考えています。また、いろいろな分野の産業が宇宙を活用してビジネスを展開することにより、新しい産業や雇用の創出にもつながるでしょう。衛星を開発したり、衛星をロケットにより打ち上げたりする企業だけでなく、GPSを使ったアプリケーションの開発や、サービスの提供など、宇宙を利用する産業はすべて宇宙産業であると我々はとらえています。実際に、宇宙を利用したサービスを考える企業は年々増えてきており、さらに宇宙産業の裾野が広がることを期待しています。
Q. 防災分野での宇宙利用についてはどう思われますか?

東日本大震災後にGPSの測位信号を使って道路状況を調査する車両。今後「みちびき」の受信機が搭載される予定。(提供:アイサンテクノロジー株式会社)
準天頂衛星に限らず、防災や災害対応の分野での「宇宙の利用」は、その効果がきわめて高いことが、東日本大震災発生時においても明らかになりました。例えば、カーナビを搭載した車で被災地へ向かう際に、どこの道路が使えるかという情報をインターネットで公開するサービスがありましたが、これは、被災地支援において大きな役割と果たしたと思います。
また、人工衛星が撮影した画像は、災害状況を把握し、人命救助や二次災害の防止に役立つだけでなく、行政の効率化にも貢献しました。自治体から被災者の方に補償金やお見舞金をお支払いする際には、行政は被害状況を確認させていただきますが、これまでは1軒1軒担当者が現地に行って確認していたものが、衛星測位やリモートセンシング画像の活用により、事務所のコンピュータで確認できるようになりました。また、東日本大震災では衛星通信電話も大活躍しましたが、これらの経験により、宇宙を利用することの意義や価値を改めて認識することができたと思います。
Q. 準天頂衛星は、その軌道上、アジア・オセアニア地域も利用可能です。準天頂衛星の外交利用や、測位サービスの海外展開は考えられますか?

アジア・オセアニア地域も利用可能な準天頂衛星の軌道
現在、政府としては、海外の市場獲得を目指し、パッケージ型インフラ海外展開を推進しておりますが、宇宙システムの輸出振興についても支援対象の1つです。パッケージ型とは、衛星やロケットのみならず、相手国の人材育成や産業創出などにも官民連携の下で協力していくとともに、宇宙を利用した設備や技術なども一緒に輸出するもので、宇宙利用によるソリューションもあわせて提供していこうというものです。
現在、日本のロケット打ち上げサービスや人工衛星は、技術的に優れていても、円高の影響もあり、コスト競争力が弱く、海外市場では厳しい状況に立たされています。そのため、単に商品を売り込むのでなく、例えば衛星を売りたい場合は、地上設備の建設や人材育成、日本の衛星データの利用、衛星を利用した新産業への協力など、その国の利益となる付加価値をつけてアプローチすることが重要と考えています。
また、JAXAのような宇宙機関を作りたいという要望があれば、それに対する政府間協力もパッケージにして海外展開することも考えられるでしょう。特にアジアの新興国は経済的にも成長していて、宇宙利用に関心を持っていますので、政府としてそれらの国に働きかけ、我が国の宇宙産業の国際競争力強化にも結びつけていきたいと思います。
Q. 準天頂衛星のノウハウは、測位関連ビジネスの世界市場にも有効でしょうか?
日本の準天頂衛星は、アメリカのGPS衛星を補完、補強するシステムであるということが重要なポイントです。GPS衛星は約30機が地球を周回し世界中をカバーしていますが、日本のように都市部の高層建築物の密集地や、山間部や谷あいなどの地域ではGPS信号を十分に受信できない場所が多くあります。その問題を解消するために、日本のほぼ真上を飛んで測位情報を提供し、GPSの機能を補完するのが準天頂衛星です。GPS衛星と準天頂衛星の情報を組み合わせることで、日本全国どこにいても測位可能時間が向上するようになります。このように、GPSを補完するという概念は日本独自のもので、米国のGPSの利用価値を向上させる観点から、我が国同様GPSを活用しているアジア・オセアニア地域においても、米国と協力しながら利用拡大を推進していきたいと考えています。
また、GPS衛星の精度が約10mに対して、準天頂衛星システムの補強信号は、その精度を約2m又は数cmと高精度にすることが可能です。このようにGPSなどのGNSS(地球的衛星測位システム)を補強する衛星をアメリカやヨーロッパも別途保有しています。これは、地域ごとに電離層等の状況が異なることから、精度を良くする手法は地域ごとに検討する必要があるからです。
このように準天頂衛星は、世界中をカバーする米国のGPSやロシアの「グロナス」と異なり、日本はじめアジア・オセアニア地域に特化したサービスを提供する衛星として考えています。GPSの補完と補強を1つの衛星で行うという日本独自の技術は、その利用において、アジア・オセアニア地域への海外展開に大いに期待できるものと考えています。
Q. 将来的には日本独自の測位衛星システムが必要になると思われますか?

平成23年9月の閣議決定で、2010年代後半を目途に準天頂衛星を4機体制とし、将来的には7機体制を目指すことが決まっています。7機あれば、GPS衛星など他国の衛星を頼らなくても、日本の準天頂衛星システムだけで測位ができるようになります。
Q. 今後の展望をお聞かせください。
2011年にアメリカはスペースシャトルを退役させ、国際宇宙ステーションへの輸送事業を民間企業に委託することとしました。それにより政府の財政負担を軽くし、自国の宇宙産業を育てるという目的もあわせて達成しようとしています。宇宙政策を国家として戦略的に進めているのです。このような世界の宇宙開発利用の現状を学びながら、我が国も国家戦略として宇宙政策を進めていきたいと考えています。
そのためにも、まず国家として行うべき宇宙政策の方向性につき、宇宙基本計画にまとめ、それに基づき、国全体で宇宙政策を進めていくための具体的な環境整備に努めていきたいと考えます。宇宙戦略室は、日本の宇宙政策の司令塔であり、準天頂衛星システムのような多様な分野で活用される宇宙インフラの開発・整備等を担当する組織として設置されましたので、その役割を十分に果たしていきたいと思います。
内閣府 宇宙戦略室 参事官
1986年東京大学工学部資源開発工学科卒業、同年通商産業省(現在、経済産業省)に入省。立地公害局鉱山課、生活産業局住宅産業課、資源エネルギー庁原子力産業課、工業技術院次世代産業技術企画室、英国留学(ロンドン大学インペリアルカレッジ環境工学科MSc取得)を経て、資源エネルギー庁石油部開発課、同庁石炭課、生活産業局紙業印刷業課の課長補佐、環境立地局総務課技術審査委員を歴任し、2000年には岐阜県多治見市理事・企画部長、2002年に経済産業省環境調和産業推進室長、2004年7月に独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構:金属資源開発調査企画グループリーダー、2006年7月に経済産業省製造産業局国際プラント推進室長、2008年7月に経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石炭課長。2010年8月から、内閣官房宇宙開発戦略本部事務局内閣参事官に着任。2012年7月より現職。
農機のロボット化で日本の農業問題を解決したい
視覚障害者の歩行環境を改善するために
日本発の屋内外シームレス測位の実現へ
衛星測位利用の高度化実用化に向けて測位精度のさらなる向上を目指す