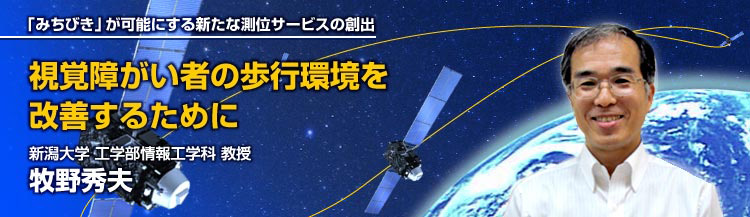Q. 歩行ナビの実証実験の結果はいかがでしたか?

周囲に建物がない皇居付近は測位信号の受信精度が高まる。(提供:牧野秀夫)
「みちびき」が打ち上げられたのが2010年9月で、私がこの実験を行ったのは2011年4月。この時はまだ受信機の動作が安定していなかったこともあり、銀座のビルの谷間ではうまく測位信号を受信できず、誤差が10mほどありました。問題なのは、ナビゲーションソフトが車道の中央を動くことを仮定していることです。例えば、晴海通りの北側の歩道を歩いていると、「南に3m移動してください」という案内が出てしまいます。通りの北側を歩いているのに、南側を歩いていると判断されることもありました。晴海通りは片側3車線もある広い通りなので、このような誤差が生じるのは問題です。
一方、銀座から皇居の方まで歩いてくると、周囲に建物がないため受信精度が高まり、数m単位の測位が可能になりました。ビルに囲まれた場所ではまだ改善の余地がありますが、公園のように見晴らしが良い場所だと、正確な案内ができることを実感しました。
Q. 実証実験から見えてきた課題は何でしょうか?
まずは、測位精度の向上です。視覚障がい者にとっては、歩道と車道の区別が付くほどの、1m単位の細かい測位情報が必要だと思います。それと、現在の地図情報だけでは、「ここは皇居です」とか「ここは市役所です」など、地図に載っている情報しか案内しません。これでは全盲者にとって十分とは言えず、「皇居のお堀を渡りました」とか「市役所の入り口はここです」といった、もっと詳しい情報が必要です。そこで、自分で携帯端末に付加情報を入力できる機能を用意して動作を確認しています。
また、「みちびき」が24時間利用可能にならないと、視覚障がい者にとって利用しやすいということにはなりません。なぜなら、「この時間帯は道案内できません」では不便だからです。ご存知の通り、「みちびき」はその軌道の関係で、日本の真上にあるのは1日8時間程度です。今は1機しかないので、現状は1日8時間しか利用できません。さらに多くの衛星があれば、24時間の運用が可能になりますので、早く2号機、3号機と打ち上がってほしいと改めて思いました。
Q. 視覚障がい者向けのナビゲーションを作ろうと思ったきっかけは何でしょうか?
20年程前にカナダの障がい者施設を訪れた時に、字幕が出る機能が付いているテレビがあって、それが日本の技術であることを知らされました。当時、アメリカでは新型のテレビには字幕機能を付けなければならないという法律がありました。しかし日本では、それを法律で義務化していなかったので普及しなかったのです。またカナダの方に、「私たちはこれほど日本の技術を使っているのに、なぜ日本の障がい者は恵まれていないのか」と言われ、顔から火が出る思いでした。日本を障がい者に優しい社会にしなければならないという気持ちになりました。
その後、新潟の盲学校の先生と知り合って、普段困っていることを聞いたら、「もっと外を歩きたい。でも外を歩く時に頼りになる点字ブロックは、どこにでもあるわけではない。豪雪地の新潟では、冬になると点字ブロックが雪に埋まって使えなくなってしまう」と言われたのです。そこで、天気や場所に関係なく、音声で位置情報を提供できるシステムを作りたいと思いました。「みちびき」の実証実験に参加したのも、視覚障がい者の方への道案内の精度を上げたいという強い思いがあったからです。
Q. 福祉分野での準天頂衛星の実用について、どんな将来像を描いていますか?

照明器具を利用した屋内案内システム(提供:牧野秀夫)
視覚障がい者の方が、24時間いつでもどこでも安心して歩ける環境を作りたいと思います。そういう意味で、照明器具からの可視光通信で位置を音声案内するシステムの研究も行っています。これがあれば、屋内や地下街でも、自分がどこを歩いているのかが分かるようになります。照明器具の裏に光を変調する回路が付いていて、その器具に交換するだけで特定の信号を出してくれるようになるため、新しい機器を設置する工事の手間も省けます。屋外では準天頂衛星を、屋内ではほかの方法を使って、視覚障がい者の方がどこにいても位置情報を提供するのが私の目標です。
また、位置情報は、自分の位置が正確に分かるだけでなく、障害物の位置なども分かるようにならなければならないと思っています。晴眼者にとっては気にならない少しの段差も、全盲者の方にとっては、大きな怪我につながるかもしれない重要な問題です。「みちびき」の高い精度を使って、「この先に行くと障害物がある」といった危険情報も案内できればと思います。
Q. 「みちびき」の実用化のために、まず必要なことは何だと思われますか?

歩行ナビゲーションの実証試験に使用した、準天頂衛星の受信機(左)と案内装置(右)(提供:岩下恭士)
視覚障がい者の方に限らず、より多くの方に「みちびき」を使ったサービスを利用していただくためには、「みちびき」の受信機がもっと改良されて、スマートフォンに内蔵するほど普及されなければなりません。準天頂衛星が複数機体制になれば受信機のマーケットも広がり、どんどん改良されるとは思いますが、もともと日本はカーナビをはじめ GPS受信機の技術は進んでいます。その中のソフトウエアを少し変えれば「みちびき」対応になるのではないかと期待しています。受信機の導入コストがかからなければ、「みちびき」の実用化はどんどん進むと思います。やはり、一般に広めるということがポイントですね。
先ほど、照明器具を利用した屋内案内システムの話をしましたが、最終的には視覚障がい者向けであっても、晴眼者の方も使えるシステムとして研究を進めています。なぜなら、障がい者の方だけを対象にした製品は、マーケットが小さく、多額の開発費を投入しても採算がとれないという問題が生じるからです。製品を大量生産できなければ、価格も高くなってしまいます。やはり、安くないと売れないし、売れるからこそ改良が進むということになると思います。ですから、障がい者の方へのサービスを考える時には、最初から、健常者も障がい者も使える「共用品」として開発を行い、それが世に出た時に、一気に広められる環境を作っておくことが大事だと思います。
新潟大学工学部情報工学科 教授。工学博士
1976年、新潟大学工学部電子工学科卒業。1978年同大学大学院修士課程修了、同年4月より同大学情報工学科勤務。1990年助教授、1995年教授。1996年には、アメリカ・カリフォルニア大学サンタバーバラ校にて、GPSの測位精度を補正する研究に従事。近年は、照明光通信や地理情報システムなどの技術研究を行う。専門は、情報機器、情報処理システム、医療機器の開発など。
農機のロボット化で日本の農業問題を解決したい
視覚障がい者の歩行環境を改善するために
日本発の屋内外シームレス測位の実現へ
衛星測位利用の高度化実用化に向けて測位精度のさらなる向上を目指す