「ひので」には、可視光・磁場望遠鏡、X線望遠鏡、極端紫外線撮像分光装置の3つの望遠鏡が搭載されます。
可視光・磁場望遠鏡は、先ほど申し上げたとおり、太陽磁場をベクトル的に捉えるほか、異なった温度の層から放射されるいろいろな光で太陽を立体的に観測できます。
X線望遠鏡は、コロナのダイナミックな活動や加熱のようすを画像として捉えます。1991年に打ち上げられたX線太陽観測衛星「ようこう」の軟X線望遠鏡の発展型で、解像度がおよそ3倍に上がっています。広い温度範囲にわたって高い感度を持ち、100万度以下の低温から1000万度以上の高温の温度層までを撮像することができます。
極端紫外線撮像分光装置、いわゆる紫外線望遠鏡は、いろいろなスペクトル輝線で太陽の画像を撮り、そのスペクトルを解析することによって、コロナ流体の運動や、温度、密度などを詳細に調べることができます。これを、プラズマ状態の診断と言っています。
「ひので」は、この3つの望遠鏡で同じところを見て、これまでにない高精度で太陽表面とコロナを同時に観測します。太陽表面の磁場を詳しく測り、その上空にあるコロナの爆発現象の画像や、プラズマ状態の診断をした結果を照らし合わせて総合的に見ることで、いったいそこで何が起こっているのかを立体視します。しかも、どういう磁力線が太陽コロナを貫き、磁力線の形がどうなったら爆発が起きるのかまで、詳細に調べることができます。異なった性能・特長を持った3つの望遠鏡を1つの衛星に搭載し、太陽の同じ場所を同時に観測するのは、史上初の試みです。
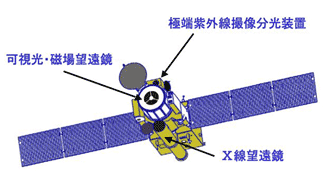

可視光・磁場望遠鏡

極端紫外線撮像分光装置

X線望遠鏡
「ひので」の3つの望遠鏡はすべて国際協力でつくられています。可視光・磁場望遠鏡は、望遠鏡の本体部分を日本が担当し、磁場を観測する検出装置はアメリカが担当しました。X線望遠鏡は、アメリカが望遠鏡の本体、日本がCCDカメラの検出器の担当です。また、紫外線望遠鏡はイギリスがとりまとめ役となりました。打ち上げ後は、衛星のデータの大部分は、ヨーロッパ宇宙機関(ESA)の協力によりノルウェーの局で受信します。このように、「ひので」は日米欧の国際共同プロジェクトとして進められてきました。
一方、日本国内では、JAXA宇宙科学研究本部と、「すばる」望遠鏡を開発した国立天文台のメンバーを主力とする全国規模のチームをつくり、「ひので」プロジェクトを推進してきました。
「ひので」のプロジェクトがスタートしたのは1999年ですが、それに先立つ基礎研究の段階から、「ひので」での活用をめざして熱膨張の小さい素材の開発に取り組みました。太陽を観測すると、衛星の中に太陽の強い光と高温の熱が入りますから、もし望遠鏡の筒の部分が熱膨張してしまうような素材ですと、焦点距離が変わり観測精度に影響が出てしまいます。たとえ温度が変化しても、それに対応できる素材を開発するのにとても苦労しました。また、0.2秒角で写真を撮る場合、カメラが手ぶれを起こしたら何にもなりません。軌道をまわる衛星はごくわずかですが揺らいでおり、通常は無視できるこの揺らぎも0.2秒角を達成するためには大きな障害になります。私たちは、望遠鏡が揺れても、それを全部補正して、数秒間ピタっと画像が止まるような技術を開発しました。

太陽観測衛星 「ひので 」
これらはほんの一端にすぎません。「ひので」では、今までにない新しい技術を他にも数多く開発してきましたが、それらを共同で設計するよう努めました。設計にあたってはお互いにすべて見えるように共同で検討し、実際に作る段階では各国が得意な分野を活かして分担製作をするという形でプロジェクトを進めてきたのです。実際には、技術を盗まれるから見せられないといった障壁もあり、国際協力はなかなか一筋縄ではいかないところもありましたが、「共同開発」という言葉にふさわしい実績が残せたのではないかと思います。