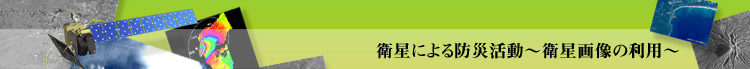



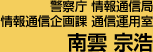
Q. 警察庁ではどのような災害対策活動をされているのでしょうか?
山城:災害が発生した場合、私たち警察は、被災者の救助や避難誘導などをいち早く行います。救出救助も含めた災害時の警察活動を、災害警備と言います。警察の役目は、国民の安全を守ること、治安を維持することですが、そのためのさまざまな活動の1つの分野が災害警備です。災害が発生した時は、被災地以外の警察とも連携して、全警察的に警備にあたります。
災害対策活動は、国を挙げて行わなければなりません。内閣府の防災担当を中心に、警察、消防、自衛隊という実動部隊があり、いろいろな関係省庁や自治体も加わって相互協力し、国が一体となって取り組みます。警察は、いざ災害が起きたらどうするかというのが任務の中心です。救出を待っている国民の下に一刻も早く駆けつけるという、災害応急対策が私たちの役目です。
Q. その中で、お二人は具体的にどのような仕事をなさっているのでしょうか?
山城:私は警備局警備課の災害対策室に所属しています。災害が発生した場合に、警察活動の全般を調整する窓口的な役目を果たします。例えば、2007年3月25日に能登半島地震が起きましたが、発生直後に石川県警や他の県警と連絡を取り、応援の警察官の派遣を調整したり、災害警備活動の指導を行いました。また、被災地の情報を収集し、総理官邸などに被害状況を報告しました。災害は基本的に国が積極的に対策を支援するべきなので、すぐに情報を集めて総理官邸に伝えるのも私たちの仕事です。
南雲:私が所属する情報通信局の通信運用室は、警察活動の通信系統の運用を行っています。災害が起きると、被災地から県警本部や警察庁へ音声や映像などの被災情報が伝送されますが、その通信網の確保を担っています。情報を迅速に伝送することは、災害対策を行う上で、とても重要なことです。また、被災地域の衛星画像を解析して、当庁や各都道府県警察へ情報提供することにより、警察活動を支援しています。
能登半島地震の被災地。赤丸は被害地を示す。左図では崩れた土砂が道路を封鎖している様子、右図では斜面が崩壊し茶色土が見えている様子が分かる。
(左:輪島市門前町深見付近、右:輪島市輪島崎町付近)
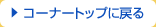
山城:災害が発生した場合、私たち警察は、被災者の救助や避難誘導などをいち早く行います。救出救助も含めた災害時の警察活動を、災害警備と言います。警察の役目は、国民の安全を守ること、治安を維持することですが、そのためのさまざまな活動の1つの分野が災害警備です。災害が発生した時は、被災地以外の警察とも連携して、全警察的に警備にあたります。
災害対策活動は、国を挙げて行わなければなりません。内閣府の防災担当を中心に、警察、消防、自衛隊という実動部隊があり、いろいろな関係省庁や自治体も加わって相互協力し、国が一体となって取り組みます。警察は、いざ災害が起きたらどうするかというのが任務の中心です。救出を待っている国民の下に一刻も早く駆けつけるという、災害応急対策が私たちの役目です。
Q. その中で、お二人は具体的にどのような仕事をなさっているのでしょうか?
山城:私は警備局警備課の災害対策室に所属しています。災害が発生した場合に、警察活動の全般を調整する窓口的な役目を果たします。例えば、2007年3月25日に能登半島地震が起きましたが、発生直後に石川県警や他の県警と連絡を取り、応援の警察官の派遣を調整したり、災害警備活動の指導を行いました。また、被災地の情報を収集し、総理官邸などに被害状況を報告しました。災害は基本的に国が積極的に対策を支援するべきなので、すぐに情報を集めて総理官邸に伝えるのも私たちの仕事です。
南雲:私が所属する情報通信局の通信運用室は、警察活動の通信系統の運用を行っています。災害が起きると、被災地から県警本部や警察庁へ音声や映像などの被災情報が伝送されますが、その通信網の確保を担っています。情報を迅速に伝送することは、災害対策を行う上で、とても重要なことです。また、被災地域の衛星画像を解析して、当庁や各都道府県警察へ情報提供することにより、警察活動を支援しています。
(左:輪島市門前町深見付近、右:輪島市輪島崎町付近)
Q. 衛星を使った災害活動への支援は、どのようなことを期待されていますか?
山城:とにかく、すぐに被災地の情報が欲しいです。被災者の救出救助にどのくらいの警察官を送り込まなければいけないかを、迅速に判断しなければいけませんから、情報は少しでも早く、発災から30分もしくは1時間で欲しいというのが希望です。遅くても1日以内に被災状況が分かれば、私たち警察だけでなく、消防や自衛隊にも非常に役立つと思います。また、衛星は観測幅が広いというのがメリットです。人が入れないような所も、衛星写真を撮れば被災地の様子が一目瞭然です。実際に能登半島地震の時は、地球観測衛星「だいち」の画像を使って、数カ所の崖崩れの位置を把握することができました。私たちは、ヘリコプターテレビ伝送システムを使って被災地の情報を収集していますが、それでは把握できない部分を衛星にカバーして欲しいと思います。「だいち」は悪天候でも撮影が可能だと聞いていますので、天候に左右されない観測にも期待しています。
さらに、災害がない平常時に衛星をどう活用しようかというのを、 JAXAのワーキンググループの方と検討していますが、私は立体的な地図情報に期待しています。衛星写真を元に、避難場所や避難経路を整理し、防災計画に役立てることができればと思います。また、平常時の詳細画像があれば、災害が起きた時の画像と重ね合わせて比較し、被害状況を把握することもできます。今まであった道路やビルが倒壊しているとか、緊急避難場所が使える状態にあるかといった災害時の情報は、衛星画像を基に把握できるようになればいいと思います。
南雲:災害活動に使う衛星は、通信衛星と地球観測衛星の2種類あります。いずれにしても、音声なり映像・画像で被災状況を把握するために使うわけですが、被災地の場所を問わず、常時使える衛星を期待しています。被災地の場所によっては無線が届かない場所がありますが、そのような所でも衛星から見れば即座に状況が分かります。例えば、道路が寸断していると、いくら応援部隊を車で派遣しても通れませんから、そういった交通情報も衛星画像から得ることができればと思います。また、地上の通信網が不通になってしまった場合に、携帯電話ほどの大きさの移動地上局と衛星を経由して、情報を伝送することができるようになればいいと思います。これはすでにJAXAでもいろいろな実験が行われているようですが、ぜひ実現して欲しいと思います。
Q. 衛星を使った災害活動の今後の課題は何だと思われますか?
山城:スピードと分解能です。衛星は地球軌道を回っていますので、どうしても時間的なロスが生まれてしまいます。災害が起きた時にその上空にいなければ、即座に撮影することはできません。また、「だいち」は2.5mの分解能がありますが、山間部を見るならば、その解像度でもよいと思います。しかし、東京で地震が起きた場合は、どのビルや道路が損壊しているかという詳細な情報が必要です。分解能は地域や人口密度などによってニーズが違ってきますが、より高精細な画像が望まれます。
南雲:私もそう思います。やはり、分解能が1m以下でないと物足りないというのが本音です。また、衛星は一度に広い範囲を撮影できるのがメリットです。能登半島地震の時も、半島全体を1回で撮影できましたので、その観測幅には感心しました。しかし、悪天候の場合、地上の状況が写らないことが問題点です。「だいち」の合成開口レーダ(SAR)が悪天候に影響されないといっても、分解能は10mですから、細かい被災状況を見ることはできません。さらに、地球観測衛星は、原則的に衛星軌道で決まる撮影日時しか撮影ができないので、災害直後に迅速に対応できないこともあります。その点が改善できたら、災害時に衛星を活用する機会がもっと増えると思います。
Q. 今後、JAXAに対して、どの様な要望がありますでしょうか?
山城:「だいち」には非常に期待しているところが多いですが、今後さらに性能をアップした衛星を打ち上げていただきたいと思います。警察庁は、あくまでも47都道府県警の調整指導をするという立場で、実際に動くのは各都道府県の警察です。JAXAからいただいた情報を、もっと各都道府県に還元できる、情報を伝える流れを作りたいと思っています。そのためにも、24時間365日、常に情報をいただけるようなシステムを作って欲しいです。災害はいつどこで起きるか分かりません。発災した時に、すぐに画像を比較できるように、また、防災計画を立てるためにも、平常時の衛星画像が全国規模であればとても役立つと思います。そうすれば、警察としても、もっと衛星を活用できると思います。
南雲:防災マップなどは平面の地図が使われていますが、衛星画像を地図の代わりに使えるようになればいいと思います。衛星画像の利点は、立体的に見えるということです。また、地図では、公園は「公園」としか書いておらず、何があるかまでは分かりません。衛星画像ですと、公園内の建物の形まで分かります。等高線だけの地図ではなく、立体的な衛星写真があればとても便利です。さらに、地図は1年に1回書き換えればよい方ですが、衛星の場合は、今の新しい情報が分かるというのも利点です。
通信衛星も地球観測衛星も、災害対策にはなくてはならないものだと思います。ですから、今まで以上に各種衛星サービスを充実して提供していただければと思います。いつでも、どこでもどんな時にでも使える衛星を開発、運用して欲しいです。「だいち」のデータも、白黒とカラーで別々に提供されるのではなく、合成したパンシャープン画像(※)を、発災時にすぐ提供できるよう整備しておいてくれれば、より迅速・効果的に活用できると思います。
※パンシャープン画像:高解像度のモノクロ画像と低解像度のカラー画像を組み合わせて作成した高解像度のカラー画像
山城:とにかく、すぐに被災地の情報が欲しいです。被災者の救出救助にどのくらいの警察官を送り込まなければいけないかを、迅速に判断しなければいけませんから、情報は少しでも早く、発災から30分もしくは1時間で欲しいというのが希望です。遅くても1日以内に被災状況が分かれば、私たち警察だけでなく、消防や自衛隊にも非常に役立つと思います。また、衛星は観測幅が広いというのがメリットです。人が入れないような所も、衛星写真を撮れば被災地の様子が一目瞭然です。実際に能登半島地震の時は、地球観測衛星「だいち」の画像を使って、数カ所の崖崩れの位置を把握することができました。私たちは、ヘリコプターテレビ伝送システムを使って被災地の情報を収集していますが、それでは把握できない部分を衛星にカバーして欲しいと思います。「だいち」は悪天候でも撮影が可能だと聞いていますので、天候に左右されない観測にも期待しています。
さらに、災害がない平常時に衛星をどう活用しようかというのを、 JAXAのワーキンググループの方と検討していますが、私は立体的な地図情報に期待しています。衛星写真を元に、避難場所や避難経路を整理し、防災計画に役立てることができればと思います。また、平常時の詳細画像があれば、災害が起きた時の画像と重ね合わせて比較し、被害状況を把握することもできます。今まであった道路やビルが倒壊しているとか、緊急避難場所が使える状態にあるかといった災害時の情報は、衛星画像を基に把握できるようになればいいと思います。
南雲:災害活動に使う衛星は、通信衛星と地球観測衛星の2種類あります。いずれにしても、音声なり映像・画像で被災状況を把握するために使うわけですが、被災地の場所を問わず、常時使える衛星を期待しています。被災地の場所によっては無線が届かない場所がありますが、そのような所でも衛星から見れば即座に状況が分かります。例えば、道路が寸断していると、いくら応援部隊を車で派遣しても通れませんから、そういった交通情報も衛星画像から得ることができればと思います。また、地上の通信網が不通になってしまった場合に、携帯電話ほどの大きさの移動地上局と衛星を経由して、情報を伝送することができるようになればいいと思います。これはすでにJAXAでもいろいろな実験が行われているようですが、ぜひ実現して欲しいと思います。
Q. 衛星を使った災害活動の今後の課題は何だと思われますか?
山城:スピードと分解能です。衛星は地球軌道を回っていますので、どうしても時間的なロスが生まれてしまいます。災害が起きた時にその上空にいなければ、即座に撮影することはできません。また、「だいち」は2.5mの分解能がありますが、山間部を見るならば、その解像度でもよいと思います。しかし、東京で地震が起きた場合は、どのビルや道路が損壊しているかという詳細な情報が必要です。分解能は地域や人口密度などによってニーズが違ってきますが、より高精細な画像が望まれます。
南雲:私もそう思います。やはり、分解能が1m以下でないと物足りないというのが本音です。また、衛星は一度に広い範囲を撮影できるのがメリットです。能登半島地震の時も、半島全体を1回で撮影できましたので、その観測幅には感心しました。しかし、悪天候の場合、地上の状況が写らないことが問題点です。「だいち」の合成開口レーダ(SAR)が悪天候に影響されないといっても、分解能は10mですから、細かい被災状況を見ることはできません。さらに、地球観測衛星は、原則的に衛星軌道で決まる撮影日時しか撮影ができないので、災害直後に迅速に対応できないこともあります。その点が改善できたら、災害時に衛星を活用する機会がもっと増えると思います。
Q. 今後、JAXAに対して、どの様な要望がありますでしょうか?
山城:「だいち」には非常に期待しているところが多いですが、今後さらに性能をアップした衛星を打ち上げていただきたいと思います。警察庁は、あくまでも47都道府県警の調整指導をするという立場で、実際に動くのは各都道府県の警察です。JAXAからいただいた情報を、もっと各都道府県に還元できる、情報を伝える流れを作りたいと思っています。そのためにも、24時間365日、常に情報をいただけるようなシステムを作って欲しいです。災害はいつどこで起きるか分かりません。発災した時に、すぐに画像を比較できるように、また、防災計画を立てるためにも、平常時の衛星画像が全国規模であればとても役立つと思います。そうすれば、警察としても、もっと衛星を活用できると思います。
南雲:防災マップなどは平面の地図が使われていますが、衛星画像を地図の代わりに使えるようになればいいと思います。衛星画像の利点は、立体的に見えるということです。また、地図では、公園は「公園」としか書いておらず、何があるかまでは分かりません。衛星画像ですと、公園内の建物の形まで分かります。等高線だけの地図ではなく、立体的な衛星写真があればとても便利です。さらに、地図は1年に1回書き換えればよい方ですが、衛星の場合は、今の新しい情報が分かるというのも利点です。
通信衛星も地球観測衛星も、災害対策にはなくてはならないものだと思います。ですから、今まで以上に各種衛星サービスを充実して提供していただければと思います。いつでも、どこでもどんな時にでも使える衛星を開発、運用して欲しいです。「だいち」のデータも、白黒とカラーで別々に提供されるのではなく、合成したパンシャープン画像(※)を、発災時にすぐ提供できるよう整備しておいてくれれば、より迅速・効果的に活用できると思います。
※パンシャープン画像:高解像度のモノクロ画像と低解像度のカラー画像を組み合わせて作成した高解像度のカラー画像




