
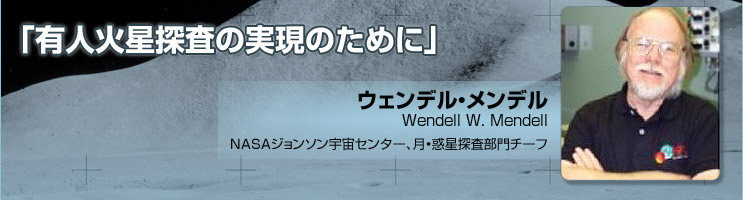
Q.アメリカの有人月探査計画の現状を教えて下さい。
2004年1月、アメリカ合衆国大統領は、これから20年から30年の間にNASAが達成すべき有人宇宙計画に関する重要な演説を行いました。そのうちの一つが、月探査をはじめとする太陽系探査です。この演説後にアメリカ議会でもその内容が討議されましたが、以来、NASAは、具体的な計画の作成に取りかかっています。最も新しいところでは、将来地球から月へ、そして火星へ人間を運べる新ロケットと有人宇宙船の建設計画が発表されています。それからつい先日、2006年12月に開かれたNASAの会見では、2020年までにどのようにして月着陸を実現させるか、また、月での活動構想について説明がありました。月面基地を建設して宇宙飛行士を送り、一週間ほど滞在させるというものです。まだ先のことなので、2020年に何が起っているか、確かなところは誰にも知る由がありません。しかし、もしアメリカに引き続き宇宙計画があって大統領や議会が承認していたら、必要な機器を作り、月着陸を実現させるだけの能力はNASAにあります。明らかにこのことは国の認可が必要ですから、アメリカの政治システムによって入れ替わる大統領と議会に検討され続けることになります。しかし今、NASAはこれらの宇宙計画に向けて動いています。現在のNASAの任務は、宇宙船やロケットの建設と、月着陸後の人類の活動の構想を考え、実現へ向けて着実に進んでいくことです。
Q.博士は月計画が火星へのステップになるとお考えですか?

火星を探査する宇宙飛行士(提供:NASA)
はい。月は火星への足がかりになると強く信じています。しかし、月面でロケットを建設するというようなことではありません。火星へはかなりの長旅で、往復におよそ3年を費やします。したがって、宇宙飛行士たちは旅の途中で遭遇する問題を自分たちで解決しなければなりません。それに、火星への長旅の間には心理的、肉体的問題も発生してくるでしょうから、クルーとやりとりするミッションの管制オペレーションは、今までとはかなり違ったものにする必要があります。ミッションの管制室からの指示を待つのではなく、クルー自らが判断を下すことが多くなるでしょう。また、彼らが使う装置の心配もしなくてはいけません。装置関係は惑星の環境下でも使用できるしっかりした設計で、高い信頼性が要求されます。こういった観点からも、月での活動はいい訓練になるでしょう。惑星で使用できる装置の設計や、長期にわたるこのような閉鎖環境の中での宇宙飛行士の反応を見ることができます。また、宇宙飛行士が生産的かつ快活に仕事ができ、成果のある仕事をして無事に帰還できるようなミッションの運営の研究も大切です。これら全てを学ばなければならないと思います。
Q.アポロ計画と今回の月計画の違いは何ですか?
大きな相違点は2つです。第一に、月へ行く目的です。アポロ時代のアメリカは、旧ソビエト連邦と冷戦状態にありました。1961年には、アメリカは旧ソ連と同じくらい、いや、それ以上に強い国家であるということを世界に証明するため、技術面で何か劇的なことに挑もうとする気運が強くありました。アポロ計画誕生の背景には、このような政治が絡んだ開発競争があったのです。二つ目の相違点は、アポロ計画の目的は純粋に人を月面へ運び、無事に地球へ連れ帰ってくることにあり、それ以外のことには触れられていませんでした。しかし後に計画が続行されるに従って、科学実験やさまざまな発見が生まれ、ミッションの可能性を広げることに成功しました。しかし、どのアポロミッションも月での滞在日数は短いものでした。
今回の月探査計画の目的は、もっと広範囲にわたります。人類が地球の外に移住できる可能性を示し、月や宇宙での活動を通してアメリカ経済発展の可能性を高めること、月探査という大事業に諸外国と国際協力をしながら取り組むことなどです。その他にも、クルーが長期的に住み、作業を行える施設の建設も目指しています。月での作業の進め方や、月に相応しい装置の研究を行いますが、その知識を生かして火星探査に向けた装置の開発も目指します。新月探査計画は、以前よりも非常に複雑で多岐にわたる大規模なもので、長期にわたる目標を掲げています。
Q.今回はなぜ、有人探査なのでしょうか?
1961年にアメリカ初の有人宇宙飛行を行ったアラン・シェパード以来、アメリカは宇宙飛行士を宇宙へ送り続けています。ご存知のように、旧ソ連、現在のロシア連邦もずっと宇宙飛行士を送っています。なぜこのような事業を国家が行う必要があるのか、なぜロボットではなく、費用のかかる人間をわざわざ宇宙へ送るのか懸念する人は大勢います。2003年、スペースシャトル・コロンビア号の大惨事が起きた当時は、アメリカ議会によるヒアリングや調査が行われましたが、その中で有人宇宙プログラムの是非も問われました。多くの議論の末に国のトップが出した結論は、有人宇宙プログラムがアメリカの若者にインスピレーションを与えること、国と社会におけるテクノロジーの向上に貢献すること、そして私たちアメリカ人は探検、前進し、可能性を見出しながら新しい環境を創造することを願う人種である、ということでした。ほかの国は異なる考えを持っていて、人類や宇宙飛行士が宇宙へ行くことに投資価値はないと感じるかもしれません。それはそれでいいのです。しかし、月へ、宇宙へ向かうこと、これがアメリカが下した決断です。
Q.有人月探査は無人月探査より重要だと思われますか?

月面車で移動する宇宙飛行士と探査ロボット
(提供:NASA)
それぞれ用途が異なります。もし「ハッブル」のような望遠鏡や、「はやぶさ」のような小惑星探査を目的とする小型衛星を飛ばしたいなら、長期間オペレーションが可能な小型ロボットを作るほうが効率的です。しかし、有人探査はある一定の環境、特に惑星の特定の環境に向いています。人間はより早く発見したり、惑星にある資源の利用方法を研究することができます。長期の作業も、居住も可能です。ただし、研究者は、有人か無人かということを気にしません。遠くの星や、生物学上の新しい情報を見つけることだけに関心があり、宇宙に人を送るかといった問題はさほど重要ではないのです。しかし、宇宙で人間が行う任務に価値があると思うならば、ロボット(観測機器)と一緒に行く人間にも投資する必要があります。ただ、これまで機械が行ってきたことを人間がすべて行うのではありません。遠くにある惑星にはこれまで通り探査機を送り、銀河は望遠鏡で観測すればよいと思います。そんなところにまで人間が必ずしも行く必要はありません。つまり、何を達成したいのか、どんなミッションを遂行したいかによります。ですから、有人か無人かという二者択一の問題ではないと思います。
Q.博士にとって月計画の魅力は何でしょうか?
ずっと月の研究を専門にしていますから、月の科学的新発見にとても興味があります。私は、これまで非常に長い間、月における人類について語ってきました。25年前からすでに、月に人類が住む時はどんな設備が必要なのだろうと考えていたほどです。私にとって月探査の魅力は、月での新しい発見をしたり、惑星における居住の可能性について研究することです。
Q.もし機会があったら、月に行ってみたいですか?
私はもう歳をとりすぎていますから無理ですね。地上で月の研究をしていたいと思います。
Q.日本の月探査計画の印象をお聞かせ下さい。
私は日本の研究者やエンジニアをたくさん知っていますが、彼らの知性と能力には大変感心しています。特に、小惑星探査機「はやぶさ」や太陽のX線天文学分野で成功を収めている方たちを尊敬しています。今年打ち上げ予定の月周回衛星「セレーネ」は、本格的な月の観測を行える、非常に野心的で高度な衛星です。日本のチームは素晴らしいと思います。彼らにはぜひ成功してもらいたいです。そして、彼らの探査機が無事に飛んで、月でたくさんの情報を得た暁には、そのデータを私たちと共有してくれることを願っています。
Q.有人月探査計画における国際協力についてどう思われますか?
国際協力はとても重要だと思います。研究者である私には、国境を超えた研究者との仕事の取り組みはごく自然なことです。残念ながら政治的な理由で国際協力が行えない国もあります。それに現在のアメリカでは、技術共有に関する法的規制があるため国際協力は特に困難です。しかし長い目で見れば、月計画やほかの宇宙活動のための国際協力は、とても大切だと信じています。これまでも私は国際協力の推進に努めてきました。もちろん、今後も日本の方たちと一緒に研究する可能性はあるでしょう。日本のチームは非常に優秀で素晴らしい仕事をしますから、そういうスタッフと一緒に成功を収めたいですね。日本人と一緒に仕事をするのが楽しみです。
Q.今、なぜ人類は月を目指すのでしょうか?
第一に、私たち、少なくともアメリカは、地球から遠く離れた火星への長期におよぶ有人探査に乗り出すことを決めました。そして、太陽系で宇宙での居住方法や作業の仕方を学ぶには、月が地球から一番近い距離にあります。これが月に興味がある理由の1つです。
次に、月は地球と似ていることです。月は地球の一部です。地球と違って月には天候も海洋も存在しませんし、大陸も動きませんが、月を研究することで、地球に関する多くのことが解明できます。また、月には古代の太陽系の形跡が多く残っていますので、地球や月の初期の時代の太陽系がどのようであったかを示す証拠も見つけることができます。月を調査することは地球をもっと理解することになります。これほど素晴らしい月のそばに住んでいるという事実を、私たちはもっと上手く活用できるようになると思います。
もちろん、ただ宇宙旅行の冒険をしてみたいという理由で月に興味を持っている人もいます。月だけでなく、火星や小惑星にも行ってみたいと思っているかもしれません。「100年後の未来には、人類は宇宙で活動しているはずだから興味がある」という人たちもいますが、こういった方たちは、宇宙に行くという素晴らしい活動の先駆者になりたいのでしょう。また、もともと宇宙に関心があり、「宇宙環境を体験できる場所の一つが月だから興味がある」という人もたくさんいるでしょう。人が月に興味を持つ理由は千差万別です。なぜ人類が月を目指すのかという問いの答えはたくさんあると思います。
NASAジョンソン宇宙センター、月・惑星探査部門チーフ
カリフォルニア工科大学物理学科卒業後、カリフォルニア大学にて物理学で修士号、ライス大学では宇宙科学で修士号、天体物理・天文学で博士号を取得。惑星表層のリモートセンシング、特に月の熱放射測定とスペクトロスコピーが専門。国際宇宙大学で教鞭をとるほか、国際宇宙航行アカデミーの宇宙技術およびシステム開発に関する学術委員会で活躍するなど、多くの科学協会や技術協会に所属。1982年以来、有人太陽系探査に関する計画と提唱を行っているが、特に恒久的な有人月面基地の建設の実現に力を入れている。