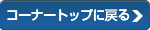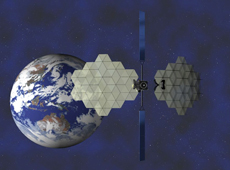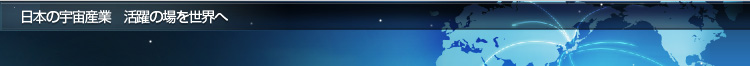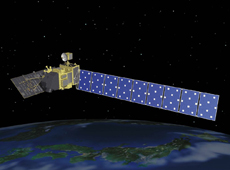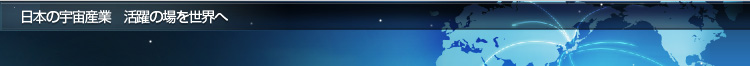

Q. JAXAはAPRSAF(アジア太平洋地域宇宙機関会議)などでアジア諸国との連携を図ってきましたが、このことは宇宙産業の海外展開にも貢献すると思われますか?
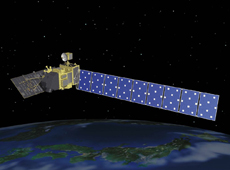
陸域観測技術衛星「だいち」
JAXAは、アジア太平洋地域の自然災害の監視を行う「センチネル・アジア」などのプロジェクトを立ち上げアジア諸国との連携を推進してきました。タイやインドネシアなどで自然災害が起こると、陸域観測技術衛星「だいち」で緊急観測を行い被災地の衛星画像を提供するなど、災害対策支援の実績が評価されています。また、宇宙利用の促進を目的としたシンポジウムをアジア諸国で開催したり、日本の地球観測衛星のデータを活用したいという国に対してデータ処理や解析方法を教えるといった取り組みも行ってきました。そのような活動を通して、アジア諸国の宇宙機関とは信頼関係を築いておりとてもいい関係にあると思います。
その信頼関係を、ぜひ宇宙産業の海外展開に活かしたいと考えています。日本はかつてアメリカから宇宙技術を導入し、咀嚼し、自分のものにしました。同じように、JAXAの経験や技術、ノウハウは、新しく宇宙開発に参入したい新興国にとって非常に魅力的なものだと考えています。
例えば、企業がアジア諸国に衛星を売り込みに行く際にはJAXAが同行して、「これはJAXAが使ったものですから大丈夫です」と太鼓判を押したり、相手国の宇宙機関からの相談にのる事ができると思います。日本の衛星を買ってくれたら、その衛星ミッションに合った人材育成や研修などのサービスを付けるといった提案もできます。そのほかにも、JAXAの試験設備を衛星の試験のために提供するとか、もしも自国に宇宙機関を設立したいという要望があれば、そのノウハウを提供するという提案もできるでしょう。このようなサービスを提供することで企業の受注活動を支援することができればと思います。
これはつまり、「オールジャパン体制」で日本の宇宙産業を支援するということにつながります。新興国の場合は、衛星データを利用するための地上インフラの整備などが必要になることがありますので、JAXAだけでなく関係省庁、国際協力銀行、ODA(政府開発援助)などが企業と一緒にチームをつくって受注活動をする必要があると思います。

Q. JAXAと産業の連携で生まれた、海外展開における最近の主な成果を教えてください。
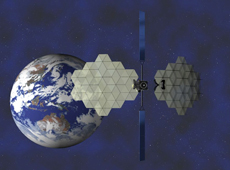
三菱電機が開発した標準衛星バス「DS2000」の原型となった技術試験衛星VIII型「きく8号」
他国の衛星を打ち上げる輸送サービスと、衛星を受注するという2つの面で成果が出ています。まず打ち上げサービスでは、2009年に三菱重工業株式会社が韓国航空宇宙研究院(KARI: Korea Aerospace Research Institute)から同国の多目的実用衛星3号機(KOMPSAT-3)の打ち上げを受注しました。日本の企業が海外の衛星を打ち上げるのは初めてです。KOMPSAT-3は2011年度にH-IIAロケットでJAXAの水循環観測衛星GCOM-Wと相乗りで打ち上げられる予定です。H-IIAロケットは、宇宙開発事業団(現JAXA)の時代から開発してきたロケットで、三菱重工業が製造を行ってきました。2007年度に打ち上げ業務が民営化され、三菱重工業に移管されています。
一方、衛星に関しては、2008年に三菱電機株式会社が、シンガポールと台湾の通信会社が共同で打ち上げる通信衛星「ST-2」を受注し、さらに2011年3月には、トルコ国営衛星通信会社より、同国の通信衛星を2機「Turksat-4A」「Turksat-4B」を受注しました。「ST-2」と2機の「Turksat」には、JAXAの技術試験衛星VIII型「きく8号」とデータ中継技術衛星「こだま」をベースに三菱電機が開発した標準衛星バス「DS2000」が使われています。
衛星バスというのは衛星の基幹部分ですが、もともと「きく8号」の開発目標の1つが、国際競争力を持つ3トン級の静止衛星のバスを作ることであり、将来的な海外展開を意識していました。これらの成果や昨年度終了した産業連携による静止衛星バスの軽量化研究の成果をベースにし、三菱電機がこの衛星バスを世界市場にも適応するように改良して、海外衛星の受注につなげたのです。また、このトルコ衛星の受注活動については、三菱電機だけでなく日本政府が主導し、宇宙開発戦略本部や外務省、文部科学省、JAXA等が一体となって行われました。

Q. 海外展開について、今後の展望をお聞かせください。

企業との連携をもっと深めて、海外展開の支援を充実させたいという思いがあります。これまでにも、JAXAの衛星をベースに開発された太陽電池パドルや地球センサなどの衛星搭載機器が海外で売れるということはありました。今後はさらに宇宙機器産業の海外展開を支援するためにも、研究開発の段階から世界市場を視野に入れて、どのような新技術が世界的に求められているのか、また、商業衛星市場など民間の需要も考慮しながら研究開発を行う必要があると考えています。
また受注活動においても、最良な方法をとれるよう企業とうまく連携していきたいと考えています。先ほど、海外展開は「オールジャパン体制」で行う必要があると申し上げましたが、それは衛星本体など大きいビジネスの場合です。機器レベルの受注は、主に先進国の宇宙機器メーカーが交渉相手となりますので、企業とJAXAだけで動いた方が良い場合もあり、案件によって的確な対応をとることが望まれます。
宇宙基本法によって、現在日本の宇宙開発体制の見直しの議論が行われていますが、どのような体制になってもJAXAとして宇宙開発の発展および宇宙産業の拡大に寄与できればと思っています。
Q. JAXAとしてはもっと産業連携を強化していきたいということですね。

相乗り衛星を搭載したH-IIAロケット17号機の打ち上げ(2010年5月)
JAXAの産業連携センターは、これまでお話したような宇宙機器産業に対する支援だけではなく、宇宙産業の裾野を拡大するような施策もあわせて行っています。具体的には、オープンラボ、相乗り小型衛星といった取り組みです。
オープンラボには、JAXAの技術を外部の方が利用して商品化する「スピンアウト」と呼ばれる活動と、外部の技術を宇宙開発に持ち込むという「スピンイン」の活動があります。「スピンアウト」の事例としては、宇宙船内服の技術を応用した消臭効果の高い下着や、ロケットで使われている断熱塗料を住宅用に応用した塗料などが挙げられます。また「スピンインの例としては、荷造り用の緩衝材を太陽電池パネルに応用できないかといった研究開発も行われていますし、「こうのとり」に地上のLED照明が採用されました。
相乗り小型衛星は、企業や大学の衛星開発を支援する取り組みです。衛星を作るためには技術やノウハウを必要としますし、ロケットで衛星を打ち上げるには莫大な費用が掛かります。まずJAXAでは、衛星を開発しようとする企業や大学をサポートして、注意点やノウハウなどをアドバイスします。そしてH-IIAロケットの余剰スペースに衛星を相乗りさせて打ち上げます。これまで10基の小型衛星が宇宙へと飛び立ちましたが、この活動は宇宙開発に関心がある学生を対象とした人材育成や、将来宇宙産業に参入したいと考えている企業の育成にも貢献しています。
日本のロケットや衛星などの宇宙技術は、半世紀にわたる研究開発により、いまや世界のトップレベルにまでなりました。これだけの技術力を持っているのは、世界の国の中でも一握りです。この国家的資産をさらに高め、持続的に発展していくためには、国内の宇宙開発を推進すると共に日本の宇宙産業が海外でビジネスチャンスを拡大していくことが重要であると思います。また、宇宙産業の海外展開が成功していけば、国内経済の活性化にも貢献できます。JAXAは、これまでの研究開発に加えて、日本の宇宙産業とともに発展し、国民生活と世界への貢献に寄与する新しい展開を模索していきたいと考えています。
小澤秀司(こざわひでし)
JAXA理事(経営企画、産業連携等担当)
1971年、京都大学工学部電気工学第二学科卒業後、旧宇宙開発事業団(NASDA)に入社。その後、衛星の追跡管制システムの開発や国際宇宙ステーション「きぼう」日本実験棟の運用システムの開発に従事。1996年から1999年にかけNASDAワシントンDC事務所長として米国に駐在。帰国後は「きぼう」日本実験棟プログラムマネージャーやNASDA企画部長を経て、2003年のJAXA発足と同時にJAXA経営企画部長に就任。2005年10月からJAXA執行役として衛星の利用を統括。2008年より現職。