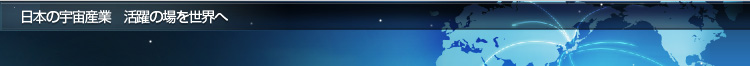Q. 小惑星探査機「はやぶさ」で実証されたイオンエンジンの海外展開にも力を入れていると聞きました。

小惑星探査機「はやぶさ」に搭載された4台のイオンエンジン

「いぶき」の温室効果ガス観測センサ(TANSO-FTS)
イオンエンジンは燃費が良いのが利点で、衛星に搭載する燃料が少なくてすみます。衛星が軽くなるため打ち上げに大きなロケットを必要とせず、価格的なメリットもあります。「はやぶさ」で実証されたイオンエンジンの技術は、海外から高い関心が寄せられています。今後はまずアメリカ市場に参入し、そこで実績を積んだ後にヨーロッパを含めた海外市場に打って出たいと考えています。
2011年4月にはJAXAの産業連携センターの方にも同行いただき、アメリカで、NASAや人工衛星製造メーカー等の関係者立ち会いのもと、イオンエンジンの動作試験を実施しました。この試験は成功し、アメリカのお客様からも好評でしたので、早く具体的なプロジェクトとして受注したいと思っています。 Q. JAXAのプロジェクトで培った技術を海外に販売していくというモデルは、今後も考えられると思いますか? 十分に可能性があると思います。ただ、宇宙で実利用した実績がなければ、海外市場ではなかなか認めてもらえません。日本は実用衛星の経験を積む場が少なく、研究開発の衛星が中心です。宇宙基本法ではそれを実利用目的の衛星へ変えようということなのだと思います。
JAXAとのプロジェクトでは、新しい技術がたくさん生まれていますし、最高峰のものを作ったという実績は強みになります。こうした技術を研究開発で終わらせることなく、世界標準にするなどグローバルに利用できるよう発展させていく必要があると思います。「はやぶさ」のイオンエンジンの改良研究では、まさにそれをJAXAにやってもらっています。
そのほか発展性のある技術は、例えば2009年に打ち上げられた温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」に搭載された、地球上の温室効果ガスを宇宙空間から測定するセンサです。温室効果ガスを定量化できるこのセンサ技術で、温室効果ガスの排出権取引に貢献できるのではないかと考えています。また、2011年度に打ち上げが予定されている第一期水循環変動観測衛星(GCOM-W1)にも同じことが言えます。GCOM-W1には、水の循環を地球規模でモニターする観測機器が搭載されていますが、これは気象予測、災害予測という意味で、今後の利用が促進されると思います。
JAXAの研究開発により、世界的にも新しい技術を持った人工衛星や惑星探査機を世に送り出してきました。それらの技術をどう世界にアピールしていくかがとても重要だと思います。またそれは欧米の主要衛星メーカーとの差別化につながるのではと考えます。
Q. 海外展開における今後の展望をお聞かせください。

まずは「ASNARO」と小型科学衛星1号機を成功させて、標準衛星バスシステム「NEXTAR」の軌道上での実績を作りたいです。そして、その先にある「ASNARO-2」や小型科学衛星2号機につなげ、国際競争力を高めたいと思います。「ASNARO-2」は、マイクロ波を使って地表の画像を撮るレーダー衛星が検討されていますが、もしこれが実現すれば、雲があっても常に地表を観測できますので、雨が多いアジアや南米の宇宙新興国にとって魅力あるラインナップになると思います。 Q. JAXAに期待することは何でしょうか? 高い機能と同時に、高い信頼性が求められる宇宙開発では、何を新しくして何をそのまま継続すべきか、その見極めも大変重要です。JAXAとはこれまで最先端の新規技術に注力して開発を進めてきましたが、これからは低コストで作るという観点で開発の工夫を行うといった取り組みについてもJAXAと共同でやっていければと思っています。
衛星ビジネスを海外で展開するためには、低コストかつ短期間で開発・打ち上げができる衛星が必要です。そのため、衛星バスのように共通する部分をできるだけ増やしたいと考えています。研究開発の要素として、オリジナルでカスタマイズする部分はもちろん必要ですが、それ以外の部分は、例えば3年間は仕様を変えないといった開発もあり得るのではないかと思います。
日本電気株式会社(NEC) 執行役員常務
1979年、日本電気株式会社(NEC)に入社。同年、電波応用事業部光電技術部に配属。2004年、誘導光電事業部長。2008年、執行役員(兼)航空宇宙・防衛事業本部長。2010年より現職。