コロンビア号(1994年7月9日〜23日)

アジア初の女性宇宙飛行士の誕生。国際宇宙実験計画「第2次国際微小重力実験室」に参加。日本の実験で話題を集めたものの1つがメダカやイモリなど水棲生物の実験で、宇宙環境が生物にどのような影響を与えるかを調べた。メダカの実験では宇宙での交尾、産卵のようすを観察し、8匹の「宇宙のメダカ」が生まれた。このメダカの子孫は研究に使われるほか、希望のあった小中学校に譲られるなど、現在さまざまなところで飼育されている。
エンデバー号(1996年1月11日〜20日)

日本人初のミッションスペシャリストとして搭乗した若田宇宙飛行士は、スペースシャトルのロボットアームを使った、宇宙実験・観測フリーフライヤ(SFU)の回収に成功。またロボットアームを操作して、国際宇宙ステーション(ISS)の建設に向けた船外活動関連の試験をサポートした。
コロンビア号(1997年11月20日〜12月5日)

土井宇宙飛行士は日本人として初めて船外活動を行い、ISSの建設に用いる組み立て機器の機能や操作性の検証試験を行った。また、当初予定されていなかったスパルタン衛星(太陽コロナ観測衛星)を手で回収する難しい作業を、スコット宇宙飛行士とともに成功させた。
ディスカバリー号(1998年10月30日〜11月8日)

生命科学および宇宙医学の分野の実験を実施。向井宇宙飛行士は植物実験のほか、宇宙環境が人体に及ぼす影響を調べるため、自ら被験者となって睡眠中の脳波など医学データを取得した。また医師としての経験を生かし、77歳という宇宙飛行士史上最高齢でミッションに参加したジョン・グレン宇宙飛行士の健康管理をサポートした。
エンデバー号(2000年2月12日〜23日)

地球観測を目的としたミッション。地球表面の詳しい立体地形図を作るため、スペースシャトル本体に取り付けられたアンテナと、スペースシャトルから伸ばした船外アンテナで地表データを取得。毛利宇宙飛行士は高精細テレビ(HDTV)カメラによる地球の撮影も行った。
ディスカバリー号(2000年10月12日〜25日)

若田宇宙飛行士は日本人として初めてISSの組み立てに参加。スペースシャトルのロボットアームを操作して、部品の取り付けや船外活動を支援した。若田宇宙飛行士はロボットアームにクルーを乗せて船外の作業場へ正確に移動するなど、その操作技術はNASAからも高く評価された。
ディスカバリー号(2005年7月26日〜8月9日)

コロンビア号の事故以来、約2年半ぶりに飛行が再開されたミッション。ISSの姿勢をコントロールしている装置の交換や部品の組み立てを行った。野口宇宙飛行士は3回の船外活動の主担当を務め、合計約20時間に及ぶ船外活動を行った。
エンデバー号(2008年3月11日〜27日)

「きぼう」日本実験棟の第1回の組み立てフライトで、船内保管室が打ち上げられた。土井宇宙飛行士はスペースシャトルのロボットアームを操作して、船内保管室の取り付けや整備を行い、日本初の有人宇宙施設に乗り込んだ初めての日本人となった。
ディスカバリー号(2008年6月1日〜15日)

「きぼう」日本実験棟の第2回の組み立てフライトで、船内実験室とロボットアームの取り付けを行った。星出宇宙飛行士はISSのロボットアームを操作し、「きぼう」に関わる作業全般を担当。「きぼう」の中心部が完成し、本格的に実験運用を開始するための基盤が整った。
ディスカバリー号(2009年3月16日〜29日)

若田宇宙飛行士が日本人初の宇宙長期滞在に向けて出発したミッション。若田宇宙飛行士はそのままISSにとどまり、日本人初の宇宙長期滞在を開始した。ISSの最後の太陽電池パドルが打ち上げられ、クルー6人体制に必要な電力の供給が可能になった。若田宇宙飛行士はISSのロボットアームを操作してISSの組み立てを支援するほか、長期滞在中に行う実験に向けた準備などを行った。
エンデバー号(2009年7月16日〜31日)
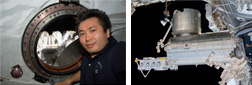
「きぼう」日本実験棟の第3回の組み立てフライト。若田宇宙飛行士によるロボットアーム操作により、船外実験プラットホームと船外パレットが取り付けられ、「きぼう」が完成した。若田宇宙飛行士は約4ヵ月のISS長期滞在を終えて、このミッションで帰還。
ディスカバリー号(2010年4月5日〜20日)

山崎宇宙飛行士は物資輸送責任者として宇宙実験材料などをISSへ運ぶほか、ロボットアームの操作を担当。2009年12月からすでにISSに長期滞在していた野口宇宙飛行士と合流し、初めて日本人宇宙飛行士2人が同時に宇宙に滞在した。
※ STSとはSpace Transportation Systemの略。
※ 日付表記は日本時間。
(写真提供:NASA/JAXA)

