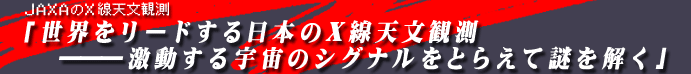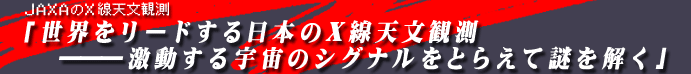|
 |
 |
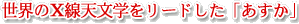 |
 |
 |

日本が1993年に打ち上げた「あすか」は、世界で初めてX線の撮像と分光を同時に行った衛星です。当時世界最高の分光性能を持ち、世界的に遅れていたX線分光学の分野を切り開いたことは大きな成果でした。これを可能にしたのは、日本の独自開発による優れた装置に加え、NASAの支援を得て、アメリカの科学者と密接に協力したことです。
国際協力は装置作りにとどまりません。観測時間を日米それぞれに配分したほか、ヨーロッパにも全体の10%を割り当てるなど、外国の研究者にも開放しました。また、今では観測されたデータの全てが、世界中の研究者の利用のために公開されています。これらの結果、海外の共同研究者が大幅に増え、日本はX線天文学における国際的な研究拠点になっているのです。
「あすか」は、ドイツの「ROSAT」と共に、1990年代のX線天文学を発展させる重責を果たしたと言っても決して過言ではありません。当時、NASAやESAには本格的なX線天文衛星がなく、世界中の研究者が高性能の「あすか」と「ROSAT」を利用したのです。
「あすか」の成果をまとめて話すことはとても困難です。なにしろ3000もの論文が出版されているのですから。あえていくつかあげるとすれば、少々専門的になりますが、
(1)活動銀河核が超大質量ブラックホールである証拠とみられる、広がった鉄輝線の発見
(2)超新星残骸のX線分光による、元素の組成、不均一分布、粒子加速の証拠など
(3)生まれたばかりの原始星からのX線の発見
(4)銀河団の高温プラズマの二温度構造を発見
などでしょう。
現在活躍中の2つの巨大X線天文衛星、NASAの「Chandra」やESAの「XMM-Newton」の中心課題には、「あすか」が開拓したテーマが数多くあることを見ても、「あすか」の果たした重要な役割がよくわかります。
 |
|
 |
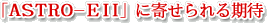 |
 |
 |

 その「Chandra」と「XMM-Newton」と共に、世界の3大X線天文衛星の1つとなる予定だった「ASTRO-E」(2000年)の打ち上げ失敗で残念ながら足踏みしたものの、日本の国際評価が低下したとは感じられません。学問的にも技術的にも、アメリカ、ヨーロッパと並んで世界の三頂点という認識は依然として変わっていないのです。 その「Chandra」と「XMM-Newton」と共に、世界の3大X線天文衛星の1つとなる予定だった「ASTRO-E」(2000年)の打ち上げ失敗で残念ながら足踏みしたものの、日本の国際評価が低下したとは感じられません。学問的にも技術的にも、アメリカ、ヨーロッパと並んで世界の三頂点という認識は依然として変わっていないのです。
今回の「ASTRO-EII」は、高解像力をもつ「Chandra」や大口径の「XMM-Newton」という巨大X線衛星に比べれば小型ですが、その2機に勝るとも劣らない極めてユニークな特徴を持った衛星です。それはこれらの巨大衛星にない、超精密X線分光ができることです。これは「あすか」の目指した進路の発展形でもあり、日米協力によって世界で初めて実現するものなのです。
世界中の研究者は「ASTRO-EII」の超精密X線分光のデータを待ち望んでいます。それは「Chandra」や「XMM-Newton」の結果を物理的に解明するのに、是非とも必要だからです。また「ASTRO-EII」にはこれまでで最高感度の高エネルギーX線検出器も搭載されています。「ASTRO -E」の失敗からわずか5年で「ASTRO-EII」が打ち上げ可能になったことは、1979年の「CORSA-b」=「はくちょう」の復活を思い出させます。「ASTRO-EII」は、必ずや世界のX線天文学の新たな1ページを開くものと大いに期待しています。
 |
|
 |
 |
 |
|
 |