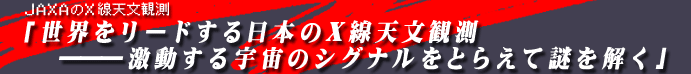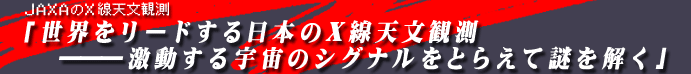|


 |
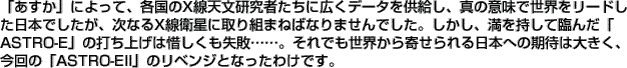 |
 |
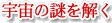 |
 |
 |

世界初の観測機器をもって“世界の天文台”となる
「ASTRO-EII」は、日本のX線天文衛星としては5代目にあたります。ところが、周知のように、当初は2000年2月に「ASTRO-E」として打ち上げられたものの軌道投入を断念しており、今回の衛星は再挑戦“リベンジ”機となります。
ASTRO-E打ち上げの年は、それまで沈黙を守っていたアメリカ、ヨーロッパが相次いで高性能の新衛星を打ち上げた直後のことでもあり(1999年、チャンドラ、ニュートンを投入=後述)、これら2機と並ぶ2000年代の“3大X線衛星”として大きな期待が寄せられていました。にもかかわらず、打ち上げに失敗してしまったのは、日本初のX線天文衛星となるはずだった「CORSA」と同様、因縁さえ感じられますが、2台目のASTRO-Eである「ASTRO-EII」は、5年遅れても“大変重要なミッション”だという世界的な共通認識のもと、再挑戦にこぎつけられたプロジェクトだったのです。
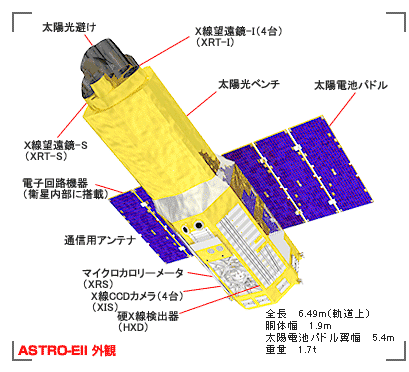 それは、日本が「あすか」で築いた実績に対する、信頼と期待だったのかもしれません。 それは、日本が「あすか」で築いた実績に対する、信頼と期待だったのかもしれません。
ASTRO-EIIがどのような力を持ち、どのようなことを解明してくれるのか――JAXA宇宙科学研究本部でASTRO-EIIに携わる高橋忠幸教授は、「ASTRO-EIIの目的は“宇宙の謎を解く”こと。それには2つの柱があります。今まで誰も持ったことのない観測装置を使って、誰も見たことのないものを見るということが第一。そして、それが世界の天文台として機能するということが2番目です」と語ります。
ASTRO-EIIには、高い分光能力を持ち、低エネルギーの軟X線から高エネルギーの硬X線、ガンマ線まで精密に分析できる数々の観測装置が搭載されています。これによって、衝突や合体を繰り返す“銀河団”や、大きな重い星が爆発した後にできる“ブラックホール”に代表される宇宙の高エネルギー活動の解明を目指しています。
そして、このASTRO-EIIの利用は日本だけにとどまりません。打ち上げ後は“軌道上天文台”として、世界各国に利用してもらうという構想があるのです。打ち上げ前から“国際公募”を行っており、すでに世界中から観測申し込みが続々と寄せられ、競争率もかなりに上がっています。
こうした“国際協調”路線は、先代の「あすか」で敷かれたもの。今回のASTRO-EIIプロジェクトも“日米協力”のもとに進められています。
 |
|
 |
 |

|
 |
| |