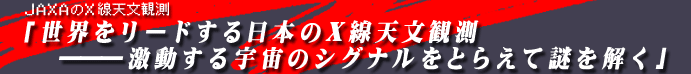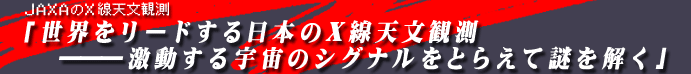|
 |

X線天文学の歴史は1962年、リカルド・ジャッコーニ(2002年ノーベル物理学賞受賞)らが観測ロケットを使って予想外のX線星を発見したことに始まります。その翌年には、故・小田稔先生が、X線星発見者の一人、ロッシ教授からマサチューセッツ工科大学(MIT)に招かれ、そこで有名な「すだれコリメータ」を開発されました。続いて私もオランダのライデン大学で、気球を使ってX線の観測を始めました。小田先生は、1966年に帰国され、東京大学宇宙航空研究所にX線天文グループを新設されます。そして、既に日本のロケットでX線観測を始めていた名古屋大学の早川幸男先生のグループと共に、日本のX線天文学研究の基盤を確立したのです。翌年、私も名古屋大学に帰任しました。この草創期に、小田先生、早川先生という偉大なリーダーがおられたことは誠に幸運でした。当時はロケット観測しかできませんでしたが、自力で観測装置の開発を進め、精力的に観測を行いました。このように、日本のX線天文学への取り組みは、世界的に見ても早かったのです。
1970年、ジャッコーニの主導で世界初のX線天文衛星「ウフル」が打ち上げられました。その年、日本も初の人工衛星「おおすみ」(世界で4カ国目)の打ち上げに成功し、自力で科学衛星を打ち上げる能力を持つに至ったのです。その直後から日本でも小田先生が中心になって、X線天文衛星「CORSA」の準備が着々と進められました。
「ウフル」打ち上げから6年後の1976年、日本で初めてのX線天文衛星「CORSA」が打ち上げられたのですが、残念ながらロケット制御の不調で失敗に終わります。しかし、小田先生の奮闘と、研究者、技術者一体になった懸命の努力の結果、わずか3年後の1979年、「CORSA-b」の打ち上げに成功したのです。これが日本で初めてのX線天文衛星「はくちょう」です。「ウフル」に遅れること9年ですが、日本は米英に次いで世界で3番目のX線天文衛星保有国となりました。小田先生の「すだれコリメーター」を載せた「はくちょう」は、当時発見されたばかりのX線バースト源を次々と見つけるなど、中性子星の研究で目覚しい成果をあげました。「はくちょう」の成功は、日本のX線天文グループが世界のトップに追いつく大きなステップとなったのです。
 |
 |

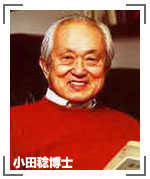
 |
|