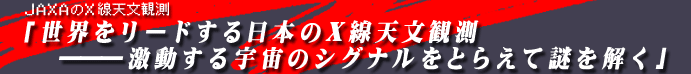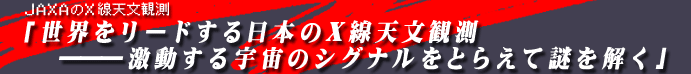|
 |
 |
 |
 |
 |

天体の色の分解能を高めて、ダイナミックな宇宙を知る
「ASTRO-EII」に搭載されている観測機器について、見てみましょう。
X線望遠鏡は口径40cmのものが5基、搭載されています。そのうち4基に“X線CCDカメラ”が装着され、色鮮やかな撮像を可能にします。残る1基にはX線天体のスペクトル(波長と光の強さの関係を示すもの)を高い精度で観測する“X線分光検出器”が装着されています。他にも、硬X線検出器が1台搭載されています。
「ASTRO-EIIの強みは、硬X線の検出器も含めて広い波長域をカバーできること。それは他の衛星にはない大きな特徴です」と語るのは、日本の天文学(X線が専門)の第一人者、國枝秀世教授(名古屋大学大学院理学研究科)です。
「もう一つの大きな特徴が、マイクロカロリーメータ。これが一番の目玉と言ってもいいかもしれません」
マイクロカロリーメータとは、X線による温度上昇を検出する微少熱量計のこと。これは「機器の心臓部はアメリカ製です。日本は外側を冷やして寿命を延ばす技術などを提供しています」と言うように、日米協力のたまものでもあります。
しかし、何と言っても、ASTRO-EIIの強みは「高い分光能力」。分光能力が大きなカギとなる理由について、國枝教授は、「日本の衛星は欧米に比べて小さい。さらには、重くて高性能の望遠鏡を作る技術もない。それならば、軽くても精度の高い分光器を作って、スペクトルを詳しく調べようとなったのです。どんな天体なのかを調べるには、スペクトルはとてもいい情報を含んでいるのです。ASTRO-EIIとしては、波長分解能を今までより高めて、天体のダイナミクス、運動学を見ることが大きなポイントとなります。ブラックホールの周囲の運動や時空の構造を解明することが、ASTRO-EIIの大きなテーマですから」と語ります。
実現に時間がかかっても、大きな飛躍を狙うのが“欧米流”、それに対して、継続的にアプローチし、規模は小さくても世界初を狙うのが“日本流”だといわれます。「小さなえさで大物を釣り上げる」――ASTRO-EIIの観測機器は、まさに日本X線天文の面目躍如といえるでしょう。
 |
|
 |
 |
  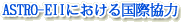
 |

國枝秀世(名古屋大学大学院理学研究科教授)
ASTRO-EIIプロジェクトのキーワードの一つが「国際協力」です。このミッションを成功させるためだけではなく、今後、世界のX線天文を占う上でも非常に重要なキーワードといえるでしょう。
ASTRO-EIIにおける国際協力を象徴しているのが、第一に「日米協力によるコラボレーション」です。検出器、望遠鏡の組み立てから試験・データ解析まで、日米が協力し合って実現させてきたのです。そして、代表的なコラボレーションが「マイクロカロリーメータ」です。この機器の心臓部はアメリカ製ですが、それを低温に長時間保つ“魔法瓶”である冷却機は日本が開発しています。
もう一つ、国際協力の象徴が「サイエンスワーキンググループ」です。技術に関しては、アメリカから相当な人材が送り込まれましたが、さらにアメリカ、ヨーロッパから各5人の“サイエンスアドバイザー”を招き入れて「サイエンスワーキンググループ」(日本風に言うと、科学観測委員会でしょうか)を作っています。
これは、ミッションの最適設計を考える目的から、「どういう衛星を作るか」「どこにポイントを置くか」、サイエンスの立場からアドバイスをもらい、衛星の設計に反映させてきたものです。この委員会には、開発状況の報告や問題点が逐一報告され、その報告を元に「どういう観測をするか」といった相談も行われています。
サイエンスワーキンググループは、「ASTRO-E」、さらには「あすか」の頃から始まっていた試みです。日本の衛星が取得したデータは当然、全世界に供給するべきものですから、インターナショナルで進めるのは当たり前という時代になっているのです。
 |
|
|
 |
 |
 |
|
 |