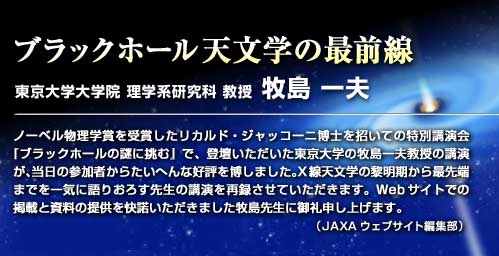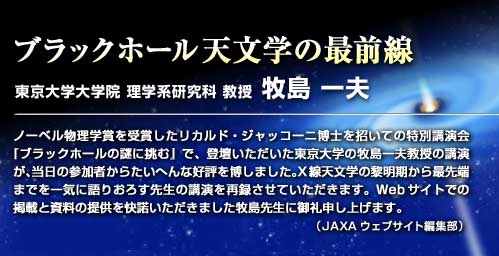牧島一夫略歴(まきしま・かずお)
東京大学大学院 理学系研究科 教授
1949年生まれ
理学博士(東京大学) 専門:宇宙物理学(X線天文学)
宇宙からのX線・ガンマ線や粒子線を観測手段に、太陽から宇宙の果てまでの高エネルギー物理現象を研究している。現在、理化学研究所の宇宙放射線研究室主任研究員も併任している。

「ブラックホール」という概念がはじめて歴史に登場したのは、ちょうど1世紀前の1905年、天才・アインシュタインが相対性理論を提唱したことに始まります。この理論 の中心には「アインシュタイン方程式」という式がありました。方程式といえば中学時代に教わった、「ax2+bx+c=0を満たすxの値を求めなさい」という2次方程式を思い浮かべると良いでしょう。アインシュタイン方程式は、それよりずっと難しいですが、本質は同じものです。
その方程式を解くことにいろいろな人が挑戦し、ドイツのシュヴァルツシルドという数学の得意な天文学者が、答えのひとつを見つけることに成功しました。その答えは、重たい物質がひじょうに小さくなって、ほぼ一点に集まったとき、そのまわりで重力がどうなるかを示しており、その中に「ブラックホール」の概念が入っていたのです。ただしそれは、とても不思議な性質をもっていましたので、皆はこれを「数式の上だけの、空想の話であろう」と思っていました。
ところが1938年ごろになると「星の進化の理論」がだんだん整ってきました。その中で例えばオッペンハイマーという人が、「重い星のなれの果てとして、シュヴァルツシルドが見つけたような状態が実現するのではないか」と言い出しました。そして、そのような重たい星の最期の状態に、ジョン・ホイーラーという人が初めて「ブラックホール(黒い穴)」という呼び名を使ったそうです。1967年のことでした。
|