ではその「ブラックホール」とはいったいどういう状態を意味するのか、ごく簡単な思考実験をしてみましょう。まず、地球の周りをまわる人工衛星を考えてみます。私たちが日々お世話になっている気象衛星や通信・放送衛星などの静止衛星は、地上から3万6000km上空にあり、秒速およそ3.3 kmで飛んでいます。1周24時間で、地球の自転と同期して回っているので、地上から見ると、静止しているように見えるわけです。もっと低いところを飛ぶ人工衛星もありますが、軌道が低いほど、地球の重力に引かれて落ちないよう速く回らないといけません。空気の抵抗がないと仮定して、地表すれすれを飛ぶときの衛星の速度は、およそ秒速7.9 kmで、これが「第1宇宙速度」といわれるものです。 次に地球の半径を4分の1に縮めてみて、その表面すれすれを周回する人工衛星を考えてみます。重力が強くなりますので、落ちずに回るためには、さきほどより速い、秒速16 kmの速度が必要になります。地球をもっと小さくすれば、必要な速度はもっと大きくなるはずで、それをグラフにしたものが、この図です。横軸は、仮想的に縮めた地球の半径で、10分の1になるごとに一つ目盛りが刻まれた、対数目盛になっています。 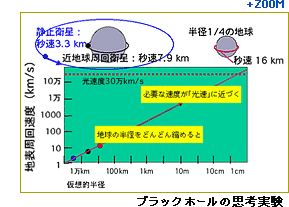 この図でわかるように、地球を縮めてゆくにつれ、衛星の周回速度はどんどん速くなり、あるところで「光の速度」に達してしまいます。しかし、どんな物体でも、光の速度より速く動くことはできないので、衛星は回り続けることができず、落下してしまいます。すなわち、天体を「ある半径」より小さく縮めると、その表面での周回速度が光の速度に達し、その内側からは、どんな物体も逃げ出せなくなるし、光さえも逃げ出せない……。これが、シュワルツシルドが数学的に発見した、ブラックホールの概念なのです。 この図でわかるように、地球を縮めてゆくにつれ、衛星の周回速度はどんどん速くなり、あるところで「光の速度」に達してしまいます。しかし、どんな物体でも、光の速度より速く動くことはできないので、衛星は回り続けることができず、落下してしまいます。すなわち、天体を「ある半径」より小さく縮めると、その表面での周回速度が光の速度に達し、その内側からは、どんな物体も逃げ出せなくなるし、光さえも逃げ出せない……。これが、シュワルツシルドが数学的に発見した、ブラックホールの概念なのです。では、物体をどこまで縮めるとブラックホールになるかというと、その「限界となる半径」は、天体の質量に比例しています。たとえば地球を半径5 mm以下に縮めたり、太陽を半径3 kmより小さくできれば、どちらもブラックホールになります。 1960年代になると、重い星がどのようにしてブラックホールになるのか、だいたいの様子が分かってきました。青年期の星は水素が多く、中心部分では核融合でヘリウムが作られています。しかし中心部で水素を使い果たしてしまうと、中心部分が重力でどんどん収縮し、その反動で外層が膨れあがって、「赤色巨星」となります。それが極限に達すると、ついに超新星爆発が起こります。そのとき、星の中心部分は重力でつぶれ、ニュートリノが放出され、外層は吹き飛びます。もとの星があまり重くなければ、つぶれた中心部は中性子星となり、十分に重いと、ブラックホールが作られます。  ブラックホールができた場合は、つぶれた星の中心部は、先ほど述べた「限界となる半径」の中にすっぽり収まってしまいます。この半径のことを、専門的には「事象の地平線」と呼びます。事象の地平線の少し外側から外向きに出た光は、なんとか曲がりながらも逃げ出すことができますが、地平線の内側から出た光は、すべて中心に向かって進むことになり、永久に外に出てこられません。 ブラックホールができた場合は、つぶれた星の中心部は、先ほど述べた「限界となる半径」の中にすっぽり収まってしまいます。この半径のことを、専門的には「事象の地平線」と呼びます。事象の地平線の少し外側から外向きに出た光は、なんとか曲がりながらも逃げ出すことができますが、地平線の内側から出た光は、すべて中心に向かって進むことになり、永久に外に出てこられません。つまり「事象の地平線」は、我々の世界と、あちらの世界を分ける境界のようなものです。つぶれた星と、この境界という、二つの概念をあわせたものが「ブラックホール」なのです。 |
||||||
|
||||||