 |
 |
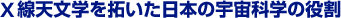
これまで宇宙X線の研究では、多くの国の研究者が、さまざまな貢献をしてきました。中でも日本は、ジャッコーニ先生のお話にもありましたように、大きな役割を果たしてきたと思います。敗戦により日本は飛行機の研究を禁止されましたが、それが解除になった1950年代、糸川英夫先生が東京大学で「ペンシルロケット」という小さなロケットを用い、ゼロからロケットの開発を始められました。それが次第に発展し、1970年には鹿児島・大隈半島にある内之浦町から、日本初の人工衛星「おおすみ」が宇宙に飛び立ったのです。
宇宙X線の観測では、1979年の「はくちょう」を手始めに、「てんま」(1983)、「ぎんが」(1987)、「あすか」(1993)という衛星が、次々と打ち上げられました。特に私たちの誇りとするところは、1世代ごとに検出感度がどんどん上がっていることです。「はくちょう」の感度を1とすると、「てんま」はその10倍、「ぎんが」は200倍、そして「あすか」は5000倍にも達します。
こうしてX線観測が進むにつれ、「はくちょう座X-1」と同じようなブラックホール連星が、現在までに20〜30個ほど、我々の銀河系の中に発見されてきました。そのうち多くのものは、ふだんはまったくX線を出さず、ときおり相手の星からガスが降り積もって突然、X線で明るく輝くという天体、すなわち「X線新星」です。しかし現在でも、「はくちょう座X-1」がブラックホールの王者であることは変りません。じっさいX線新星の中には、ブラックホールではなく中性子星を含むものもあり、X線の性質が「はくちょう座X-1」の性質に似ているかどうかが、その区別の決め手に使われることが多いのです。
もちろん、星と連星を形成していない単独のブラックホールも、数多いと思われます。しかし、ブラックホールはガスを飲み込んでX線を放射しないと、一般にはその存在に気づかれません。連星をなしていれば、相手の星から大量のガスが供給されるため、ブラックホールは強いX線を出すことができ、自分の存在を周囲に知らせることができるわけです。
|
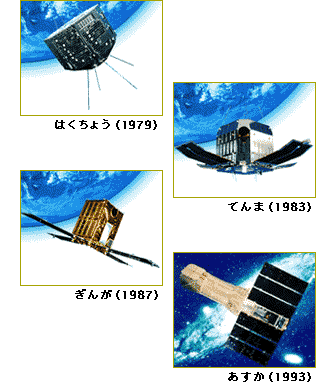 |
|
 |
 |