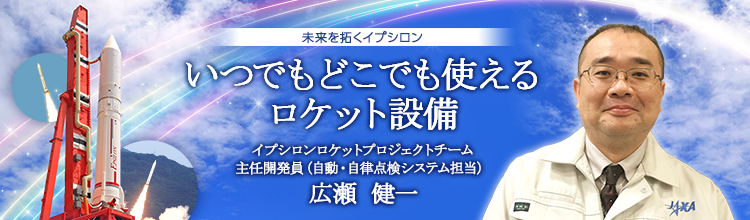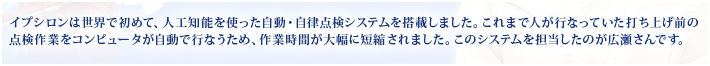
──イプシロンの自律・自動点検システムとはどのようなものでしょうか?
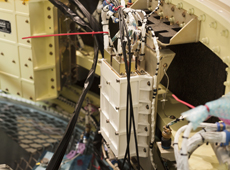
イプシロンに搭載された人工知能「ROSE」(提供:JAXA/JOE NISHIZAWA)
ロケット本体に搭載した計算機「OBC」と人工知能を使った自動・自律点検システム「ROSE」、イプシロン管制センターに設置された、ロケットの点検・打ち上げを遠隔で操作する装置「LCS」を連携させ、ロケットの点検を効率化します。機体から送られてくる機体の情報を地上のパソコンで見て、異常なデータとなっていれば検知するわけですが、それをパソコン2台でできるということで「モバイル管制」とも言われています。これまで複数の装置、人間が行なっていた点検をROSE、LCSが行うことで、少人数かつ短時間での作業を実現しました。
これまでは、機体の搭載機器ごとに地上設備がありましたが、ROSEが各機器からのデータを集めて地上設備に送ります。そして、そのデータをJAXAの事業所やメーカに伝送することができます。例えば、機体製造を担当するIHIエアロスペースは、自社の工場でそのデータを見て、機体に不具合の兆候がないかどうかを技術評価します。これまでは、技術評価する人たちも内之浦に来ていましたが、ネットワーク化されたことで遠く離れていても作業できるようになりました。
──このシステムによって、どれくらい作業時間が短縮されたのでしょうか?
このシステムの工夫だけではないですが、1段ロケットを射場に設置してから発射まで、42日間かかっていたのを7日に短縮することができ、また、打ち上げの3時間前まで衛星の作業を行うことが可能になりました。ロケットを発射台に設置した後、電気系の点検を行いますが、点検用のケーブルを取り付けるなど手間が多く、従来はその点検にたくさんの時間を割いていました。また、衛星の最終アクセスは、これまでは打ち上げの9時間前まででした。衛星からは、ロケットに搭載した後も、最終準備や点検を打ち上げぎりぎりまで行いたいという要望があり、それに十分応えることができたと思います。
──苦労したのはどのようなことでしょうか?

イプシロン管制センターの外観
機体からデータを送り、それを地上で受け取ってから何秒後に評価をするといったタイミングの設定が難しかったです。それぞれの搭載機器によって特性があり、一概に何秒後に評価するとはできず、それぞれ細かく設定する必要がありました。少しでもそのタイミングがずれるとエラー判定され、その後の作業はすべて自動停止します。最初のうちはエラーの連続で、その度に手順を組み替え、試行錯誤しながら進めました。
──そのタイミングの誤差で、打ち上げが延期された時のお気持ちは?

イプシロン管制センターの内部
機体にコマンド送って返ってくるまでの時間差、0.07秒を考慮せずに判定してしまったのが、打ち上げ中止の原因です。打ち上げの19秒前に自動停止してしまいましたが、それはシステムが不具合を事前に検知したこと、つまり、正常に動いていたことを意味します。ですから、システム異常で失敗したとマスコミに言われた時は、とても複雑な心境になりました。
──打ち上げが成功した時はいかがでしたか?
打ち上げが延期になった後、作業に問題がないかを調べる調査チームが組まれ、内之浦で徹底的な総点検が行われました。その作業が結構大変でしたので、打ち上げを見た時は素直に感動する部分と、自分が関係した設備が無事に機能して「ああ、よかった」と、ほっとする部分がありましたね。
また私は、固体ロケットの打ち上げを見たのは初めてで、射点から2kmほど離れたイプシロン管制センターの中にいました。発射の衝撃が建物にも伝わってきて、まさか体で打ち上げを感じられるとは思っていませんでした。私は以前、H-IIAやH-IIBの射場設備を担当していましたが、種子島宇宙センターの場合は管制室が地下にあるので、打ち上げの衝撃を感じることはありませんでした。機会があればぜひ、建物の外からイプシロンの打ち上げを見てみたいです。
──自動・自律点検システムは今後どう改善されていくのでしょうか?

打ち上げ直前のイプシロン(提供:JAXA/JOE NISHIZAWA)
実のところ、“自動”点検は初号機で実施されましたが、“自律”点検の機能はまだ活用できていません。精度良く、自律的に技術評価するためには、できるだけ多くのデータが必要なのですが、今はその基礎データを蓄積している段階です。現在は、2号機に向けて、これまで集めたデータを基に、正常か異常かを判定する設定値を調整しています。自律点検システムは、データの数が増えるほど精度が上がっていくので、地上試験や打ち上げを重ねなければならないと思っています。
また、システムの使い勝手をもっと良くしたいと思います。例えば、現場ではその場で手順を組み替えなくてはいけないこともあります。その際に、諸々の設定値を変更しなければなりません。その設定変更や確認作業を、もっと臨機応変にできるようにしたいと思います。
──いずれは、携帯でも自動・自律点検の操作をできるようになるのでしょうか?
これはセキュリティー的に難しいと思います。技術的には可能かもしれませんが、一般公衆回線を使うと、外から妨害されるようなことも考えられます。ただ、専用回線を使うなどして、シンプルな設備を目指していきたいとは思っています。
──広瀬さんが理想とする発射管制設備とはどのようなものでしょうか?
どこでも、いつでも使える設備です。自動・自律点検の機能を持つ発射管制設備を1つ作り、それを持ち運ぶことができれば、内之浦でも種子島でもどこでもロケットを打つことができます。
──この仕事のやり甲斐は何だと思いますか?

やはり、打ち上げた瞬間というか成功した時の開放感じゃないでしょうか。打ち上げ前の数ヶ月間は苦労の連続ですが、それを乗り越えられるのは、なんとしても打ち上げを成功させたいという強い思いです。射場にいる誰もがそう思い、一心不乱にその目標に向かってやってきましたので、宇宙に向かって飛び立つロケットの姿を見た時に、張りつめた緊張感から開放されるのです。私はその瞬間がたまらなく好きです。
──子どもたちへのメッセージをぜひお願いします。
これまでの方法にとらわれずに、いろいろな発想をしてほしいと思います。そして、何事も「やればできる」ということを信じてほしいですね。正直にいうと、最初に自動・自律点検の話を聞いたときに、「え、そんなことできるの?」と私は思いました。でもやっていくうちに、できるとかできないではなく、「絶対にやり遂げてやる」という強い気持ちの方が上回ってきたんです。きっと自分の中に何か熱いものがあったのだと思います(笑)。そんなふうに熱くなれるものを1つでも見つけてほしいと思います。
JAXA宇宙輸送ミッション本部 イプシロンロケットプロジェクトチーム 主任開発員
1986年に宇宙開発事業団(現JAXA)に入社し、H-IIロケット、H-IIAおよびH-IIBロケットの射場設備の開発に従事。2011年、イプシロンロケットプロジェクトチームに異動。発射管制設備(LCS)等の射場設備開発を担当。
良いロケットにするには、もっとシンプルに!
未来につながるイプシロンの技術
乗りやすくて優しいロケット、イプシロン
いつでもどこでも使えるロケット設備
多様な要求に応えられるロケットを目指して