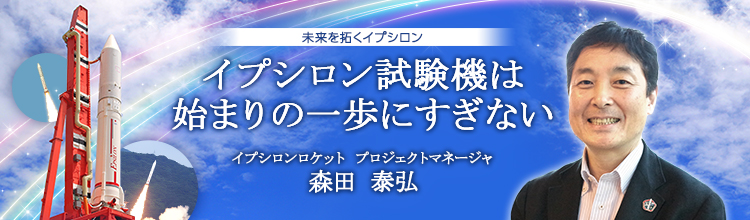──イプシロンは森田先生が目指すロケットになりましたか?

イプシロンロケット試験機打ち上げ
M-Vの開発が中止になった記者会見の時に、私は「M-Vの性能は世界一だが、これからのロケットは性能だけで勝負はできない。もっと簡単に打ち上げるシステムを作らなければならない」と言いました。この方向性を忠実に実行できましたので、最初の一歩として満足できるロケットになったと思います。
──打ち上げが成功した時のお気持ちはいかがでしたか?
チーム一丸となって頑張ってきたので、なんとしても成功させたかったし、成功すると信じていました。だから、人前では自信満々で語っていました。一方で、ほとんど眠れない夜やくじけそうになった時もありましたので、宇宙に向かって飛んでいくイプシロンを見た時は、心からほっとしました。
──打ち上げは2回延期されましたが、その時のお気持ちはいかがでしたか?
イプシロン最大の革新技術は点検の自動化・自律化にあります。「人間の思い至らない部分を機械が見破って大事故を未然に防ぐ」というのが基本コンセプトです。しかし、2回目の延期の直接の原因は、コンピュータ間のやりとりの動作タイミングのずれでした。機械に見破られたのが人間の初歩的なミスだったのがとても残念で、大いに反省しています。でも、開発の過程の試験機ということもあり、打ち上げ前にしっかり見つけることができて良かったというのも本心です。
一方、1回目の延期の原因は製造図面の誤りによるものでした。こういう人間の単純ミスをゼロにするのが理想ですが、万が一あったとしても打ち上げ前に見つけることができるように試験を行っています。今回もこれがよく機能したのですが、今後はもっと時間をかけずにやりたいですね。
──8月27日は夏休み中で、多くの子どもたちが打ち上げ見学に来ていました。それを意識されていましたか?
実は、私たちは管制室の中で作業に集中していましたので、あんなにたくさんの方が見学にいらしてくださっていたとは知りませんでした。後からマスコミの方たちから聞いてビックリしましたね。小惑星探査機「はやぶさ」以来、宇宙というものがみなさんにとって身近になってきたのでしょうか。私は、イプシロンの目的は打ち上げシステムを簡単にすることにより、打ち上げ頻度を高めて宇宙への敷居を下げることだと言ってきました。でも、全国のみなさんの意識は我々の想いを通り越して、すでに宇宙が身近になっているのだなあと感動しました。2回目の打ち上げ延期の後は、批判や心配の声に悩まされることもありましたが、「頑張れ」という声援が、その3倍くらい届きました。みなさんの応援に支えられてイプシロンを打ち上げることができ、心から感謝しています。
──どのようなきっかけでモバイル管制のアイデアが出てきたのでしょうか?

打ち上げリハーサル時の管制室の様子
M-Vロケットの引退時には、パソコンによるモバイル管制という具体的なアイデアがあったわけではありません。ただし、M-Vをやっている頃から、ロケットの運用をもっとシンプルにしない限り、宇宙開発の未来はないという危機感を持っていました。その方策を考える過程で、IT技術の進歩を利用した、モバイル管制というアイデアが出てきたのです。さらに、そのモバイル管制を実現する手段として、人工知能を使った自動・自律点検という考えが生まれました。M-Vはもともと1回あたり約80億円という割高な打ち上げ費用を理由に廃止となりましたので、コスト削減は必須の課題です。モバイル管制をすることにより、ロケットの打ち上げ準備にかかる日数も人数もコストも大幅に少なくなります。
──なぜ今、新しい固体燃料ロケットが必要だったのでしょうか?
いま宇宙開発利用は大きな時代の転換期に差し掛かっています。これからは小型・高性能・低コストという考え方が重要で、打ち上げの頻度を上げてチャンスを増やしていくことが、今後の宇宙科学の進歩と宇宙開発利用の発展のカギを握っています。大型衛星ばかりでなく、小型衛星を活用して効率よく成果を上げていくことが強く求められているのです。固体ロケットは構造も単純なので、このような時代の要請にばっちり応えることができるというわけです。
──固体ロケットは軍事転用できる危険性があるという人もいますが、それについてはどう思いますか?
我々の考え方は、ミサイルというよりもサンダーバードです。あくまで平和利用なんですよね。私たちは科学者ですから、イプシロンが悪用されるなんてことを考えもしないし、そうさせたくもありません。
──最も苦労した点はどこでしょうか?

世界最高の性能を誇ったM-Vロケット
イプシロンの開発が正式に国から認められるまでの研究期間、2006年からの4年間が一番苦しかったですね。パソコン2台でロケットを打ち上げると言い出した時に、一番逆風が強かったのは、実はJAXA内部でした。特に打ち上げ作業の人数を減らすことに対しては、「オレたちの仕事はどうなるんだ?」という空気感みたいなものがありました。「そんなことできっこないからやめておけ」という批判もありました。でも私たちは、こてんぱんに言われても、「未来のロケットを作るんだ」という確固たる信念を貫き通しました。新しいことを始める時に大事なのは、丁寧に説明して少しずつ理解者と応援団を増やしていくことです。よくくじけなかったなあと我ながら思いますね。
イプシロンの性能計算書の表紙には「新燃(しんねん)」と書いてありますが、実はこれはその4年間のことを表しています。苦しかった時期に、恩師で日本の固体ロケットの研究を引っ張ってきた秋葉鐐二郎先生から「宇宙開発に“たら”も“れば”もない、いいロケットを作って未来を拓け」と言われました。それ以来、私たちはM-Vより良いロケットを作るという信念でここまで来られたのです。だから、新しい燃え、「新燃(しんもえ)」と書いて「しんねん」と読みます。
──恩師からの励ましの声は心強いですね。
それはものすごく大きかったです。逆風が吹いてもくじけなかったのは、そういう方たちの励ましのお陰です。秋葉先生からの「頑張れ」という言葉が、どれほど心強かったことか。秋葉先生は日本のロケット開発の父と言われた糸川英夫先生の一番弟子です。私はその秋葉先生の弟子ですから、糸川精神がしっかり内蔵されています。それは、世界に追い付き追い越せではなく、世界の先を行けというチャレンジ精神のことです。そもそも、イプシロンの名前の由来もこうです。Mロケットの「M」を90度傾けると、イプシロンの「E」になります。つまり、Mロケットの精神、言い換えるとペンシル以来の固体ロケットの精神を引き継ぎながら、全く別の次元のロケットになるという意味なのです。モバイル管制のような世界のロケット業界が驚くような革命は、まさに固体ロケットの遺伝子そのものです。
──イプシロン成功の秘訣は何だったと思いますか?
H-IIAを開発した旧NASDA方式とM-Vを開発した宇宙研方式が、うまく組み合わされたことがひとつだと思います。宇宙研は研究・教育機関なので、柔軟な発想力を持ち、新しいことに挑戦しやすい環境があります。むしろ新しいことをやらない限り存在意義がない。一方、旧NASDAは、目標を決めたら必要な作業へ落とし込み、それを適切な人に振り分けて実現していくことにかけては天才的です。こうした両方のいいところが融合されて、イプシロンの開発が成功したのではないでしょうか。これは私の正直な気持ちです。
そういう意味では、M-Vの廃止は新しい時代を切り拓くための産みの苦しみとも言えます。M-Vはとても偉大なロケットだったので、それを一掃するような技術改革はなかなかできなかったと思うからです。M-Vが廃止になった時は悔しかったけれど、みんなで頑張って見事にピンチをチャンスに変えましたね。2003年にJAXAが発足してから10年経った節目の年に、イプシロンが飛んだというのはなにか意味がありそうです。
──イプシロンは今後どう進化していくのでしょうか?

イプシロンロケット試験機
イプシロン試験機は、ロケット改革の第一歩にすぎません。私たちの最終目標は、飛行機と同じくらい身近に宇宙ロケットを打ち上げられる世界です。特殊な打ち上げ設備が必要なくなればいいなと思っています。そのような世界の実現に向けて、イプシロン試験機では、打ち上げシステムを改革し、管制室をパソコン2台にしてしまいました。次は、ロケットを打ち上げてからの追跡管制を改革したいと思っています。例えば、ロケットを追尾する大型アンテナがいらなくなれば、テレビの中継車くらいの簡単な設備で打ち上げが可能となります。まさに射場全体がモバイルになって、世界中のどこからでも打てるというイメージです。これを、次の世代のイプシロンで実現したいと思っています。
──どこからでもロケットを打てるようにしたいのですか?
どこでも打てるくらいロケットの打ち上げ方が簡単になると、本当にどこからでも打ってしまうのではないかと誤解されますが、決してそういう意味ではありません。なぜなら、ロケットには発射台が必要であり、それはどこにでも設置できるものではないからです。現時点では、東京には置けそうもないですよね。それに、単に発射場があればいいというわけでなく、地元のみなさんの理解と応援が一番大切なんです。
イプシロン初号機が成功したのも、射場がある内之浦のみなさんの応援のお陰です。私たちがどんなに夜遅く帰ってきても、温かい食事とお風呂を用意して、とびきりの笑顔で待っていてくださる。そういう優しい気持ちにとても癒やされました。それを考えると、内之浦以外の場所で打ちたいとは思いません。どこからでも打てるくらい簡単な設備にしたいというのがポイントです。
──車の自動運転機能がありますが、ロケットの飛行も人工知能で制御されるようになるのでしょうか?
それも視野に入れています。現在でも、すでに誘導制御は自動になっていますが、将来的には、飛行安全システムも自動化したいと考えています。これは、ロケットに異常があった場合には自爆するというシステムで、今は人が判断するようになっています。人が行うためには、地上に高性能のレーダーやコンピュータが必要です。ロケット自らが飛行の状態を監視できるようになれば、それらの地上設備はいらなくなり、宇宙への敷居はますます下がるでしょう。このような大きな改革は、今すぐ実現するのは難しいかもしれませんが、「未来をこうしたい」という目標を持つことが大切です。
──コンピュータ同士のコミュニケーションと、人間同士のコミュニケーションを、今後どう使い分けていくのでしょうか?
当然、人間が得意な部分もありますから、無人で打ち上げるわけではありません。人がやった方が良い部分と、機械がやった方が良い部分は異なるのです。例えば速さです。今回のイプシロンの自動監視項目は約2,000項目近くありましたが、機械ならたった70秒で点検が終わってしまいます。一方、新しい問題が起きた時にそれを解決する方法を考え出す能力は、今のところ人間の方が上でしょう。ですから、機械と人間の長所を見極めて、そのメリットを生かしてチームとして仕事をしてもらうのが1番だと思います。
──チームを引っ張っていくうえで、心がけていたことはありますか?

モバイル管制という、突拍子もないアイデアを実現させたわけですが、正直に言うと、実現するのは難しいだろうなと思った時期もありました。けれど、皆に話す時には、自信満々に、「これは未来にとって絶対必要なんだ」「頑張ればできるんだ」という2点を必ず強調していました。この言葉には、未来に対する前向きな気持ちと、頑張れば絶対にできるという安心感が含まれていたと思います。
──記者会見の時、先生はいつも笑顔でしたね。先生から笑顔が消えたら……
怖いですね(笑)。8月27日の打ち上げ中止の原因究明の記者会見の時には気をつけていたのですが、やっぱり笑顔が出たようです。あれでも真面目な顔をしていたつもりなのですが、好きな仕事をしていることからくる心の余裕が自然と表れたのでしょう。中止になったからといって、それは決して失敗ではなく成功に至る過程なのだから、次に向かって頑張ればいいという気持ちが強かったです。
──将来の展望をお聞かせください。
何度も言っていますが、ロケットの打ち上げシステムをどんどんシンプルにして、ロケットをもっと気軽に打ち上げられるようにしたい。今の飛行機ぐらいロケットを身近な存在にしたい。そういう世界を作ることが私たちみんなの夢です。これに尽きますね。打ち上げの準備を1週間でできれば、年間50機は打ち上げられることになるでしょう。そのためにもイプシロンロケットをどんどん発展させて、夢のような世界に近づけたいと思っています。
人類の未来に一番大事なのは人の力です。イプシロンのEはEducation(教育)も象徴しています。イプシロンチームには、20代や30代の若い人もいて、彼らが育っているのが本当に頼もしいですね。次回は2015年の2号機で、ジオスペース探査機「ERG」を打ち上げる予定です。彼らがこれからさらにどう成長していくかますます楽しみです。機体も設備も一層成長していきますので期待していてください。イプシロンに夢をのせて、みんなで明るい未来を拓きましょう!
JAXA宇宙科学研究所 宇宙飛翔工学研究系 教授 工学博士
イプシロンロケットプロジェクトチーム プロジェクトマネージャ
東京大学工学部航空学科卒業。同大学院工学系研究科博士課程(航空学専攻)修了。カナダ・ブリティッシュ・コロンビア大学機械工学科客員研究員を経て、1990年にシステム研究系助手として旧文部省宇宙科学研究所(現JAXA)に着任。同年、M-Vロケットの開発がスタートし、主にシステム設計や誘導制御系の研究開発を主導するほか、火星探査機などの展開構造物や、小型月探査モジュールの姿勢制御系の開発にも携わる。2003年、M-Vロケットのプロジェクトマネージャ、2010年よりイプシロンロケットのプロジェクトマネージャとして我が国の固体ロケット開発をリードするとともに、飛翔工学研究系教授として研究教育に携わる。専門はシステムと制御。
良いロケットにするには、もっとシンプルに!
未来につながるイプシロンの技術
乗りやすくて優しいロケット、イプシロン
いつでもどこでも使えるロケット設備
多様な要求に応えられるロケットを目指して