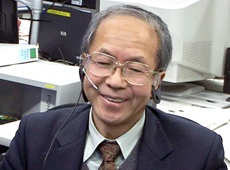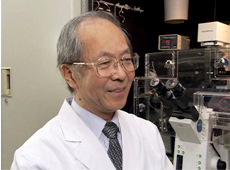Q. 今後どのような生命科学実験を「きぼう」で行いたいですか?

宇宙で実験する予定のメダカと同じ系列のメダカ(提供:東京大学)
別の研究グループでは、水生生物のメダカが、宇宙環境で何世代まで世代交代をするか、その仕組みや、どのような行動をとるか調べてみたいと思います。メダカは、卵から産卵できる成魚になるまで約3ヵ月と期間が短いため、宇宙飛行士の長期滞在中に、親から子、子から孫へ世代交代するのを観察できます。メダカは体の中が透けて見えますので、メダカがどのように泳ぐかということだけでなく、循環器系や心筋がどのように動くかも外から見て分かります。
また、日本人にとってメダカは子どもの頃から馴染みのある生物で、メダカの研究には古い歴史があります。日本の伝統的な生物ともいえるメダカを使って、日本発のオリジナルの研究をぜひ行いたいと思います。メダカは遺伝子ゲノムがすべて解読されていて、人の遺伝子の組成と似ている部分があることが分かっています。ですから、将来、人類が月や火星を目指すとしたら、重要なデータになると思います。
東京大学特任教授 産業技術総合研究所 幹細胞工学研究センター センター長 理学博士
1972年、東京大学理学系大学院博士課程修了(理学博士)。ドイツ・ベルリン自由大学分子生物学研究所研究員、横浜市立大学文理学部教授を経て、1993年に東京大学教養学部教授に就任。1996年、東京大学大学院総合文化研究科・教養学部教授に就任。2003年、東京大学大学院総合文化研究科長・教養学部長。2005年、日本学術会議副会長。2007年〜2008年3月、東京大学理事(副学長)。2006年より産業技術総合研究所(産総研)器官発生工学研究ラボのラボ長、2009年より科学技術振興機構研究開発戦略センターの上席フェローを務め、2010年4月から産総研 幹細胞工学研究センター センター長として現在に至る。1989年に細胞の分化を誘導するタンパク質「アクチビン」を発見。その後、心臓や腎臓など22の臓器を作り出し、再生医療の扉を開く。1990年日本動物学会賞、1994年シーボルト賞(ドイツ政府)、2001年紫綬褒章、日本学士院賞・恩賜賞、2008年エルヴィン・シュタイン賞など数多くの受賞歴があるほか、2008年には文化功労者に選ばれる。専門は発生生物学。