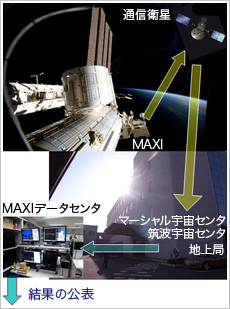Q. MAXIによる観測成果は、今後の宇宙の研究にどのような影響を与えると思いますか?

銀河NGC6240の中心部にある衝突寸前の2つのブラックホール。ハッブル宇宙望遠鏡とX線天文衛星チャンドラの観測データの合成画像(提供:X-ray (NASA/CXC/MIT/C.Canizares, M.Nowak); Optical (NASA/STScI))

ガンマ線バーストの想像図(提供:ESO/A. Roquette)
これまでの全天X線観測に比べ、感度が上がりましたので、電波や光、ガンマ線など異なる波長との同時観測をする機会が増えると思います。変動する天体をさらに深く研究することができ、新しい発見への期待が高まります。また、広い視野で全天を長期にわたって観測しますので、一度に500個ほどの天体を追うことができます。長期間見ていれば、天体変動の新しい局面に遭遇するかもしれませんし、系統的に研究することもできると思います。
例えば、長期観測は活動銀河核の研究にとても有効的だと思います。活動銀河核は非常に大きいブラックホールをその中心にもつ天体で、その振る舞いがよく分かっていません。長期間観測していると、変動の瞬間を捉えることができるかもしれません。また、巨大ブラックホールが合体する様子はすでに観測的にも知られていますが、合体前の兆候を捉えることができたら大発見です。天体が合体するときにはX線を放出しますが、その様子を、合体する前から長期に観測していたら、誰もが成し遂げていない「重力波」の検出にもつながるかもしれません。とにかく、変動の瞬間を捉えることが非常に重要だと思っています。 Q. 先生は今後MAXIでどのような研究を行いたいですか? 激しく変動する天体がどのような理屈で変化させているかを体系化することです。具体例として、宇宙で発生しているいろいろなジェットを、体系的に研究したいと思います。私たちは、コンパス座のX線源である「Cir X-1」を、電波天文学の研究者と共同観測していますが、MAXIでこの天体をずっと見ていたら、小さい爆発によるX線の放射をいくつか検知しました。そして、X線観測でフレアが見つかった時刻に、電波でジェットを観測していることから、これは、小さいジェットであることが分かりました。このことは電波と共同観測をしていたから分かったことですが、ある意味では、これまで見つけにくかった小さいジェットでも発見できるという自信につながりました。
ジェットは、活動銀河の巨大なものから、中性子星やブラックホールから生じるジェットから太陽フレアまで、その規模はさまざまです。しかし、ジェットは突発的なもので、いつ何処で発生するか分からないため、全天観測をしていなければなかなか発見できません。そのため、これまでX線ではあまり観測されていません。X線新星や中性子星の連星系「Cir X-1」からのX線で、ジェット発生の瞬間を知らせる観測ができたことから、MAXIは世界の期待を集めています。
このように、大小さまざまなジェットの観測データを大量に集め、それを体系化したいというのが私の目標です。
理化学研究所 基幹研究所 宇宙観測実験MAXIグループ 特別顧問 理学博士
JAXA宇宙科学研究所 ISS科学プロジェクト室 プロジェクト共同研究員
東京大学助教授、旧文部省宇宙科学研究所客員教授を経て、理化学研究所の主任研究員、JAXA招聘研究員を務める。X線天文学が始まった1962年から、ロケット、気球、衛星を使ってX線天文学の研究に従事し、X線バースト、活動銀河、ガンマ線バーストなど幅広い初期の研究成果をあげる。また、MAXIの観測が始まって1ヵ月後の2009年9月に、イタリアで開催された国際X線天文学会に招待され、MAXIの初期成果を発表。MAXIを国際的にデビューさせた。