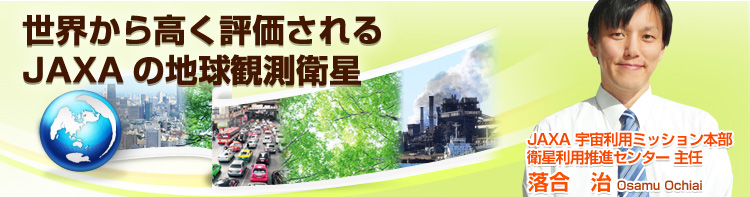Q. JAXAはGEOの炭素プロジェクトにどう貢献しているのでしょうか?

陸域観測技術衛星「だいち」

温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」
全球炭素観測と解析システムの構築を達成するために、先の「森林炭素トラッキング(Forest Carbon Tracking)」と「宇宙からの温室効果ガスの観測」という2つのタスクがあります。「森林炭素トラッキング」には「だいち」の観測データを提供しています。また、宇宙からの温室効果ガス観測については、「いぶき」は、雲がなければ3日間で全球の二酸化炭素とメタンの観測ができますので、今後データの検証が進めば、価値ある重要なデータになると期待されています。
特に、「だいち」は2009年の全球の森林・非森林の分類画像を、10mの分解能で作成しました。これほど高い分解能で、全球の森林分布を出したのは、「だいち」が世界で初めてです。森林は、地球温暖化の要因となる二酸化炭素を吸収して光合成を行っていますので、その面積等から、どれくらいの量の二酸化炭素を貯蓄できるかを調べることができ、温暖化問題を考えるうえでとても重要です。森林のモニタリングは「だいち」のほか、欧州宇宙機関の「ENVISAT」なども参加していますが、同時に同じ場所を観測することで、データの整合性を検証する作業も行っています。そして、それらの観測結果は国連気候変動枠組条約(UNFCCC)」などに報告しています。 Q. GEOのメンバーからは、JAXAに対してどのような期待がありますか?JAXAの衛星データには多くの期待が集まっています。特に、「だいち」と「いぶき」については、とても重要なデータを提供してくれると多くのGEOの参加国と機関から高く評価されています。
「だいち」は、森林炭素トラッキングによる「気候」分野への貢献だけでなく、アジア太平洋地域の自然災害の監視を目的とする「センチネル・アジア」や、世界の災害監視やデータの提供を行う「国際災害チャーター」といった国際的なプロジェクトを通じて、これまで「災害」分野にも多くのデータを提供してきました。今後は、「生態系」「農業」「生物多様性」といったほかの分野への貢献も考えられ、例えば、2010年10月には、「だいち」を利用した湿地の調査に関する協力協定が、ラムサール条約事務局と結ばれています。これは、湿地を生息地とする水鳥の生物多様性の調査に役立てられます。
また「いぶき」についても、気候変動の研究などにデータを使いたいという要望が世界中から来ています。
Q. GEOの炭素プロジェクトを通じて得るものは何でしょうか?

2010年11月に北京で行われたGEO閣僚級会合
GEOのプロジェクトで成果をあげることで、日本の次の衛星計画をきちんと進めていくことにつなげていきたいと思います。JAXAでは、地球環境変動観測ミッション「GCOM」、全球降水観測計画「GPM」、雲・エアロゾル放射ミッション「EarthCARE」といった衛星を打ち上げる予定がありますが、「だいち」や「いぶき」によって得た経験や実績が、きっと役に立つはずです。予算を確保するという意味でも、実績を残すことはとても重要だと思います。
また、国際協力で他国のメンバーと一緒に調整しながらプロジェクトを進めていますので、将来の衛星計画を立てる際、ほかの国との協力体制を築きやすくなっていると思います。例えば、「いぶき」の後継機をどうするかという大きな課題があります。2010年11月に北京で行われたGEOの閣僚級会合では、炭素プロジェクトにおいて科学要求としてまとめられたGEO炭素戦略報告書をもとに、JAXA以外の衛星も含めて、今後の計画をどうするかという話し合いが行われました。それを受けて、現在、JAXAでは、NASAやESA(欧州宇宙機関)などと調整しながら、炭素観測をする衛星の今後の計画を作成しつつあります。まだ調整は続くと思いますが、このような国際協調による将来の衛星計画の策定に係る調整作業も、GEOのプロジェクトに参加している成果だと思います。
そして何よりも、地球規模の問題となっている温室効果ガス削減に対する政治的な判断にGEOを通じて貢献するということは、国際社会において、大きな意義があると思います。
Q. 今後JAXAは、GEOの炭素プロジェクトにどう貢献していきたいですか?

JAXAとしては、今後もGEOに貢献していきたいと考えています。特に、「災害」「気候」「水」の3分野では、これからもっとデータの提供を増やしていきたいと思います。どのようなサービスでもそうだと思いますが、新しいデータを広く使ってもらうにはまず敷居を低くする必要があります。また、データを利用するためのさまざまなプロバイダ側のサポートも必要です。残念ながら個人的にはJAXAの衛星データはまだ十分広く活用されるまでには至っていないと思います。可能な限り使いやすいデータを積極的に無償で利用してもらうことにより、GEOのみならず世界標準の地球観測データとして位置づけられる事が可能になると思います。また、現在は気候変動が大きなテーマとなっていますので、「だいち」と「いぶき」を使って森林監視や温室効果ガスの観測を確実に実施し、成果を出していきたいと思います。
落合 治 (おちあいおさむ)
JAXA宇宙利用ミッション本部 衛星利用推進センター 主任
1994年、北海道大学環境科学研究科大学院修士課程修了。大学では地球物理学(気象)を学ぶ。同年、宇宙開発事業団(現JAXA)に入社し、地球観測プラットフォーム技術衛星「みどり」から陸域観測技術衛星「だいち」に至る複数の地球観測衛星ミッションのデータ情報サービスシステムの開発に携わる。2006年より地球観測に関する政府間会合(GEO)の事務局に複数システムからなる全球地球観測システム(GEOSS)の構造及びデータ管理のエキスパートとして出向。2009年より現職。
温暖化をまねく二酸化炭素の循環を探る
世界初!高精細な地球規模の森林マップ
環境問題解決に向けた日本の貢献に期待
世界の政策担当者が待ち望む炭素循環データの統合
信頼性の高いデータで温室効果ガス削減を実現