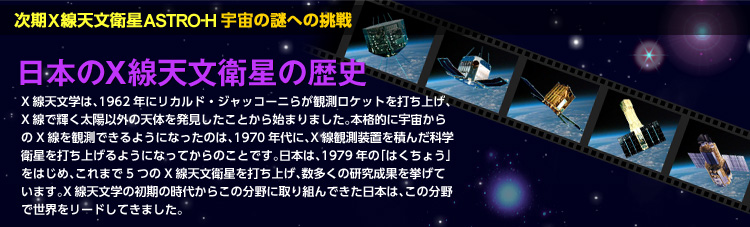打ち上げ日:1979年2月21日
サイズ:0.75m×0.75m×0.65m 質量:約96kg
ブラックホール天体「白鳥座X-1」にちなんで命名された、日本初のX線天文衛星。X線バーストと呼ばれる爆発現象など、X線天体から放射されるX線のスペクトルと、X線の強さの変化を観測。「すだれコリメータ」の搭載により、新天体の天空上の位置を決定。
主な成果は、新しいX線バースト源を数多く発見するなど。

打ち上げ日:1983年2月20日
サイズ:0.94m×0.94m×0.89m 質量:約216kg
「蛍光比例計数管」という新開発の装置によって、X線星、X線銀河、ガンマ線バースト、軟X線星雲などの観測を、優れたエネルギー分解能で行う。
主な成果は、銀河系の銀河面に沿って存在する、数千万度の高温プラズマを発見。X線天体から放射されるX線のスペクトル分析から、中性子星(超新星爆発の後に残る天体)の強い重力場などを明らかにした。

打ち上げ日:1987年2月5日
サイズ:1.0m×1.0m×1.5m 質量:約420kg
X線天体から放射されるX線の強さの変化を、高感度・高精度で測定することを目的とした衛星。打ち上げ直後に起きた、超新星1987Aから放射されるX線の観測に成功。ブラックホール、中性子星、超新星、活動銀河核、ガンマ線バーストなど、さまざまな天体からのX線放射の観測を行う。
主な成果は、超新星残骸や暗黒星雲内部の高温プラズマの発見。高感度をいかして、活動銀河核のX線放射強度の時間変動をとらえるなど。
また「ぎんが」では、観測機器を英国、米国など外国の研究者と共同開発するなど、国際協力が本格的にスタートした。

打ち上げ日:1993年2月20日
質量:約420kg
X線の撮像とX線天体のスペクトル観測を同時に行うため、X線望遠鏡および世界初のX線CCDと撮像型蛍光比例計数管を搭載し、感度を飛躍的に高めた。ブラックホール、活動銀河核等の観測だけでなく、超新星残骸では宇宙における粒子加速現象、銀河団では暗黒物質の分布と質量など、幅広い物理現象の観測を行う。
主な成果は、超新星爆発のX線スペクトルの変化を広帯域で観測。ブラックホールから放射される鉄輝線の、一般相対論から予言される効果の検証。超新星残骸の粒子の加速現象や、衝突・合体をしながら成長する銀河団の観測など多岐に渡る。

打ち上げ日:2005年7月10日
サイズ:6.5m×2.0m×1.9m 質量:約1700kg
「あすか」よりもさらにエネルギー分解能、角分解能ともに向上し、感度を高めた軟X線望遠鏡と硬X線検出器を搭載。より広いエネルギー範囲で観測を行う。
これまでの主な成果は、惑星状星雲にて普通の星により炭素などが合成されたことを観測、銀河団中でレアメタルを発見するなど、星から超新星爆発に至る元素合成の歴史を示す。銀河の分厚いガスや塵に隠されたブラックホールの発見。天の川銀河の中心で起こる爆発的現象の観測。超新星残骸で粒子が加速される証拠をつかむなど、宇宙の高エネルギー現象や、宇宙の構造と進化を研究している。現在も観測を行っており、今後も成果が期待される。
ブラックホールと銀河形成の関係を突き止める|宇宙の進化解明の鍵となる銀河団に迫る
日本のX線天文衛星が描く 新しい宇宙の姿に期待|ASTRO-Hの概要
異分野に展開されるASTRO-Hの技術|日本のX線天文衛星の歴史