理事長定例記者会見
奥村理事長の定例記者会見のトピックスをお伝えします
日時:平成28年11月9日(水) 11:00-11:30
場所:JAXA東京事務所 B1F プレゼンテーションルーム
司会:広報部長 庄司 義和
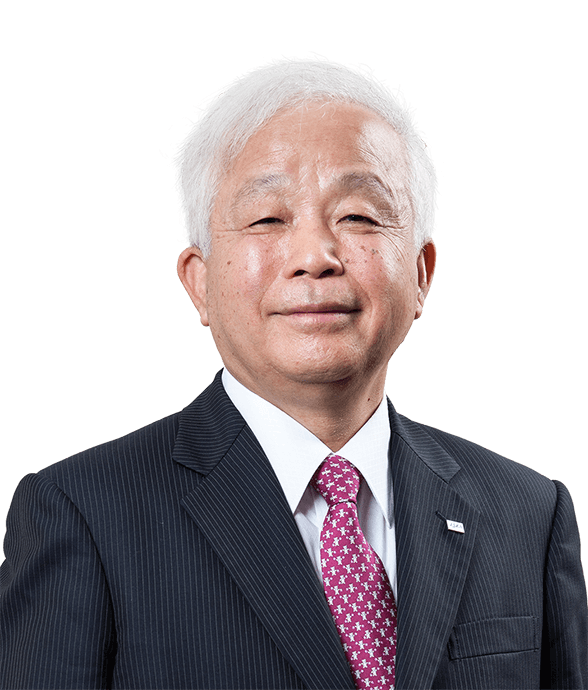
大西宇宙飛行士の帰還
皆さんご存知のとおり、大西宇宙飛行士は、10月30日に地球に帰還いたしました。現在は米国ヒューストンにて、リハビリを行っています。最新の情報では、日常生活にはほとんど支障がなく、昨日から自動車の運転を開始するまで回復したようです。本人曰く、飛行前の80%には回復しているとのことです。無重力から80%まで回復するのは比較的早いが、残り20%の回復には時間がかかるようで、そのプロセスが本当のリハビリだと認識しているようです。本人も、一日でも早く皆様に元気な姿をみていただいて、軌道上での活動内容についてもご報告させていただきたいと言っておりますので、期待していただきたいと思います。
今回の帰還にあたっては、着陸地点をはじめ、モスクワ郊外のTsUP(ツープ)管制センターにも多くの報道関係者の方々に取材に行っていただいたと聞いています。ご支援、ありがとうございました。
第23回アジア太平洋地域宇宙機関会議(APRSAF)
アジア太平洋地域宇宙機関会議(APRSAF)は、今年で23回目を迎えます。この会議は文部科学省とJAXAが中心になって、アジア太平洋地域の宇宙機関の皆さんと共同で、宇宙技術の発展、あるいは地域の抱えている社会課題の解決等に貢献しようと、毎年集まっているものです。今年はフィリピンのマニラで来週から開催されます。私も出席する予定です。今年は、37か国・地域の皆さんがご出席の予定で、今年のニューフェイスは、アジア地域ですとカンボジア、モンゴル、イランが参加する予定です。アジア地域外ですと、欧州からイタリア、スペイン、ノルウェーも新たに参加する予定です。その他、既存の宇宙国であるアメリカ、ロシア、ドイツ、フランス、イギリスは従来から参加しております。そういう意味で、この会議は、いまや国際的なオープンフォーラムになるつつあると感じています。
今年予定しているテーマを紹介しますと、特に力を入れているところは、東南アジア、アジア太平洋地域共通のテーマである自然災害です。私どもも国内でいろいろと展開しており、既に各国機関と協力して国際的にも宇宙技術を自然災害の抑制等に使おうとの活動を進めてきていますが、今回もこのテーマを大きく取り上げ、セッション等を設けて議論を行う予定です。
今回の統一テーマは、「Building a Future through Space Sicence, Technology and Innovation」(仮訳:「宇宙科学・技術・イノベーションを通じた未来構築」)として、各個別の課題を設定しています。その重要な一つが自然災害の抑制に関する宇宙技術アプリケーションになります。
もう一つは、今年の4月に国際宇宙ステーション(ISS)/「きぼう」日本実験棟から宇宙空間へ放出されたフィリピン初の国産衛星である「DIWATA-1」を事例として、若田宇宙飛行士をモデレータに迎え、現地の大学生、日本の大学生と開発に携わった経験談や、アジアにおける今後の宇宙開発への期待について検討をしていただくイベントを開催予定です。
もう一つご紹介しますと、大西宇宙飛行士がISS長期滞在中に、微小重力を活用した物理実験のアイデアを、APRSAF参加各国から募集し、120もの応募の中から選抜された5件の実験を軌道上で実演しました。この実験を行う際に、提案者の学生には日本に来ていただき、大西宇宙飛行士の実験実演の様子を直接目で見ていただきました。今回提案された方には、それぞれの国でご褒美があるようで、タイの大学生は、タイの科学技術担当大臣から直々に激励をうけたり、インドネシアの高校生は、居住地の市から奨学金を授与されることになったと聞いています。このように、「きぼう」日本実験棟を通してそれぞれの国々、地域の人たちにまで我々の活動が少しづず浸透してきているのかと受け止めており、宇宙を通してそれぞれの国の若い人の人材育成に、私たちも微力ながら貢献していると感じています。
環境問題への取り組み
モロッコのマラケシュで第22回気候変動枠組条約締約国会議(COP22)が開催されています。JAXAは、サイドイベントですが環境省、国立研究開発法人国立環境研究所(国環研)と共同で、人工衛星による温室効果ガス監視の取り組みや熱帯林監視に関することを紹介する予定です。
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、2006年制定の温室効果ガスの排出量/吸収量の算出・報告に関する「ガイドライン文書」を2019年5月に改訂する予定です。そこに向けて、今年の9月1日にJAXA・環境省・国環研が連名で「「いぶき」(GOSAT)観測データによる大都市等の人為起源二酸化炭素濃度の推定結果について」のプレスリリースをしていますが、これのポイントは、各地域で発生する二酸化炭素を、しかも人為的に発生する二酸化炭素を、「いぶき」(GOSAT)、あるいは地球観測衛星から推定できる可能性があるということを世界で初めて紹介した成果です。この成果が将来ガイドライン文書に採用されると、世界共通のツールとして、宇宙から二酸化炭素排出量をモニタすることにより、各国が個別に国連に報告する排出量の妥当性検証にも使える可能性があります。今回サイドイベントとしてCOP22の場で紹介させていただくことになっています。我々も温室効果ガス観測技術衛星2号「GOSAT-2」を準備していますので、更に精度を上げることができると期待しています。
航空技術部門が開発した数値解析プログラム「FaSTAR」を機体メーカーが利用
航空技術部門が開発した、数値シミュレーションツール「FaSTAR」を、日本の機体メーカーにライセンス契約で利用していただくこととなりました。ポイントの一つは、他の数値解析プログラムに比べて極めて高速で答えが出せるというところに特徴があります。そこに着眼されたのだと思いますが、三菱重工業株式会社殿にライセンス契約でご利用いただきます。 航空機の開発には、大変複雑な風洞実験、あるいは計算機シミュレーションで繰り返し最適解を求めるという、非常に大きな作業を行う必要があります。これは開発する目的の飛行機に要求される様々なニーズを取り込んで開発するので、膨大なエネルギー、時間、コストがかかります。そのために、空力性能の優れた航空機開発には、出来るだけ正確に、また速くシミュレーションで推定できる結果を得るということが設計にとって重要なツールです。これは一例ですが、飛行機の翼の形を少しずつ変えるなど工夫をして数値計算を行いますが、仮に1000ケースを計算するとなると、今回の我々のプログラムでは1日半で終わります。従来のやり方では約1000日かかります。仕事の質が変えられる本格的なツールであると考えています。当然このツールは社内でも使われていますが、近いところでは、低ソニックブーム設計概念実証(D-SEND)の実験でも使っており、最適形状を推定しています。ベースの技術ですが、いろいろなところで展開していくことが、我々の役割と認識しています。
実験用航空機「飛翔」による2つの飛行試験について
気象影響防御技術「WEATHER-Eye」では、飛行機の安全な運行を確保する技術の研究開発を行っていますが、名古屋に置いてある実験用航空機「飛翔」を使って実証実験を行う予定で、その一つがこのWEATHER-Eyeに関係するテーマです。先日も報道されましたが、羽田空港にも飛行機の発着回数が増えるということで、東京上空の飛行航路の設定等で議論があったようですが、そこで問題になるのが騒音です。もう一つ地上との関係で言いますと、翼に付く氷の落下も問題になります。特に今回は翼に氷が付き難くするシステム「ハイブリッド防除氷システム」の実験を行う計画で、これは航空機の翼などに付着する氷を効率よく取り除くことを目的にしています。
同時にこの実証実験の機会を利用して、もう一つ実験を行います。機体を軽くすることは永遠の課題ですが、軽くすると必然的に剛性が弱くなるという課題があります。この二つをどうバランスするかは永遠の課題です。特に実際に飛んでいる時の剛性確認が重要になりますが、今回飛行機を飛ばしますので、その機体に私どもが地上で開発している光ファイバーを使ったひずみ分布の方式を使って、実際にどういうふうに機体が動的に剛性が変化していくのかを測る実験を「飛翔」を使って、同じタイミングで実施する予定です。
実験は11月7日~14日に行う予定です、結果が出ましたら皆様にご報告いたします。